内容説明
中国の台頭、アメリカの後退、そしてロシアの暴走。国際環境は厳しさを増し、日本が安全保障で果たすべき責任は重くなっている。しかし日本では憲法をはじめ、一度でき上がった独特な仕組みをなかなか変えられない。危機の時代にふさわしい防衛の姿とは。日米安保条約、憲法第9条、防衛大綱、ガイドライン、NSC(国家安全保障会議)という重要トピックの知られざる歴史をたどり、日本の安全保障の「常識」を問い直す。
-
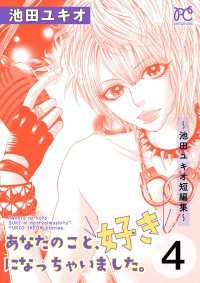
- 電子書籍
- あなたのこと、好きになっちゃいました。…
-
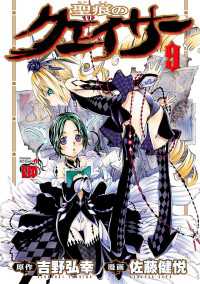
- 電子書籍
- 聖痕のクェイサー 9 チャンピオンRED






