- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
2008年に著者は、日本各地の動物園・水族館にいる、動物と動物に関わるひとびとを訪ねる連載をスタートさせる。「動物園とは動物を収集・飼育・展示する施設である」この定義から導かれる、動物園の持つ原罪とは何か。動物園のメディアとしての特性は何か。動物を擬人化してもいいのか。飼育係は、どのように動物と関わるのか。共同通信の記者が全国をまわって考えた、動物園の過去、現在、そして未来。
目次
はじめに 生きものスルーから「生きもの大好き」へ/第一章 動物園へ行く/1 増井光子さんの拒否から始まった/園長のリレー連載を企画する/執筆依頼して玉砕、逆に説得される/園長、記者の劣化を嘆く/2 連載をスタートする/反戦を訴えるドゥクラングール/ダスキールトンの死と飼育係と女の子/オカピを「かわいい」と言わせたい/コウノトリ野生復帰の現場に行く/池田啓さんのメディア批判/3 昆虫生態園で問いを突き付けられる/飼育係は調理人でもある/展示できないチョウもいる/ボーンフリーという言葉を知る/擬人化は常に否定されるのか/第二章 動物園を知る/1 動物園とは何か/客観性を否定するタイトル/リード文に隠された難問/大規模動物園に違和感を持つ/必要条件から定義を試みる/法律も動物園を定義してこなかった/定義からメディアとの相似性をみる/定義が露わにする支配・侵害/最大の侮辱は「見世物」という言葉/原罪を消す逆説的な方法/2 正当化するための「四つの役割」/中川志郎さんとJAZAの大きな違い/域外保全は「動物園保全」と呼びたい/「たかがカエル」というなかれ/生きものに出会うこと自体が教育/「野生からの使者」として研究する/文体からして楽しげな「レクリエーション」/生きものにとっての不当さは消えない/五六文字の侵害極小化宣言/公共性と商業性の相克もメディアに似る/3 ゾウのシンポジウムから広がる出会い/求む! 良き水先案内人/会うべき人を浅倉義信さんに教えてもらう/錦織一臣さんの基礎的だが深い話/二刀流にチャレンジする/入江尚子さんの魅力的な応答を記事に/遠藤秀紀さんの扉をたたく/「かわいそうなゾウ」の骨どこへ?/第三章 動物園で学ぶ/1 『かわいそうなぞう』の虚構と真実/本質的使命を果たしているか/空襲はなかったのにゾウが殺された/殺害を命じたのは軍部ではなかった/最大の動機は市民への警告/絵空事のクライマックス/「時局捨身動物」という擬人化/ジョンの殺害着手が早かったのはなぜか/再びなぜ「逃がしてはいけない」のか/Zoo is the Peaceと唱えるだけでは……/わたしは石をなげうてるか/2 カリスマとノンカリスマ/目玉がないところが目玉/ノンカリスマ種にこそ注目せよ/イカに人生をささげる/サンマがカリスマ種に転化する/3 「擬人化」の二つの方向性/天皇と握手したチンパンジー/おサル電車はなぜ消えたのか/事実婚でさえない雌雄のカバ/ハチ公像が〝誉れの出陣〟/ハチ公の実像をどう見るか/4 擬人化が開く回路/『雪の練習生』が表現する動物の人権/シロクマピースが教えてくれたこと/わが子に「飼育」はそぐわない/忘れないゾウと号泣する雄牛/名付けるとき立ち上がる人格/死出虫のリアルの果てに/第四章 動物園で考える/1 アニマルウェルフェアとは何か/動物の幸せを科学する/マガモになったローレンツ/環境エンリッチメントは「うれぱみん」/とことん愛されて幸せなマナティー/緑に囲まれた生息環境展示はうれしい/2 ウェルフェアの傘を広げたい/山本茂行さんが飼育係にこだわる理由/ヒューマンエラーは必ず起きる/人間の安全に対して脆弱な体制/下村幸治さんが説く幸せな動物園/生きものと人のウェルフェアを定義に/3 消えていいのか「命の博物館」/巡回シンポで訴えた危機とは/自然を生かし人と人をつなげる拠点に/市民が望んだ緑と生きものの公園/クラゲで巨大水族館に対抗する/魚歴書に通信魚……べらぼうに面白い展示説明/漫画を描いて動物の気持ちを通訳する/ポップな水族館が固定観念を砕く/飼育係自身が発信してほしい/消えるときが来るまで/おわりに/取材した動物園水族館/主要参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
gokuri
C
お抹茶
onepei
-
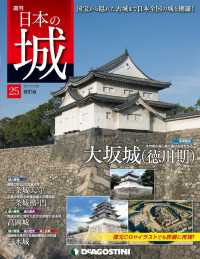
- 電子書籍
- 日本の城 改訂版 - 第25号
-
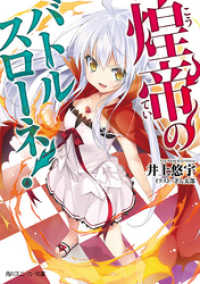
- 電子書籍
- 煌帝のバトルスローネ! 角川スニーカー…





