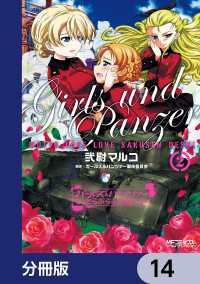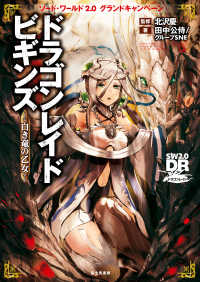内容説明
情報社会を支配する相互評価のゲームの〈外部〉を求め、「僕」は旅立った。そこで出会う村上春樹、ハンナ・アーレント、コリン・ウィルソン、吉本隆明、そしてアラビアのロレンス――。20世紀を速く、タフに走り抜けた先人の達成と挫折から、21世紀に望まれる主体像を探る「批評」的冒険譚。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
42
著者の前著が良くなかったので、しばらく様子をみていた本。読むとはなしに数ページから止まらなくなり、30ページくらいで良い本だと確信を得る。ネットワークに外部は無い。とすれば空間ではなく時間をずらす。そこで著者のキーワードである「遅いインターネット」ということだが、実は著者の言っていることとは合っていない。当然、時間も場所もずらす。著者の言わんとするところは、あえて同期しないことによる異化効果ということだ。コロナ禍真っただ中に100年前のアラビアのロレンスを訪ねる。彼の『知恵の七柱』を彼の内面を探る文学とし2022/12/17
kei-zu
25
「アラビアのロレンス」を「情報に溺れる」現代人の先駆けと、村上春樹を「情報へのアプローチを行う」現代人の一側面と、それぞれ分析を行う。 村上の作風の変化について「デタッチメント(関わりのなさ)」から「コミットメント(関わり)」に変化したという。なるほど、私が同氏の小説に手が伸びなくなったのは、そのタイミングであった。 著者が提唱する情報への「遅い」関与は、これまでの著作を踏まえ、引き続き興味深くある。2023/02/22
かがみ
7
「空間的外部」を消失した「空間的内部」における「時間的外部」を切り開くための理路として村上氏が「速さ」を追求したのだとすれば、宇野氏は「遅さ」を肯定したといえる。これはどちらが「正しい」という話ではないと思う。少なくとも、いずれかを「正しい」とする二項対立的な思考こそがまさしく「相互評価のゲーム」に囚われた思考ではないか。自らの理想に向かう「速さ」の追求とその理想から逸脱する「遅さ」の肯定というダブルシステムのあいだを自在に往還するということ。それこそが本当の意味での「自立」であるように思える。 2023/08/31
ZUSHIO
7
事前に予習として『アラビアのロレンス』を観ておいて、村上春樹も読み込んでいるので、この本の言わんとしていることが、実によく分かった。自分の感覚的な把握としては、吉本隆明曰くの自己幻想や対幻想や共同幻想の三幻想によって閉ざされた状態であれば、SNS時代の今に始まったことではなく、外部(砂漠)にも内部(壁抜け)にも真の実存はないということ。 三島由紀夫的(村上春樹的)自己幻想の如く体を鍛えるわけでもなく、街中をゆっくり走れという処方箋は、殊にもうタイムを追求しないジョガーである私には共感度は100%だった。2023/01/01
なつのおすすめあにめ
7
『リトル・ピープルの時代』を読んだときに『仮面ライダー555』のオルフェノクと『木更津キャッツアイ』のぶっさんという、遠い二つの存在を並べて考えるスタイルに衝撃を受けたが、今回は『アラビアのロレンス』(の、砂漠)がコアアイディアで、相変わらず村上春樹がdisられている。「身体感覚を取り戻す!」みたいなのもやりすぎると三島由紀夫のように切腹しなくてはいけないから、「深夜のネットサーフィンの結果たどり着いた、誰かのホームページに書き綴られた文章を明け方まで通読したときの罪悪感と充実感を思い出すこと」、それぬぁ2022/11/13