内容説明
相手に何かを伝えるため、人間は即興で言葉を生みだす。それは互いにヒントを与えあうジェスチャーゲーム(言葉当て遊び)のようなものだ。ゲームが繰り返されるたびに、言葉は単純化され、様式化され、やがて言語の体系が生まれる。神経科学や認知心理学などの知見と30年におよぶ共同研究から導きだされた最新の言語論。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サアベドラ
38
言語は身振り手振りによるコミュニケーション、すなわちジェスチャーゲームから生まれたとするポピュラーサイエンス的言語起源論。デンマークの認知言語学者とイギリスの認知行動科学者の共著。チョムスキーらの生成文法論に真っ向から反対する主張であるが、生成文法自体にずっと違和感を抱いていた評者からすると本書の論の方がむしろ自然に思える。論証が若干甘い気がするが、一般向けなのである程度はやむなし。言語は第一義がコミュニケーションなのだから、指示語が重要な位置を占めるのは当たり前で、自分の頭でっかちさに気付かされた気分。2023/03/25
踊る猫
32
実に大胆な本だ。常識的に考えれば私たちは外在する/外にあらかじめある言語体系を学び、それを自家薬籠中の物としてそれからコミュニケーションを開始する、となるだろう。しかし著者たちは私たちの言葉が「即興」と「ジェスチャーゲーム」で成り立っていると喝破する。そして、その偶然性に支えられたコミュニケーションが進化することが人間の進化とシンクロしたのだ、と。私は言語学に関してはまったくもって門外漢なので真偽の判定はできないが、リアリティを感じる理論だと思う。コミュニケーションの偶然性と奇跡。そこから哲学を見出せるか2023/01/08
masabi
8
ジェスチャーゲームを通じて言語が洗練されてきたと主張する。人間には生得的に言語を獲得する機能があるとする生成文法に反対する立場で、言語に確固とした基盤はなく、その場その場での即興のやり取りと過去の蓄積からなる文化的な所産だとする。2024/12/22
みかん。
8
1ヶ月ほどかけてちまちまと読了。伝統的に純然たる文系学問であった言語学は脳科学や生物学などの理系学問を取り込んで模索をしたのだけど、近年は言語学では少しずつ理系から文化やコミュニケーションなどへの重視(文系学問への揺り戻し)が再び出てきているらしい。私見ですが、これら「文系への回帰」は情報技術やインターネットの発展とも無関係ではないと感じました。2023/02/12
kanaoka 58
6
言語の起源は、ジェスチャーゲームであり、その蓄積が慣習化し、一定の体系にまとまっていったもの。言語の習得は、このゲームの達人になり、日常的なやりとりをこなせるようになることであり、抽象的な文法パターンを学ぶことではない。会話は当事者の共同作業(ゲーム)により構築されるもので、そのためには、言葉の下に隠れた文化、知識、規範等々、相手の関心事、共感、観察・理解が必要となる。 語学を苦手とする者(私)にとって、外国語を勉強するうえで、本書の内容は大変役に立つものになりそうです。2023/02/12
-
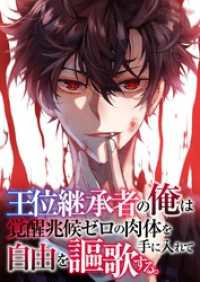
- 電子書籍
- 王位継承者の俺は覚醒兆候ゼロの肉体を手…
-

- 電子書籍
- 暴君の子を授かりました【タテヨミ】第4…
-
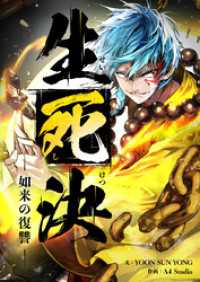
- 電子書籍
- 生死決~目覚める真人~ 如来の復讐【タ…
-

- 電子書籍
- プランダラ【分冊版】 100 角川コミ…





