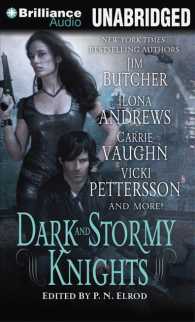- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
東京やニューヨークのような都市はなぜ生まれるのか? 大都市が繁栄を極めるかたわらで、地方は過疎の一途をたどっている。輸送技術と情報技術の発展により世界の都市化が急速に進むいま、人々が集まる原理から現代の課題まで、都市経済学から考える。
目次
はじめに 都市を研究する
第1章 なぜ都市ができるのか
1 自給自足の時代
2 交易がもたらす変化
「比較優位」と「機会費用」
3 労働生産性が重要な理由
4 分業による協業と規模の経済
技術革新が起こるとどうなるか
この節のまとめ
5 同じ産業が一つの地域に集まると生まれる地域特化の経済
マーシャルの経済
集積によるリスクの低減
消費者の誘致
6 大都市ができあがることで利益が生まれる都市化の経済
労働者が集まるメリット
公共財の充実
第2章 「多様性」と「輸送費用」の役割
1 輸送技術の発達と費用の低下
2 日本の都市化から見る人口移動の重要性
3 多様性が大都市で果たす役割
多様性が高まりやすい場所
「中間投入材」の多様性
スキルの多様性
4 消費の多様性(多様性と集積1)
輸送費用が下がると起きること
最初の小さな差が大きな差になっていく
歴史的な偶然
一方には損をする人も出てくる
5 中間投入財の多様性(多様性と集積2)
6 スキルの多様性(多様性と集積3)
7 輸送費用の低下は現在も止まっていない
第3章 集積と経済成長
日本のGDPの移り変わり
1 経済成長のメカニズム
資本蓄積
技術の進歩
人的資本の蓄積
2 日本の高度成長期に起きた集積
第4章 少子化と都市
1 少子化の原因
夫婦が子供の数を決める要因
子供にかける教育費
賃金水準の上昇
女性の賃金水準の上昇
消費財の多様性と子供の数
子供を持つことと消費活動を天秤にかける
2 都市部で出生率が低くなる原因
都市の生活費と出生率
多種多様な消費財が大都市の子供の数を減らす
大都市で高くなる教育費
都市と地方における女性の賃金格差
第5章 情報通信技術の発達がもたらすもの
1 都市における知識やアイデアのやり取り
知的な生産活動では顔をあわせることが重要
2 本社機能を地方へ移すことにメリットはあるか
3 出会うことのなかった人々の新たな結びつき
新たな情報伝達技術は都市の役割をむしろ強化する
第6章 東京は本当に大きすぎるのか
1 適正な人口水準
賃金と通勤費用と土地の価格
都市に住む人の数と土地の価格の関係
人口が増えることのメリットはあるか
集積の経済の効果を計測することは難しい
東京の人口規模が大きすぎるはっきりとした証拠はない
2 東京一極集中と過疎化する地方
一極集中と過疎化を是正することに合理性は本当にあるのか
少子化は理由になりうるか
おわりに
参考文献一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kei-zu
yyrn
ヒナコ
奈良 楓
まゆまゆ