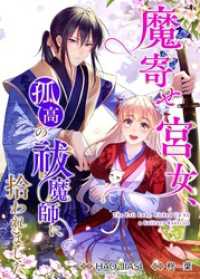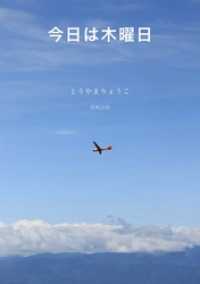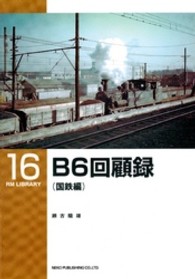内容説明
8~11世紀にかけて西欧諸国に恐怖に陥れたヴァイキング。しかし彼らは単なる略奪者ではなかった。時に傭兵として、商人として、あるいは政治的支配者として東西ヨーロッパの歴史に深く関与し、他方で農業を生業として独自の法的社会を築いており、その実態は一様には語れない。本書では主としてアイスランドのサガを用いてその社会を再構成し、歴史的存在としてのヴァイキングの全体像に迫る。ヴァイキング史の碩学による通史。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キャプテン
35
★★★★☆_「世界はきっと、ぼくのものフェア」第三弾、ヴァイキング編。侵掠のイメージが強く、海賊という側面が印象深いヴァイキング。アングロ・サクソン人の島となったブリテン諸島を襲撃。イギリス北部にデーンローという場所があるのは、ヴァイキング(デーン人)が住み着いたことに由来するほど、イングランドの文化にヴァイキングは入り込んでいる。そんなヴァイキング、この本を読むとイメージが変わってきて、海賊的存在というより、出稼ぎ軍団に思えてくる。少し乱暴で、とても純粋な存在に思えてくる。北欧に一度行ってみたくなった。2019/10/11
六点
10
斯界の古典にして基本書。掠奪を旨としていたわけでは無いのは知っていたが、世界は何処でも中世は自力の時代であったのだなあ、と、思う。「個体発生が系統発生を繰り返す」を地で行く様な「アイスランドのサガ」解読による、ヴァイキング社会の成立と発展は大変に興味深かった。現代の政治とは歴史とは無縁で成立し得ないのだが、北欧のその後に於いて、王権の成立に遅れた結果、独特の北欧の政治体制となったのであろうなと思わせる。最後にできたアイスランドが、ある意味ゲルマン人の古層を残している事に得心がいった。2020/04/18
shimashimaon
5
ロシアの起源がルーシというヴァイキングであったことをきっかけに『ヴィンランド・サガ』にハマり本書に辿り着きました。面白かったのは第6章「血の復讐」です。法治国家で生きる我々には自立救済権がない代わりに公権力が強制力を行使して秩序を維持しているので、公権力がなく復讐が認められる世界は無秩序で恐ろしく感じます。しかし実際は厳然たる法秩序だということがよくわかります。『ヴィンランド・サガ』はまさに復讐がテーマですが、極めて厳格なルールが存在することも表現されていて惹かれます。荒正人先生の本も古本で入手しました。2025/11/30
Mana
5
ヴィンランド ・サガ作者の推薦本。直接ヴィンランド・サガとの関連はないけど、彼らの文化を知ることで登場人物たちへの理解が深まった気がする。決して暴力が荒れ狂うだけの世界ではなく、その中でも法律や規範が存在する。女性にも限定的ながら相続権が認められていたのを知ってイメージが好転したけど、略奪婚が普通に行われていたり、過度な理想化は厳禁だと思った。印象的なのは血の復讐は権利であり義務でもある。トルフィンの行動は個人的な感情の他に、ヴァイキングの価値観もあるのだと知った。2019/07/17
スプリント
5
知られざるヴァイキングの生活が書かれており楽しめました。歴史よりも文化史、風俗史的な内容です。2017/05/31