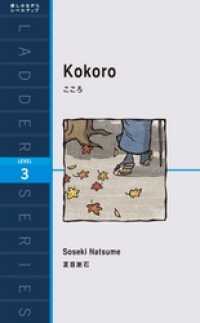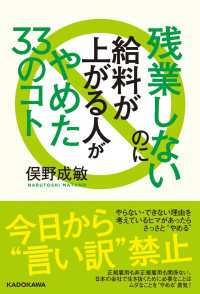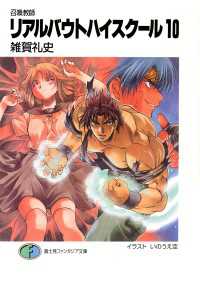内容説明
失礼なことを悪気もなく言ったり、
繰り返し約束を破ったり遅刻したり、
すぐに泣いたり怒ったり、
じっとしていられなかったり…
理解に苦しむその言動も、本人たちが物事をどう受け止め、感じているのか、つまり“見ている世界”を理解し、その対応策を学ぶことで、ともに生きるのが楽になるはずです。
たとえば、「発達障害の人には社交辞令や皮肉が通じない」といいう困りごとの場合、その理由が「脳の特性により、言葉を字義通りに受け取ってしまう」という原因によるものだと知れば、少しは気持ちが落ち着くでしょう。
そして、「発達障害の人と話すときは、極力ストレートな表現を心掛ける」という対処法にも納得がいくはずです。
この本では、大人から子どもまで、そんな身近にある困りごとを32個紹介し、その理由と対応策を紹介しています。
「自分も発達障害かも?」と思う人も、生きづらさの正体を知ることで適切にサポートを受けたり、対応策をとったりしていくことで、困りごとが解決されていくことでしょう。
特性を持つ子どもの親御様も、子育てが少し楽になるはずです。
定型発達の人でも、発達障害の特性に似た傾向を持つ人は、決して少なくありません。
また、発達障害との診断はくだらなくとも、発達障害の特性を持つ“グレーゾーン”の人もいます。
発達障害なのか。
グレーゾーンなのか。
定型発達なのか。
そういった診断的な面だけにこだわらず、さまざまなコミュニケーションの困りごとを解決するツールとしてこの本がお役に立てれば、これほどうれしいことはありません。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
馨
98
職場に発達障害と診断された同僚がいます。また、診察していないだけでそうだろうなと思う人も数名います。現代では名前がついたけれど昔は無かったと思うので、名前がつくと自分もかも?と思う人も何気に多いと思います。読んでいたら、こんなことも特性の一つなのかと思うような、欲しいと思ったら止められず何でも買ってしまう、とか、片付けられないとか、細かく分類したら誰でも当てはまるようなこともあって驚きました。2025/01/11
読特
86
空気が読めない、会話が成立しない。優先順位がつけられず、約束時間が守れない。はまると我を忘れる。臨機応変に対応できない。夜は寝られず、朝は起きられない…ADHDは20人に1人、ASDは100人に1人。付き合いにくいと感じられる中、彼らも傷つき安さを抱えている。一方、肯定的な面もある。多動性の行動力、抜群の記憶力、発想力という強力な武器。発達障害は病ではなく特性。理解が必要。とはいえ、安易に行動の問題を発達障害に帰着するのはよくない。悪意ではないのか、矯正可能か。個性を尊重しながら生き易い社会を目指すべし。2024/01/05
k sato
59
「違う文化の人なんだ」と捉えて接するのもコツ。発達障害を持つ人の行動や心理の本質を解説した一冊。この本では、家族や職場の人が、当事者の特性を理解して手助けすることが必要だと訴えている。また、論理的ではなく感覚優先で指示をする古い企業文化が当事者を混乱させていると述べている。私見であるが、当事者が自らの特性を理解することも大事だと思う。正確で規則正しい日本の文化に適応しようとするから、当事者が苦しむのではないか。こう考えると、これらは、当事者に限った話ではない。激変する時代の生きづらさは当事者だけではない。2023/07/17
Natsuko
55
精神科を訪れ、発達障害の診断を受け、むしろほっとしている方が多いと聞く。対応法を取り上げる本も増えているが、本著はその現状と直面するドクターが、「脳の発達に特性をもつ方に見えていると思われる世界」を分かりやすく説明したうえで、本人と周囲の人々が対策を「取り合う」というスタンスであるのがいい。「ただ一方で、近年発達障害の認知が広まったが故の弊害として、多くの問題を安易に発達障害へ帰着させようとする空気がある」というあとがきにも共感。ASDとADHDの特性の解説も分かりやすく、今後大いに役立ちそう。2024/07/27
TATA
50
さらっと一読する。軽めかなと思って読むととても沢山の示唆がある一冊でした。社会が成熟するという事は多くの人が不便なく生きられるということかもなと考えるとこの手の示すことがとても大事に思えます。2024/11/14