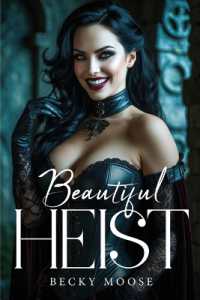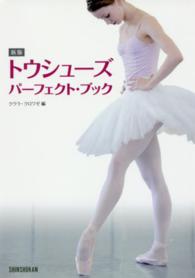- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
大学が近くにあることは、自治体にとって地域活性の起爆剤になり得る。高校生が地元で文系・理系だけでなく、看護、芸術といった特色ある教育を受けたり、病院など大学付属機関も誘致できるかもしれない。……とはいえ、地方大学の開学には、国公私立いずれの場合も、財政的な負担が大きい。卒業生が地域に残るかも不透明。これまでに撤退した大学も全国では少なくない。人口減少によってどちらも縮小が予測される自治体と大学。その関係史を紐解き、両者の望ましい協働、今後のゆくえをさぐる。
目次
はじめに/第一章 大学の誕生──戦前の大学誘致、戦後の新制大学/大学とはどのような存在か/国立大学とは/公立大学とは/私立大学とは/自治体とは/帝国大学の誕生/悪しき「慣例」の始まり/京都の次の帝国大学はどこに?/九州帝国大学誘致運動/福岡県、長崎県、熊本県の誘致運動/なぜ京都帝国大学福岡医科大か/九州帝大が先か、東北帝大か/公立大学の誕生/全国初の市立大学は大阪商科大/旧制専門学校から新制公立大学へ/現存する新制公立大学は医歯薬系が半分強/新制国立大学の設置に関する一一原則/第二章 公立大学無用論──財政負担、私学移管、新構想大学の誘致……/公立大学を手放す理由/国立移管された公立大学──静岡県、茨城県、岐阜県……/国立に移管するにも金が必要/公立大学と市の衝突/道楽息子は養子に出すべきか──金沢美術工芸大学の場合/コネ入学問題に揺れた高崎経済大学/私学移管騒動まで勃発/高崎市の財政負担はどのくらいだったのか/百条委員会まで設置された都留文科大学/教育委員会でなく、首長の職務権限/国立学校の新設と政治家の関わり/国立高専一期校と自治体/長岡・豊橋の技術科学大学──新構想大学の誘致1/上越・兵庫・鳴門の教育系大学院──新構想大学の誘致2/鹿屋体育大学、北陸・奈良の先端科技大──新構想大学の誘致3/昭和四〇年代以降の公立大学設立の動き/文部省の方針転換/第三章 平成、令和の新設ラッシュ──国策としての大学〝改革〟/「アメリカの大学」誘致/「アメリカの大学」誘致の三類型/潮目が変わった大学政策──契機は看護系大学の設置/公立大学にも法人化の波が到来/石原都政と東京都立大学の解体と再編/東京の公立大学トップダウン改革の是非/東京都立大学への先祖返り?/大阪の大学統合/府市合わせの統合の先に/特定分野に特化した九〇年代の新設公立大学/二〇〇〇年から二〇一〇年代にかけての新設公立大学/公設民営大学の設置と公立化/二〇二〇年以降の公立大学新設の動き/第四章 変わる関係──高等教育は大都市でしか受けられないのか?/歴史からみえてくる自治体と大学の関係/自治体と国立大学の関係は財政次第/変わる、自治体と国立大学の関係/自治体と公立大学の関係/自治体と私立大学の関係/大学教員出身の首長/国公私立大学ごとに異なる家庭の経済状況/都道府県ごとの大学数格差/市町村の大学誘致メリット/小さな村と大学の関係/大都市部への大学の集中/国による都市部集中への規制/大学と組織の名称/自治体と高等教育政策の関係/文科省の大学COC事業とは/大学誘致に強いコンサル/再び国の規制強化が/自治体と大学の連携協定/アメリカ州立大学の状況/アメリカ以外の大学の状況/日本と海外の大学の比較/第五章 自治体の戦略と私大の地方展開──成功と失敗の分かれ道/私立大学の地方展開/難しくなる大学誘致/大阪府高槻市の大学誘致支援調査から/東海大学の事例──私大の地方戦略見直し1/東京理科大学の事例──私大の地方戦略見直し2/立命館大学の事例──私大の地方戦略見直し3/大学を増やす自治体の戦略/新潟県の地元志向/新潟県に続々誕生する公設民営大学/県と市がコラボして誕生した山形の東北芸術工科大学/山形県が主導した東北公益文科大学/教育県・長野の大学事情/高校生に「優しくない」長野県?/最も大学過疎だった長野市/熾烈だった福島県の大学誘致合戦/東海大学の誘致を断念した郡山市/迷走する郡山市の大学誘致/明星大学誘致を巡る白河市といわき市の明暗/粘りに粘って県立大学開学にこぎつけた会津若松市/大学撤退に翻弄された北海道紋別市/最後は自前の大学をつくった函館市と釧路市/公立大学を設置しなかった栃木、徳島、佐賀、鹿児島/都内や大阪府内の大学誘致/大学誘致の事例からみえてくるもの/第六章 大学冬の時代──撤退・廃止・合併/一八歳人口の推移/大学冬の時代の到来/勝ち組と称された自治体でも大学撤退/大学撤退を巡って、変わり身の早い自治体も/学校法人による「事業継承」/北海道での「事業継承」/大学への多額の補助が問われる時代へ/加計学園グループと自治体/今治市における補助金の妥当性/マスコミ報道の論拠/獣医学部の定員に関して/問題の本質は何だったのか/私立大学援助の効果は五〇倍/揺れる大学のガバナンス/二〇四〇年、消滅可能性大学は……/冬の時代のシナリオ/大学はどこへいく/自治体はどこへいく/おわりに/参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
すのさん
まる@珈琲読書
もけうに
お抹茶
今Chan