内容説明
心は、脳の中だけにあるものではない 生命の心は、脳と身体と世界の相互作用から創発する。認知科学の第一人者が、微生物や人工生命などの例を交えて提起する心の科学
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ばんだねいっぺい
24
知的なヒントが渋滞しているすごい本。身体的認知にとっての外部環境がいかに大切かというところがいちばん 刺さった部分だ。2023/05/29
原玉幸子
18
ロボット工学から、脳神経学、認知科学、哲学や言語学まで考察を広げている本書は、A・ダマシオ『意識と自己』、渡辺正峰『脳の意識、機械の意識』などでの私なりの理解、「意識=(本書での)認知とは」が主旨の気がします。付録にあった「認知の統一理論」を目指す、との表現が分かり易いかと思います。ですが、専門的な箇所が難しいのか冗長で退屈なのかが分からないまま、結構読み飛ばしました(恐らく後者なのでしょう)。科学者仲間達が偉大な先生の論考を翻訳するのは、広く理解されるより「通好み」過ぎたかも。(●2023年・春)2023/02/04
mim42
11
前世紀末に書かれた認知科学・心の哲学についての革新的な啓蒙書。中央集権管理器官としての脳が記号処理的に心を産み出すという視点から、脳と身体・環境の相互作用と共進化が「心」を創発するというパラダイムシフト。その証左的役割でコネクショニストモデル(=ニューラルネットワーク等の並列分散モデル)が至る所で登場するのは興味深い。20年後の自由エネルギー原理等の議論に自然に繋がりそうな仮説・推察。実際に、付録の講演の質疑応答ではサプライズ最小化の議論が行われている(殆どの質問者が稚拙に見えるのは逆過去美化バイアスか)2024/11/04
武井 康則
10
考えることを本書では精神とか心と言っているが、それは知識ではない。人工知能に知識を与え続けてもうまくいかなかった。学習すること、習得とは脳と環境が出会い、互いに働きあうことで到達、達成される。数々の実験からそれが実証され、アリなどの群れがリーダーのないまま一匹一匹が目の前の自然に働きかけることで創生が生まれる。現在人工知能の研究が脳の研究を加速させているが、その結果脳についての常識が覆り、知識の神話も崩壊しつつある。知恵は目の前の環境に全身で働きかけ、その中で様々な試みを繰り返し、織り成していくものだ。2025/01/03
人生ゴルディアス
9
文庫落ちなので油断していた。認知科学における対立する"脳概念"を議論するなど、かなりヘビーな内容だった。脳は外界から五感を通してシグナルとして受け取り、それを内部で計算して出力するだけのものではなく、また、シンボルという内的な概念を”心”に蓄えそれを操作するものでもないと言い、その中間を探っていく。脳は計算リソースを減らすために外界を構造化させ、構造化されたものを見た他人の脳が刺激されて新たなる構造化をする。そして人間はたまたまそれが他の動物より得意だっただけ……みたいな話が本当に面白かった。2022/11/16
-
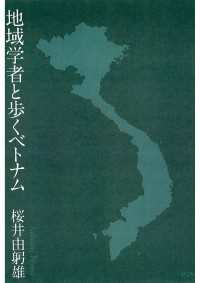
- 電子書籍
- 地域学者と歩くベトナム
-

- 電子書籍
- モブなのに過保護な公爵に溺愛されていま…
-

- 電子書籍
- 感受点 サイコミ×裏少年サンデーコミッ…
-
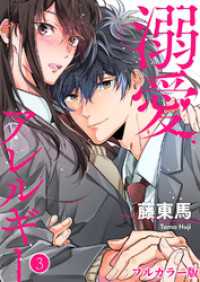
- 電子書籍
- 溺愛アレルギー【フルカラー版】3 チェ…
-

- 電子書籍
- 死願者ゲーム -死にたい奴は、生き残れ…




