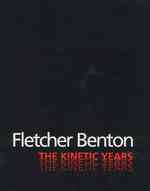内容説明
つまずきの原因を「読解力が足りない」で済ませては支援につながらない.著者らは学習の認知メカニズムにもとづいて,学力の基盤となることばの知識,数・形の概念理解,推論能力を測るテストを開発.その理念と内容,実施結果を紹介し,それで測る力が算数・国語の学力とどのような関係にあるのかを質的・量的に検討する.※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.
目次
はじめに
第1章 「ことばのたつじん」「かんがえるたつじん」の基本理念 学びの前提を測るテスト
1-1 開発の意図と目的
1-2 学力とは何か
1-3 「生きた知識」とは何か
1-4 「生きた知識」を使うために必要な認知能力
1-5 テストデザインの基本理念
1-6 テストの使い方
第2章 誤答から見える算数学力
2-1 算数文章題テスト
2-2 3, 4 年生用問題の誤答タイプ
2-3 5 年生用問題の誤答タイプ
2-4 誤答分析のまとめ
2-5 個人差
2-6 階層ごとの誤答タイプの分布
第3章 「 ことばのたつじん」による言語力のアセスメント
3-1 テストの概要
3-2 「ことばのたつじん①」 語彙の深さと広さ
3-3 「ことばのたつじん②」 空間・時間のことば
3-4 「ことばのたつじん③」 動作のことば
3-5 言語力の個人差
3-6 「ことばのたつじん」と学力の関係
第4章 「 かんがえるたつじん」による思考力のアセスメント
4-1 テストの概要
4-2 「かんがえるたつじん①」 整数・分数・小数の概念
4-3 「かんがえるたつじん②」 図形イメージの心的操作
4-4 「かんがえるたつじん③」 推論の力
4-5 「かんがえるたつじん」と学力の関係
第5章 「 ことばのたつじん」「かんがえるたつじん」と学力の関係 統計分析
5-1 算数文章題テストを学力の指標とした重回帰分析
5-2 標準学力テストを学力の指標とした重回帰分析
5-3 重回帰分析からの考察
第6章 学習のつまずきの原因
6-1 知識の問題
6-2 推論と認知処理能力の問題
6-3 相対的視点と認知的柔軟性の問題
6-4 読解力と推論力の問題
6-5 複数要素の統合への手立てが重要
付録1 ほんものの学力を育む家庭環境 保護者アンケート調査から
A-1 保護者アンケート調査
A-2 家庭環境が学力に及ぼす影響
A-3 ほんものの学力を生む家庭環境
付録2 「ことばのたつじん」「かんがえるたつじん」の開発の過程
付録3 「ことばのたつじん」「かんがえるたつじん」の頒布の対象と入手方法
終わりのことば
注
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南北
けんとまん1007
クリママ
k sato
TAK.I
-

- 電子書籍
- うちのママが言うことには 3 クイーン…
-
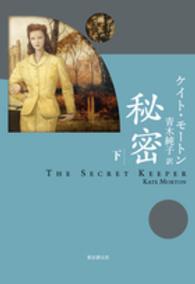
- 和書
- 秘密 〈下〉