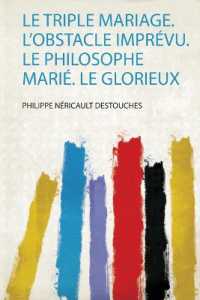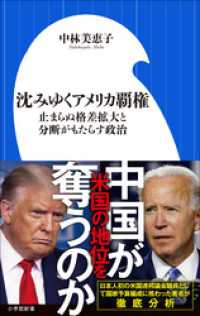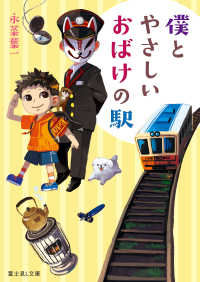- ホーム
- > 電子書籍
- > 趣味・生活(健康/ダイエット)
内容説明
認知症の人が生活する上で直面しがちな34の困り事を事例としてとりあげ、なぜそのような行動をとるのか、家族や介護職はどうかかわれば良いのかを脳の器質的特徴を踏まえて解き明かす。医学モデルでも生活モデルでもない、脳科学からのアプローチを示したはじめての書。
※本電子書籍は同名出版物(紙版)を底本として作成しました。記載内容は、印刷出版当時のものです。
※紙版とは異なる表記・表現の場合があります。また、電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
61
【脳科学的分析の結論:認知症になっても「その人らしさ」は変わらない】家族や介護者が「なぜ?」と思う認知症の人の行動を、34の事例で取り上げ、その理由を脳科学の視点から解説した書。著者紹介:<同居する母親がアルツハイマー型認知症と診断され、以来、娘として生活の中で表れる認知症の症状に向き合ってきた。一方で、母を脳科学者として客観的に分析することで、医者/患者、科学者/被験者という立場で研究するのとは違った認知症の理解を持つにいたり、情報を発信している>。NHKの「クローズアップ現代プラス」などでも話題に。⇒2023/12/15
ぐっち
18
うちの母も「家に帰りたい」というので読んでみた。なぜ家にいるのに「家に帰る」というのか、なぜ同じことを何度も聞いてくるのか、なぜ同じものをいくつも買ってしまうのか。認知症あるあると、そのようになる脳の変化を知って、うちだけじゃないんだ、そして違う人になってしまったわけじゃないんだ、と安心できる。対処法というより、認知症になった人に対して、ちょっとだけ理解が進む本。2023/10/21
かわ
3
認知症の人の行動とその行動の理由、本人の気持ちが書いてあって理屈を知りたい人には合うかも。 父が精神系に罹ってた時も、自分がメンタルギリギリの時も「家に帰りたい」と言っていたので、心から安心できる状態になりたい気持ちはよくよく分かる。 他の行動も「認知症ではない人でも、疲れているとこういう現象あるよね?」というのが書かれていてすごく納得感があった。2024/06/11
miu_miu
0
アルツハイマー型とかレビー小体型とかに分けて事例と解説による対応アドバイスが載っています。だいたいわかってきたので、さらっと読み流しました。2025/04/27
ナルコ
0
具体的な例を挙げて、認知症患者がどうしてその行動を取ってしまうのか、家族はどう対応したらいいのかを優しく砕いて説明してくれます。自尊心を保つこと、少なくなったとしてもやれること、役割を担ってもらうこと、その人の人間性が失われてしまうわけではないことなど、とても重要なことが学べた気がします。理想論的なところも少し感じられますが、家族の認知症が進行したらこうありたいなと思う内容でした。2024/03/02