内容説明
激動の戦国時代、いかなる日本語が話され、書かれ、読まれていたのか。武士の連歌、公家の日記、辞書『節用集』、キリシタン版、秀吉の書状……古代語から近代語への過渡期を多面的に描く。
-
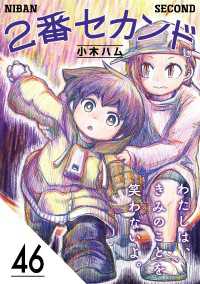
- 電子書籍
- 2番セカンド【分冊版】46
-
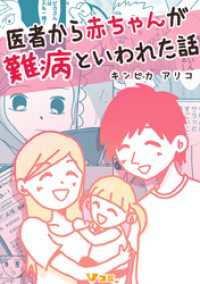
- 電子書籍
- 医者から赤ちゃんが難病といわれた話39…
-
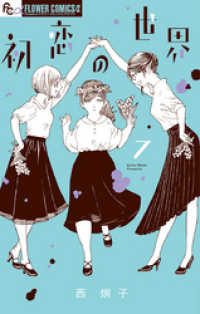
- 電子書籍
- 初恋の世界(7) フラワーコミックスα
-

- 電子書籍
- 週刊 東京ウォーカー+ 2018年No…
-
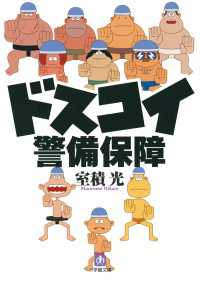
- 電子書籍
- ドスコイ警備保障 小学館文庫



