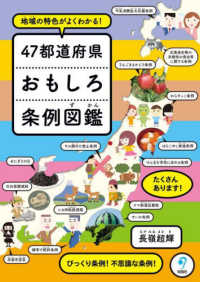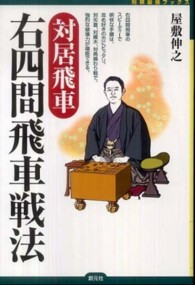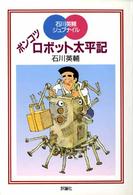内容説明
「決められた正解を素早く出す」ことが優秀な人とされた時代から「自ら正解をつくる」ことができる人の時代へ。
「自ら正解をつくり出す時代」の思考の技術。
近年の日本の地盤沈下の背景には、すでに世界が「正解がない時代」になってるにもかかわらず、いまだに日本では「決められた正解を素早く出すことが優秀な人の条件」とされていることにある。これらは変わらない偏差値信仰、近年の官僚・みずほ銀行などのエリート組織の躓きを見ても明らか。
「正解がない時代」とは「正解がいくつもある時代」のこと。そのためには自分たちで正解をつくっていく必要がある。そして自分たちで正解をつくるとは、仮説ー実行ー検証を回していくことにほかならない。
この過程で必ず付いてくるのが失敗。いままで避けがちだった失敗とどのように向き合い、どのように糧としてしゃぶりつくすのか、そこがこれからの時代の成否を分ける。
そのためのポイントを丁寧に解説、これから私たちが身につけるべき思考法を明らかにする。
第1章 正解がない時代の人材とは
第2章 すべては仮説から始まる
第3章 失敗を捉えなおす
第4章 仮説の基礎をつくる
第5章 仮説をつくる三つのポイント
第6章 仮説を実行する
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まゆまゆ
17
正解がどこかにあると考えて人々が行動したきた結果、日本社会が創造力の低迷した社会となってしまったのは、失敗を過度に恐れ行動しなかったためである。自ら考えて行動する場合は、失敗することを前提として、その失敗から何を学ぶかにかかっている。全ては仮説から始まる。その仮説をたてるためには、基礎知識に裏打ちされた直感を大切にするべき。2022/06/22
C-biscuit
8
失敗学で有名な畑村氏の新刊。先日娘の卒業式でRADWIMPSの『正解』を聞くことがあった。歌詞にもある、答えがある問ばかりではない今の世の中を改めて感じられる本である。著者もそういうVUCAの時代についてこれまでの日本の世界に追いつくための行動を変えていかなければならないとし、警鐘を鳴らしている。それでも高校くらいまでの答えのある勉強は基礎として重要であり、これを一足飛びにはできないことだとも改めて痛感。学び直しはいつでもできるが、基礎は基礎として必要なことでもある。これからの時代は多くの正解がある。2023/04/03
しゅー
7
★★正直なところ、期待とは大きく違う本だった。講談社文庫の『失敗学のすすめ』や『失敗学実践講義』を愛読していたので、手法や実践事例のアップデートを期待していたのである。ところが、大半が今の世相に関する著者の持論の展開に終止していて、技法の面は「良い仮説を作って試行錯誤していきましょう」に終わっている。事例も震災と原発事故に関する考察はあるものの、相変わらず昔の回転ドアの事故が例で使われていて、ちょっとビックリ。2022/07/17
harhy
6
いろいろ考えさせられる。1990年代以降の日本経済の衰退の一因は、過去の成功体験にとらわれ、また失敗を恐れすぎてリスクをとらなくなったこと。いい仮説に基づくいい失敗は、本来創造や明日の成功の種。ところが、家庭、社会、組織がその失敗に対してもいつの間にか不寛容になり、前例のないものに対して正解を出せなくなって委縮。今こそ失敗に学ぶ姿勢が必要なんだろうな。2023/01/07
Mik.Vicky
6
すごく頭もよく実績がある方なんだろうけど、ことこの本については、内容が薄かったように感じた。私が言うのも気が引けるが・・・しかし前向きな失敗はしていかなければならない。私は失敗を恐れずチャレンジするタイプの方だと思うので、年をとってもその気概を維持していきたい。2022/11/05
-
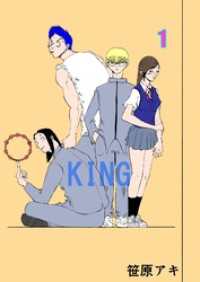
- 電子書籍
- KING 1巻