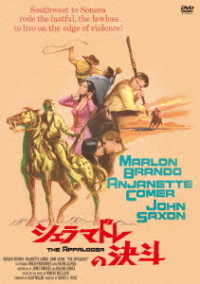- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
新大陸やアジア諸国から流入する大量の珍花奇葉、珍獣奇鳥、玄怪な工芸品……。西欧のルネサンスは、情報の大洪水に見舞われ、中世までの伝統的な知のフレームが大きく揺らいだ時代であった。さらに「古代」という過去の発見、 新たな救済の道の発見(宗教改革)、宇宙や身体内部の発見(天文学や解剖学) ……まさに発見につぐ発見の時代相だ。この未曾有の知の大爆発に、果敢に立ち向かった人々がいた。膨大な言葉と物を集め、分類を工夫し、印刷メディアと人工記憶を駆使しながら、独創的な知のソフトウェアの開発をめざす挑戦が幕を開ける! 情報革命がもたらしたルネサンス文化を読み解く。
目次
プロローグ 情報爆発の時代
光でもなく闇でもなく
一四九二年の衝撃
もっとすごい一五四三年
広がる地平
メディア革命と情報爆発の時代
情報編集という視点からみたルネサンス
第一章 ルネサンスの地図の世界
花の都がクサい?
クジラ愛ずる君主
自然の驚異に魅せられて
新大陸と戦乱のイタリア
ルネサンス文化のフィルター
メディチ家とプトレマイオス
「地図の間」の構想
コスモスの支配
他にもあった「地図の間」
製作の経緯
描かれた地図の特徴
最初に描かれた二枚
ダンティが描いた新世界
食人イメージ
新世界発見の業績を読み替える
イタリアの偉業として
イタリアの立場
伝統知と新知識の融合
第二章 百学連環の華麗なる円舞
人間、この偉大なる奇跡
カメレオンのごとくに
拡大する世界の中心で
世界を賛嘆する人
八宗兼学
知のための知
「百学連環」と喜ばしき誤読
クインティリアヌス『弁論家の教育』──古代の百学連環思想①
ウィトルーウィウス『建築十書』──古代の百学連環思想②
キケロー『弁論家について』──古代の百学連環思想③
中世における知の集約と分類
『大亀鑑』
ムーサの円舞
アンジェロ・ポリツィアーノ
円環か樹形図か
フランソワ・ラブレー
神の霊感がもたらした発明
ルネサンスと古代・中世を分けるもの
ベイコンによる転換
第三章 印刷術の発明と本の洪水
「積ん読」の誕生
キケローを叱りつける
ブック・ハンター
印刷術の発明をめぐって
印刷本の特徴
印刷術の拡散
本が増えるわけ──発行部数と市場原理
人気タイトル
拡大する蔵書の規模
印刷版書誌の誕生
万有書誌の夢
選別書誌
禁書目録
禁書目録をめぐる悲喜こもごも
阿呆船の向かう先
第四章 ネオラテン文化とコモンプレイス的知の編集
不治の病
どうしてこうなった
ちょっと待て
ネオラテンの誕生とキケロー主義
模倣と創造をめぐって
私は猿になりたい
病を治すには
ネオラテンの学習法
エラスムスの古典語学習法
ベストセラー作家のお手本
コモンプレイス(Loci communes)
中世からルネサンスへ
コモンプレイス・ノートテイキング
鋏と糊を持って読む
印刷版コモンプレイス・ブックの登場
テクストール『オッフィキーナ』
みんなのネタ本
ツヴィンガー『人生の劇場』
劇場の構成
誰も使いこなせない樹形図
コモンプレイスと知的生産
コモンプレイス化する世界
文化資本のレポジトリーとして
第五章 記憶術とイメージの力
キケローになれる装置
古代の記憶術
三つの基本原理
イメージの力
ルネサンスにおける復活
印刷術と記憶術
キケロー主義者カミッロ
カミッロの記憶劇場
窓付きの魂
ヴィジュアル・インデックス
言葉とイメージと物
記憶劇場からミュージアムへ
初の蒐集理論書
キケローの雄弁を超える
コモンプレイスとミュージアム
フランチェスコ一世のストゥディオーロ
トリノの大ギャラリー
第六章 世界の目録化──ルネサンス博物学の世界
恋するアルドロヴァンディ
破天荒な青年
ローマでの運命の出会い
ボローニャ大学博物学教授
博物学という学問
古典文献の校訂(十五世紀後半)──ルネサンス博物学の発展①
自然との照合で植物学が自立(十六世紀前半)──ルネサンス博物学の発展②
教育研究体制の確立(十六世紀後半)──ルネサンス博物学の発展③
増大する品種
植物園と乾燥植物標本
博物学と印刷術
十六世紀の動物誌を読む
エンブレム的世界観
解釈フレームとして
エンブレム的世界観と新大陸の博物誌
アメリカに行きたい!
博物図譜の誕生
図譜のメリットとデメリット
アルドロヴァンディのイメージ論
ヤコポ・リゴッツィ
アルドロヴァンディの図譜工房
世界八番目の驚異
パンデキオン・エピステモニコン
カット&ペースト
後世のために
エピローグ 「情報編集史」の視点から見えてくる新たなルネサンス像
衰退へと向かうエンブレム的世界観
アッカデーミア・デイ・リンチェイと『メキシコ宝鑑』
記憶術のその後
伝統と革新のはざまで──接ぎ木と引用
あとがき
主要人名索引
主要参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サアベドラ
MUNEKAZ
さとうしん
かんがく
武井 康則
-
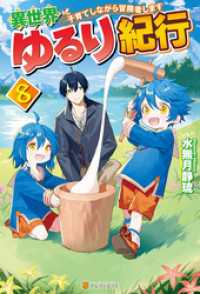
- 電子書籍
- 【SS付き】異世界ゆるり紀行 ~子育て…
-
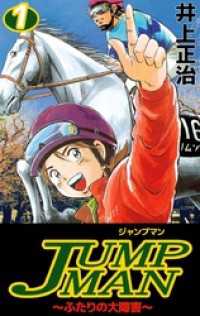
- 電子書籍
- JUMPMAN ~ふたりの大障害~(1…
-
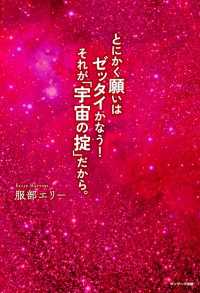
- 電子書籍
- とにかく願いはゼッタイかなう! それが…
-

- 電子書籍
- アンデッドガール・マーダーファルス(1)