内容説明
今や政府・企業・組織・個人のどのレベルでも必要とされるSDGsの要・普遍的人権の理念や制度の誕生と発展をたどり,内政干渉を嫌う国家が自らの権力を制約する人権システムの発展を許した国際政治のパラドックスを解く.冷戦体制崩壊後,今日までの国際人権の実効性を吟味し,日本の人権外交・教育の質を世界標準から問う.
目次
はじめに
第1章 普遍的人権のルーツ(18世紀から20世紀半ばまで) 普遍性原理の発展史
Q.人権理念や制度はいつ生まれたものなのか?
1 他者への共感と人権運動の広がり
2 二つの世界大戦と普遍的人権の理念
第2章 国家の計算違い(1940年代から1980年代まで) 内政干渉肯定の原理の確立
Q.なぜ国家は自らの権力を制約する人権システムの発展を許したのか?
1 国際政治のパラドックス
2 冷戦下の新しい人権運動
第3章 国際人権の実効性(1990年代以降) 理念と現実の距離
Q.国際人権システムは世界中での人権の実践の向上にどの程度貢献したのか?
1 冷戦崩壊後の期待と現実
2 21世紀の国際人権
3 人権実践の漸進的な向上
第4章 国際人権と日本の歩み 人権運動と人権外交
Q.日本は国際人権とどのように関わり合ってきたのか?
1 日本国内の人権運動の歩み
2 同化から覚醒へ
3 日本の人権外交と試される「人権力」
おわりに
あとがき
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
119
自然権や人道主義と区別して、「普遍的人権」という理念がどのように形成されたかがとてもよくわかる。何よりの驚きは内政干渉が肯定されていること。国家主権の絶対性と内政干渉の禁忌は国民国家の基本であるのに、なぜ国際人権には内政干渉が許されるのかを考えることを通じて、大切なものが見えてくる。世界は、国連人権理事会や国際刑事裁判所など国際人権システムを整備してきたが、その実効は上がらない。そして、本書が出版された一週間後に始まったロシアのウクライナ侵攻。明らかなジェノサイドに対して手も足も出ない現実が露わになる。2022/05/01
榊原 香織
72
上手にまとめてあるので流れがつかみ易い。 一般的には国際的人権の誕生は1940年代。 ラディカルな意見では1970年代。 割と新しい。 人種とか超えた人権だから。 最終章、日本についてでは、安倍元首相の価値観外交についても触れている。 2022年刊2022/07/11
風に吹かれて
24
どのような人々にも認められる普遍的な人権があるはずだ、少なくとも、おだやかに過ごしている人々の頭上に爆弾を落とすようなことは誰にも認められてはならないはずだ、と思っているのだが、世界は今もそれを行っている。どのような理念も自国の理念が正当だとして多くの国が反対しても爆撃を行う国があり、世界はそれを止められない。今日のニュースでも電力を喪失した病院で新生児が死に、危機に瀕している新生児が何人もいることを知らされた。 →2023/11/13
もえたく
23
2023新書大賞第9位。人権運動が広がったのは他者への共感であり、その端緒が書簡体小説だったというのは興味深い。手紙の交換を読むというスタイルで読者の埋没感を高め、登場人物との一体化を促進したと。その後、写真が普及し人々の痛みや苦しみに対する共感が容易になっていく。人権理念の発展の歴史から、国際人権の現在が検証されていて、歯痒さも感じながら希望も持てる論調でした。2023/05/02
とある本棚
21
なぜ国家の集合体である国際機関が、人権に関する内政干渉を認めるようになったのか、そのパラドックスの解決が本書の主題。冷静期に米ソ双方が相手の政治体制を批判するための根拠として人権概念を用い、その結果その人権概念が普遍性を帯び、批判した国自身も人権に配慮せざるを得なくなったという指摘は秀逸。本書は時系列に国際人権の発展を追っており、後半部の内容は類書の国際開発分野ではよく言及されるものであったが、前半部の人権概念の端緒である「他者への共感」がどのように生まれたかという議論は面白かった。2022/05/01
-
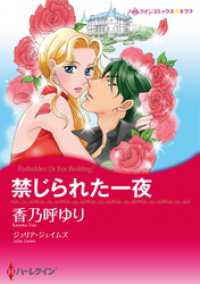
- 電子書籍
- 禁じられた一夜【分冊】 6巻 ハーレク…
-
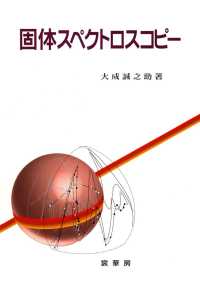
- 和書
- 固体スペクトロスコピー







