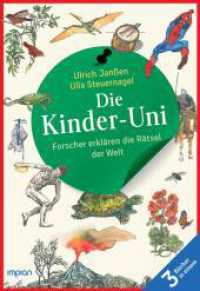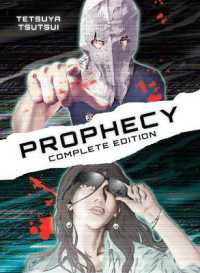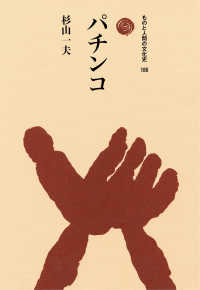内容説明
小学生の悠翔のもとに突然やってきた謎の少女,アリス.まるで赤ちゃんのように何も知らなかったが,悠翔たちから多くを学んでいく.しかしそこに,怪しい影が忍び寄り……!? AIと共存する未来とはどういうものか.「発達する知能」は,いかに実現されるのか.小説と解説の合わせ技で,いざ,めくるめく知の融合体験へ!
目次
第1話 訪れる者
第1話解説 人工知能の時代
「知能」って何だろう/人工知能技術は人間に近づいているのか?/「関数」としての人工知能/発達する心をつくる
第2話 物を調べる者
第2話解説 探索と物体概念の獲得
物体の概念とは何か?/「見て,触って,聞いて」知るロボット/「物体概念」の数理モデル/探索する幼児 vs 待っている人工知能/ロボットに好奇心をもたせる/「時々,ダメそうなことをやってみる」知的さ
第3話 言葉を覚える者
第3話解説 音素と語彙の獲得
言葉を聞きとるための知識/幼児は音素と単語を発見する/音列の統計情報をつかう/ロボットは単語を「発見」できるか?/幼児の音声認識にテキストはいらない/それは「クーラー」か,「スズシイ」か?
第4話 徘徊する者
第4話解説 移動と場所の学習
幼児はやがて歩き始める/身体そのものが「知的」である/柔らかいことの大切さ/「場所」の概念を理解する/本物の言語使用に向き合う
第5話 街に出る者
第5話解説 社会の中での言語獲得と理解
「はじめてのおつかい」からサービスロボットを考える/「統語的」関係から意味を定義する/分布意味仮説 単語の並びに潜む意味/データベース的な知識を使うロボット
第6話 苦悩する者
第6話解説 人工知能と社会構造の変容
人工知能に仕事を奪われる?/技術が発展すると「仕事」は変わる?/インターネットと人工知能の同盟関係
第7話 衝突する者
第7話解説 人工知能との関係性と倫理
人間のふりをするロボット/会話の文脈理解は難しい/関係性を育む/「ロボット工学三原則」って言われても/人工知能は規範をどう学ぶか?/ロボットと生きるための倫理
第8話 未来に向かう者
第8話解説 発達する自律的な人工知能の創成
自律的なロボットを創る/人工知能の感情と意識/アリスが「人間」になった理由/プロジェクト・アリス
引用文献
カバーイラスト:沢音千尋
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tadashi_N
Mc6ρ助
Midori Matsuoka
臓物ちゃん
shin_ash
-
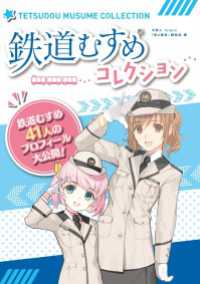
- 電子書籍
- 鉄道むすめコレクション 天夢人