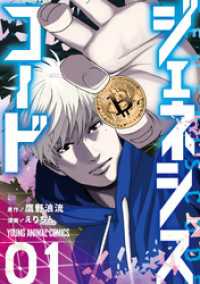内容説明
江戸の世で、アウトローはどこから生まれてどのようにして「侠客」となったのか。相撲が興行として発展し相撲とりが専業となっていった流れの影に何があったのか。江戸風俗の大家・鳶魚の語りによって、そのルーツ、歴史風俗が鮮やかに浮かび上がる。興味尽きない歴史読み物。
(※本書は2010/10/8に発売し、2022/5/17に電子化をいたしました)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
石橋
0
あとがきにもあるようにいろんなところから鳶魚の文章をもってきているのでやや繰り返しが多く、時系列がわかりにくい。でも「侠客」「角力」の成り立ちについては非常に納得。特に侠客は歌舞伎でよく聞く名がたくさん出てくるので想像が膨らんでとてもおもしろかった。2015/10/04
蕃茄(バンカ)
0
ジンギ≠仁義 ジンギ≒順儀2015/07/07
冬至楼均
0
商売として成立する前の相撲の話。そして”正しい”侠客”の話も。 2011/10/23
ポルポ・ウィズ・バナナ
0
トリビア的には侠客のお話のほうがばつぐんに面白かったな。尺八は1尺8寸、脇差がわりに所持してたとか。あと、文章のリズム感が素晴らしかったことを記しておきます。見事な講談ビート。2011/02/22
SigZ
0
★★★☆ 侠客の歴史は興味深く読めたし、とくに大鳥逸平についてはもっと調べてみたいと思った。しかし、後半の角力についてはあまり相撲に興味がないせいか、読むのがつらかった。国技館が建てられたとき、江戸っ子からの評判が悪かったエピソードは杉浦日向子も書いていたけれど、本書からの孫引きだったのだろうか。ところで柴田宵曲が「着る」という字をことごとく「著る」と書いているのは、なにか理由があるのだろうか。最後の章は公事訴訟について割かれているのだが、板倉勝重についてもっと書いて欲しかった。2010/11/29