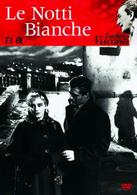内容説明
目をあけて眠るアカネズミ、公衆トイレをつくるタヌキ、孤島に1頭で生きるシカ、ハエに血を吸われるコウモリ--。
野生動物を「好きすぎる」著者の奮闘動物エッセイ!!
野生動物たちのユニークな生態、彼らと濃く触れ合う日常、共存のあり方まで語り尽くす。
※フィールドワーク中の写真などを使用しているため、一部、画質が荒い写真があります
■内容
1.アカネズミは目をあけて眠る 野生のアカネズミとの出会い/「テキパキ」という名のネズミ/アカネズミとドングリの謎
2.動物行動学者、モモンガに怒られる 産む子どもの数が問題だ/母モモンガに睨みつけられる/モモンガの森と生きる
3.スナヤツメを追って川人になる あの大切な「樋門」が!!/スナヤツメの不思議な生態/ここにいて、あっちにいないのはなぜ?
4.負傷したドバトとの出会いと別れ 翼の折れたハト/森で生きる生物、草原で生きる生物/ホバからもらった宝物
5.小さな島に一頭だけで生きるシカ 津生島へ上陸を果たす/調査でわかった島の驚くべき植生/ヒトが生きていくために必要なこと
6.脱皮しながら自分の皮を食べるヒキガエル 数千分の一を生き延びろ/ヤマカガシとヒキガエルの深い関係/動物の生態を理解する喜び
7.タヌキは公衆トイレをつくる コバキチ点を追え!/タヌキの雄は意外と子煩悩/溜め糞が教えてくれたこと
8.コウモリにはいろいろな生物が寄生している コウモリには立派な鼻がある/コウモリを襲う奇病の存在/生きる上でのリスクとどうつきあう?
9.ザリガニに食われるアカハライモリ アカハライモリの可愛すぎる幼体/動物行動学者、深夜の草むらで格闘する/動物との接し方についての新しい規範
■著者について
小林 朋道(こばやし・ともみち)
1958年、岡山県生まれ。公立鳥取環境大学副学長。
岡山大学理学部生物学科卒業後、京都大学で理学博士取得。
岡山県で高等学校に勤務後、2001年に鳥取環境大学環境情報学部環境政策学科(現:公立鳥取環境大学環境学部)助教授、2005年に教授に就任。
環境学部長を経て2022年より現職。専門は、動物行動学、進化心理学。
著書に『先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます! 〔鳥取環境大学〕の森の人間動物行動学』をはじめとする先生シリーズ(築地書館)、『ヒト、動物に会う コバヤシ教授の動物行動学』(新潮社)など多数。
研究、およびプライベートでさまざまな動物と交流を深め、数々の知られざる生態を発見してきた。
ヒトと自然の精神的なつながりや、動物行動学を活かした野生生物の生息地の保全にも取り組んでいる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アーちゃん
canacona
トムトム
K.H.
七月せら




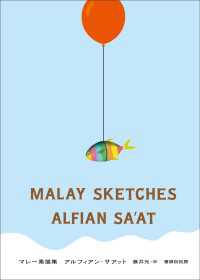
![漫画ゴラクスペシャル 15号 [2021年10月15日配信] 漫画ゴラクスペシャル](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1070325.jpg)