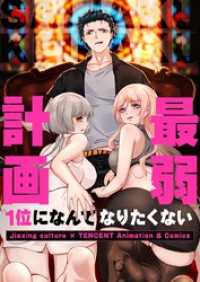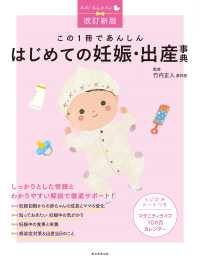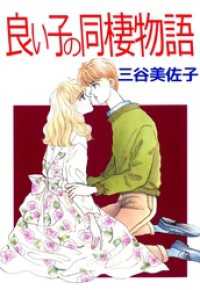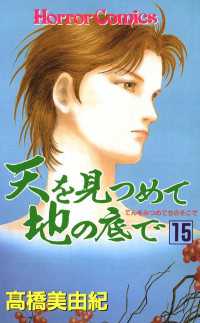内容説明
丸木舟で島嶼(とうしょ)間、時には外洋まで乗り出していった縄文人。縄文文化の範囲は現在の日本の国境にほぼ重なる。縄文文化と新石器時代のロシア極東、朝鮮半島、中国大陸とを比較して、なぜ縄文文化が日本固有といえるのかに迫る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
62
目視できる限りの島に丸木舟で行ってた感じですね。 黒曜石とか特殊な貝とか求めて。 あるいは冒険心か 沖縄出土の蝶の形をしたアクセサリー 今でも使えそう。さて、南島(沖縄)は縄文文化が伝わったのかそれとも独自の物なのか2023/05/13
tamami
41
今回は、縄文という言葉に少し惹かれすぎたようだ。内容的には、正統な考古学の手法!で縄文文化と列島周辺の地域との交流?行き来?の有無について、説得力ある説明に納得するも、玦状(けつじょう)耳飾や石刃鏃、曽畑式土器など、石器や土器の非常に詳細な分析(これが無いと結論は出ないのだけれど)が続いて、少々退いてしまう。大陸との交流において、言葉が俎上に挙がっているのは新鮮に響いた。縄文時代以前には、環日本海を覆う原東アジア語?が存在したが、その後大陸では民族が入れ替わり、彼我の言葉が通じなくなったと考えると面白い。2022/04/15
鯖
22
結論としては縄文時代の考古学資料を検証すると、間違いなく往き来はあったが、私たちが思っているほど朝鮮半島や極東との交流はなく、縄文文化は独自のものという感じ。その理由として九州の縄文人と朝鮮半島の新石器人とは言葉が通じず、意思疎通できなかったとあげる。特に古代の本って妄想いっぱい夢いっぱいで突き進みがちな感があると思うんだけど、そっちにいかなかったことに妙に感心した。南島のオオゴマダラを模したと思われる蝶型骨製品のアクセサリーきれいだなあ…。2022/06/04
月をみるもの
15
島影が見える数十kmの距離であれば、縄文人が海を超えたことはわかってる。問題は、同じように海に隔てられていても文化圏が同じになるところと異なるところ存在するのはなぜか、だ。言語はこの違いの原因なのか、それとも結果なのか? 一方で言語が明らかに違っていると考えられる領域(大陸と日本列島)でも、特定の装身具(玦状耳飾とか)が広く分布しているのはなぜなのか? 謎は深まるばかりだが、鬲(れき:三足土器)とか青銅刀子とかのさらなる発見と新たな研究手法(石器の成分分析など)が新たな知見を生み出していくにちがいない。2022/05/19
はちめ
10
縄文時代における朝鮮半島や極東地域との交流は海を越える必要があるが、それでもなんとなくそれなりの交流が行われていたという認識がある。しかし、当時の遺物の詳細な検討からすると単発的な行き来があった程度であり、特に北方地域においては、日本列島側から極東に人が渡った形跡は見られない。当時の状況は、本書の表現によれば、海の向こうには言葉の通じない人々が存在するという認識だったということになる。このことは、日本語や日本人の成立という観点からも興味深い。☆☆☆☆★2022/05/28