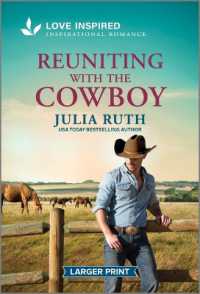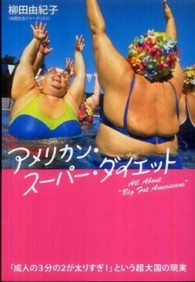内容説明
明治維新は「武士」から刀を奪った―。刀を腰に差す「帯刀(たいとう)」=武士の特権という今日の〝常識〟は、はたして正しいのか。江戸~明治初年まで、誰が、何のために帯刀し、人々のまなざしはいかに変わっていったのか。虚栄と欲望がからみ合い、武器からファッション・身分標識・旧弊のシンボルへと移り変わる姿を追い、「帯刀」の本当の意味に迫る。
目次
帯刀とはなにか―プロローグ/帯刀の誕生と変質―武器・ファッション・身分標識(刀・脇差を帯びること/帯刀規制のはじまり/百姓・町人の脇差)/身分標識としての帯刀―「帯刀人」の登場(非常帯刀の登場―京都の帯刀改/天和三年令の弛緩/帯刀の特権化と整備/帯刀へのまなざし)/虚栄と由緒と混乱と―ひろがる「帯刀」のゆくえ(帯刀に魅せられて/「士」に紛れゆく者たち/帯刀と身分秩序/白刃に血が滴るとき―終わりの序曲)/明治初年の帯刀再編―消えゆく身分標識(平民帯刀の整理/三治一致と藩の帯刀許可/暮往く帯刀人の時代)/身分標識から旧弊・凶器へ―貶められた最期(脱刀がもたらしたもの/帯刀意義の変質/廃刀の時代/変わる常識、消えゆく習慣)/刀を差せない日―エピローグ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
akiakki
11
江戸時代の風景画にはどう見ても町民が刀を差した絵が多数ある。帯刀とは?から始まる江戸時代から明治時代までの帯刀文化と行政。刀を帯びる意味は武器→ファッション→身分標識と変化していきますが、脇差は全くアンタッチャブルだったのは驚きでした。ちなみに士分の身分標識である帯刀が、更に非常帯刀と常帯刀に分けられる下りは同著者の『壱人両名』を読んでいるとニヤリとできます。2025/12/05
bapaksejahtera
11
江戸初期まで刀剣は治安の為に誰もが頼った。又裃に脇差や刀を帯びる事は背広にネクタイの様な決まり事、身分を問わず年始祭礼葬儀に不可欠な習慣は幕末まで続く。他方身に大小を帯びる帯刀習慣は日常の労働に邪魔であり自然に武士に限られる。偃武と共に刀剣は武器としての実用を離れ自己顕示の具となり、傾奇者が極端に走り17世紀後半に終に取締まりに至る。都市では士分以外常時着用は禁ぜられる。帯刀風俗に武器ではなく身分標識に不可欠な物に変容。この認識は明治初年まで続くが開化の洋装に帯刀は不可能であり時代の趨勢は帯刀禁止を導く。2021/11/26
in medio tutissimus ibis.
5
戦国時代には実用的な武器であった刀が、世の中が平和になるにつれファッションと化し、それが取り締まられるに至って身分表象となった。そのために平民が刀を帯びることが禁じられる一方で、武士においてはそれは義務となったが、脇差は禁止の対象ではなく、また士分以下においても職能や幕府またはそれ以外の権力への奉仕によって帯刀御免となった。江戸末期、悪化した治安は刀に武器としての属性を取り戻させ、明治政府は身分表象としての帯刀を引き締めたが、遂には洋服との兼ね合い等の理由から規制されるに至った。刀に見るサンスクリット化。2019/05/28
テキィ
4
興味深い話だった 刀はファッション性があったんだよなー2019/03/18
hiro6636
2
武器からファッション、そして権威から旧弊へ2019/04/26