内容説明
男女の地位に違いがなかった双系的社会から父系的社会へ移行する中で、古代の女性首長たちは、どのような活躍をしていたのか。関東から九州に至る数多くの古墳群の発掘成果(埋葬施設・副葬品・人骨の性別)から埋葬のルール(埋葬原理)を抽出。古墳時代の親族や首長を問い、王位継承のあり方を分析する。「王朝交替論」についても一石を投じる。
目次
女性首長の墓が語るもの―プロローグ/埋葬原理研究のこれまで(古墳の被葬者は何人か/用語と定義/田中良之の基本モデルと課題)/一般層の埋葬原理(人骨の分析による埋葬原理/考古資料の分析による埋葬原理/夫婦原理の埋葬)/首長墳の埋葬原理(首長墳におけるキョウダイ原理/古墳群にみる父系化の過程/父系化の諸段階とその背景/キョウダイ原理の埋葬と首長位継承)/大王墓の埋葬原理(大王墓の複数埋葬/大王陵における埋葬原理/大王墓における夫婦原理の埋葬)/埋葬原理研究から見た「王朝交替論」(「王朝交替論」をめぐる研究略史/初期ヤマト政権は連合政権か?/過渡期の大型古墳/王墓群移動が意味するもの/王族はさらに分派する)/埋葬原理の意味するもの―エピローグ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南北
47
古墳時代の首長たちがどのように埋葬されていたか、特に被葬者の性別に着目して「埋葬原理」を明らかにしようとした本。複数の埋葬者は夫婦ではなく、キョウダイ(兄弟・姉妹・兄妹・姉弟など)が多く、また母系制の首長も数多くいたが、次第に父系制へと移行していったと指摘している。また、後半はこれをもとに「王朝交代論」を展開しているが、王族の分派活動だとの仮説は興味深かった。ただ、継体大王や斉明天皇など、大王と天皇の表記が何の説明もなく混在しているのが気になった。2021/03/26
月をみるもの
14
初期の古墳には、かなりの割合の女性首長が葬られていた。その後、なぜそしてどのように父系化が進行したのかを、考古学的な物証と文献を組み合わせることで明らかにしていく。さらにこうした埋葬原理が、奈良南部→北部→河内の王墓域移動〜王朝交代論への考察につながっていく部分の論考は、知的興奮を喚び起さずにはおかない。2018/12/09
鯖
14
幾多の古墳に埋葬された骨の歯冠や頭蓋の小変異を調べ、その親族関係を明らかにした本。キョウダイ原理という言葉で表されるように、姉弟や兄弟等の血族関係がある人々を合祀していたというのが意外だった。時代が下って、藤原氏も倫子は実家の源氏の仁和寺の墓に、帝の后である妍子や嬉子も墓は実家の宇治にある藤原氏代々の木幡墓にあるとのこと。…藤原氏に関してはなんか逆に、さすがに鳥辺野とかに風葬じゃなかったんだなあと思っちゃったけど。説話集で、大貴族の幼いこどもの屍体を風葬する話なかったっけ??2018/08/01
さとうしん
11
従来古墳の被葬者は一人だとされてきたが、調査・研究の進展にともない、二人以上を埋葬する複数埋葬の方が一般的であることがわかってきたという。その古墳の埋葬原理に注目する。複数埋葬ではきょうだい・親子など血縁者をともに葬ることが多く、配偶者は基本的に出身氏族のもとで葬られたことや、王墓の築造地域の移動は「王朝交替」を示すものではなく、王族内の分派活動による政治変動を示しているのではないかという議論が面白い。2018/05/26
ウォーカージョン
6
古墳は複数埋葬が基本。母系も父系もあり。キョウダイ原理による埋葬。地位の継承は、兄弟、従兄弟など。分派するこてとによって王権の中心地が移動、これは王朝交代とは異なる。など、いろいろ勉強になったし、納得もした。自分のイメージしていたことが、概ね間違っていなかったなと思った。2019/02/07
-
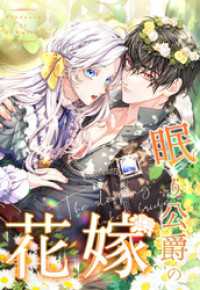
- 電子書籍
- 眠り公爵の花嫁 第22話【タテヨミ】 …
-
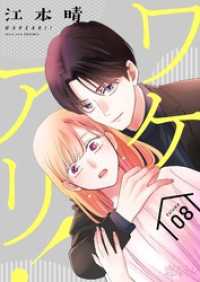
- 電子書籍
- ワケアリ! 8
-
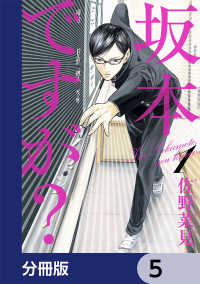
- 電子書籍
- 坂本ですが?【分冊版】 5 HARTA…
-

- 電子書籍
- KAMINOGE12
-
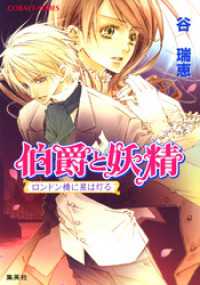
- 電子書籍
- 伯爵と妖精 ロンドン橋に星は灯る 集英…




