内容説明
古墳時代から飛鳥時代にかけて地方行政のトップにあったのが、有力豪族が任命された国造である。だが、その実態は謎も多い。本書は、稲荷山鉄剣銘に刻まれた「ヲワケ」の名や、筑紫の磐井など国造と関連する豪族、記紀の記述を紹介しながら、国造制とは、いつ施行されたどのような制度で、誰が任命され、いつ廃止されたのかまでを描き出す。さらに奈良時代以降に残った国造がどのような存在であったのかなどを解説する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
116
日本史の教科書で「大和朝廷期の地方行政官」と習ってから完全に忘れていた国造について、その成立から消滅までを初めて系統的にまとめている。といっても記紀や鉄剣銘の僅かな記述しか史料がないので、そこから推測される状況や学説の紹介が中心。中央政府として振る舞い始めた当時の朝廷が、無の状態から国家を創り上げようと苦闘していた姿が見えてくる。「推定する」「考えられる」が多く隔靴掻痒が拭えないが、法律や行政組織という概念もなかった時代に人をまとめる苦労は相当なものがあったはずだ。日本の官僚制も赤ん坊の頃があったわけか。2022/03/01
南北
68
大和政権の地方官であり、有力豪族が任命されたとされる「国造」だが、国だけでなく郡(当時は評)を単位としていたり、一族で継承するものもあれば、遥任と考えられるものもあったという。中には出雲の国造や紀伊の国造のように神社の神官として今日まで続いているケースもある。一言で言えばよくわからないとしか言いようがないが、日本書紀では絶賛している大化改新以後の時代も「国」の直下の行政区域が「評」だったと考えられるので、なぜ「郡」に書き換えたのかという根本的な疑問が残ってしまう。2024/07/12
saga
60
『ヤマト王権』から引き続き本書を読む。歴史の時間に習った(覚えさせられた?)「くにのみやっこ」ではあるが、文字史料が少なく、わずかに残る点と点の史料から、線や面を推定していかざるを得ないということがよく判った。ここに歴史研究の面白さがあるのかも知れない。大和政権が日本国内を支配するに当たって、中央からの官人派遣と地方有力者との融和政策、やがて中央集権が完成していく段階の国造という役職であったと理解した。2023/04/19
kk
27
律令制以前の地方統治の柱の一つである国造制度について、その成り立ち、機能、廃止の過程などについて、史料を基に丁寧に解説しようとするもの。基本的には親切に説明してくれているってことなんでしょうけど、全体としてマジメというかカタギというか、「あとがき」に至るまでわりとガチです。古代史ファンの暇つぶし用ってわけにはいかないようです。2022/04/11
mahiro
22
古墳時代のヤマト政権の確立と共に地方豪族の地域支配の為に置かれた国造の成立と広がり、やがて中央集権的律令制度が施行されるとともに迎える終焉までを考証している。記紀の記述やワカタケル大王や磐井の乱、国造とは何か辺りまではサクサク楽しく読めたがその後は結構読むのに苦労した。ある程度以上古代の知識がある人向けかな2022/01/25
-

- 電子書籍
- 鬼嫁と結婚してしまった結果【同人版】 …
-
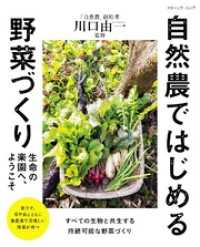
- 電子書籍
- 自然農ではじめる野菜づくり
-
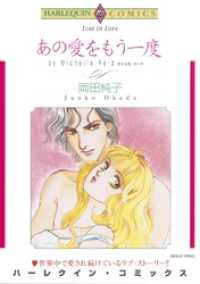
- 電子書籍
- あの愛をもう一度【分冊】 8巻 ハーレ…
-

- 電子書籍
- 新装版 魔法先生ネギま!(17)
-
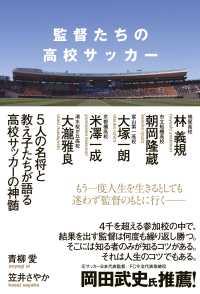
- 電子書籍
- 監督たちの高校サッカー




