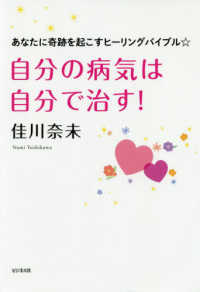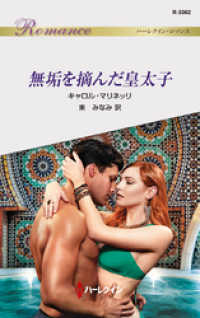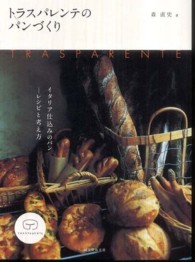内容説明
何が政府と市民の相互信頼を生むのか? 閉塞感の漂う日本へのヒントが満載!
台湾の天才デジタル大臣オードリー・タン氏は、デジタルを駆使して市民参加型の新しい民主主義の実践に挑んでいる。誰でも簡単に政治参加できるプラットフォームの創設や、1人1票ではない投票方法の導入など、画期的な事例を多数紹介。世界が注目する台湾モデルの精髄を説き、政治への諦め感が漂う日本人に変革の手がかりを示す。
〈目次〉
序 章 デジタルで民主主義を改良する
第1章 開かれた行政府をつくる
第2章 私はなぜ民主主義に関わるようになったのか
第3章 市民参加型の討論を実現
第4章 投票方法のアップデート
第5章 さまざまな問題をどう乗り越えるか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
58
タンさんの言葉は、何度触れても、ぶれることのない、それでいて新しい発見がある。透明性、アカウンタビリティー、公正さ、楽しさなど、改めてその言葉の意味することや背景を考える。そして、グッド・イナッフという姿勢。それは、まさに対話の先にあるものだと思う。小さなことから、スピーディに始め、どんどんアップデートしていく。その地道な積み重ねが、人を呼び込むのだと思う。あらゆる所・場で適用できる思考だ。2022/09/03
ピンガペンギン
27
閉塞感を感じる日本からタンさんのことばを聞くと、こういう人が活躍する台湾がうらやましく思える。SNSは冷静な議論の場所になりにくい。そのため独自プラットフォームJoinで市民が意見を自由に表明できる(5000人以上賛同者があれば政府が議題にして検討)ように。市民が投票して優勝したら政策として取り入れられるイベントが毎年ある。そこではクアドラティックボーディングという1人1票ではない方式で投票する。タンさんの生育環境、ドイツでの1年間が大きい転機だったことも興味深かった。2026/01/15
zoe
19
タン氏の研究をタン氏の語り口で書いた本。集団的知性を高め、市民が民主主義を自然と成し遂げる仕組みとは。オープンにするということ。多くの目に晒されチェックが入れば大抵の問題は明らかになり解決される(リーナスの法則)。リバースメンター、年長者と若者。g0v(ハンズオン、オープンソース、公共性)。ダブルダイヤモンドプロセス(発見、定義、展開、提供)。クアドラティックボーディング。1票投じる毎に票数の2乗分のポイントを消費する。最初の持ちポイントは99ポイント。選択肢が多い場合、投票者の2番手以降の意思がわかる。2022/03/05
武井 康則
13
コロナ下の台湾でマスクの配布等、インターネットを使って手際よく混乱を回避させたオードリー・タンのデジタルコンテンツについてのインタビューをまとめたもの。一度に多くの人が参加できるデジタルコンテンツなら政治参加の道具として良いのではないかという考えから政府が導入した背景と環境がある。地域が狭く、同質の人が多数であり、たぶん格差が小さく、教育水準が高い。そして、民主主義の歴史が浅い。1996年に総統選挙が行われ民主化が始まった。だから政治に対する関心が高い。そこで政府をオープンなものにしようという考えのもと、2023/11/08
うえぽん
13
タン氏の言うデジタル民主主義は、紙の投票を電子化するという意味ではなく、通常の数年に1回の選挙の弱点(低頻度、死票の多さ)を補うために、イシューの表明(5000人以上の賛同者による電子請願)や、99ポイントから第2選択肢以降にも票を割り振らせ、複数プロジェクトの優先順位を付けるのに適したデジタル投票(Quadratic Voting)等によって参加の頻度と質を上げようというもの。多くのSNSの弱点(返信機能、匿名性)の指摘や、将来世代の意向を加えることで現世代間の合意形成に役立つとしている点も首肯できる。2023/07/21