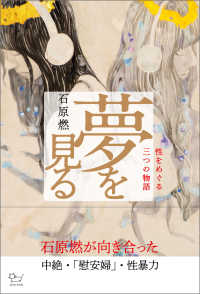内容説明
徳川家康が入城し、将軍の本拠地として大都市へ変貌した江戸。その始まりは平安時代末、秩父平氏一族の江戸氏が拠点を置く低湿地だった。太田道灌の江戸城築城、戦国大名北条氏の支配を経て、入府した家康の大工事によって、城と町は発展を遂げる。江戸の繁栄はいかにして築かれたのか。本書では新知見をふまえ、中世から近世への変遷過程を解明。平安時代の寒村から、豪華絢爛な都市が成立するまでの500年を描き出す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
旅するランナー
214
江戸東京博物館学芸員による、徳川家康が見た江戸の考察。著者齋藤氏は江戸の変遷を中世から連続して考えるという視点を貫かれています。平安時代の江戸氏一族から、太田道灌、小田原北条の領国を経て、徳川家につながります。何にもない湿地をゼロから家康が立ち上げたと思ってましたけど、どうやら家康さんを神格化するために後付けされたイメージみたいです。日比谷入江みたいに、ここまで海がきていたのかとか、古地図と現代東京を見比べるのも面白いです。2022/03/27
パトラッシュ
113
太田道灌による築城後も辺境の寒村だったというのが江戸初期のイメージだが、戦国期を通じて古河公方の御座所が計画されたり陸水交通の結節点として一定の発展を遂げていた姿が見えてくる。本格開発は徳川氏の入府以降だが、ほとんど江戸に滞在しなかった家康は城の拡張に手をつけただけで、次の秀忠時代に将軍家の本拠地として大規模な城郭普請や町場形成が行われたとする。こうした中世からの連続発展説に立つ著者に対し、徳川を挟んでの断絶説を主張するなど学説が割れているらしい。本書では連続説に納得できるが、断絶説の主張も聞いてみたい。2022/03/13
六点
96
平安時代末期の秩父平氏流江戸氏の勢力扶植から始まり、江戸の立地の良さに着目された太田道灌の時代。小田原北条氏の時代となると、「関東への入り口」ともいうべき要地になる。そして水陸交通の拠点となり、徳川家康の江戸入府を迎え、30年に亘り、断続的に江戸城は改装を受け続け、遂には天下人の居城、政権の聖地とまで上り詰める。六点は東京に詳しくないので、イマイチ土地勘が無く、「そういうもんなんだあ」としか感想が持てなかったが、都市のポテンテンシャルというものは、多かれ少なかれ、都市が大発展する前には見出されているのだ。2022/06/06
HANA
72
江戸というと徳川将軍のお膝元、八百八町が繁栄を謳歌していたというイメージだけど、本書は平安末期の江戸氏から家康の入府、幕府成立辺りまで、徳川以前からの江戸の流れを追った一冊。とはいえ中心となっているのは戦国時代、太田道灌の築城から北条氏の支配を経て江戸幕府成立辺りまで。それも通史的な流れではなく、ミクロな話題が多いため東京の地理に暗い自分はわかりにくい箇所が多い。かつての大橋が今どこかとか本気でわからないし。ただ興味ある話題、古河公方が江戸を根拠にしようとしていたとか馬出しの流行とかは面白く読めたが。2022/01/19
kk
24
さまざまな変貌を遂げつつも、中世から近世にかけての江戸の街には基本的な連続性が認められるという主張。史料だけでなく考古学的な知見も加味しながら、中世江戸の状況の緻密な復原にチャレンジ。地名の比定や往来方向についての勘考など、堅気で真摯な取り組みに感服。他方、土地や門や橋や堀や曲輪の名称など、細かい固有名詞がてんこ盛り。都内中心部の土地勘のある人でないとちょっとストレスを感じるかも。もう少し地図とかを工夫すれば、かなり取っ付きやすくなるんじゃないでしょーか。2022/03/05