内容説明
現代を生きる私たちにとって、本格ミステリはなぜこんなにも面白いのか。テクノロジーが劇的に進化し、モラルの壁が高く厚くなっていく時代背景に刺激されつつ、紡がれてきた新たな作品群を読み解く、切れ味鋭い作家論集。読めば、本格ミステリがますます好きになる。第9回本格ミステリ大賞と第62回日本推理作家協会賞をW受賞した名著!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
16
今まで読んできた本が多く、取り上げられていて嬉しかったです。一般の本ではマニアックに見られ、本格ミステリーでは異端されて蔑ろにされているような20世紀末~21世紀初頭に登場してきたミステリーが本格を換骨奪胎、またはコピーしているだけではなくキャラクター性、ロンハーや検索エンジン導入、多重人格探偵サイコ、アイデンティティの曖昧さ、オウム真理教、個室など時代の変化も反映しているという視点が面白かったです。大きな括りではなく、バラバラだった個々に注目し、関連付けることを媒介し、現在を模索する新本格ミステリー評論2012/05/17
しろ
9
☆7 やっぱ評論って面白い。現役の有名ミステリ作家(綾辻、有栖川や米澤、道尾など)について語られた20編。各作品の繋がりを捉える緻密な論理性と、ドストエフスキーやロンドンハーツなどと絡める意外性とが上手く両立している評論は面白い。比較的自由に語ってたと思うけど、最後にはしっかりまとめてきた。よく聞くことだが、大きな物語は死んだのだ。そして物語だけでなく、人間の精神、社会、それらの中に違うモノが、価値観が並列に混在しているのが「今」なのだ。だから読み手の解像度によって作品の価値が変わってくる。ってことかな?2012/02/27
いちはじめ
5
個別の作家論から浮かび上がる新本格以降のミステリの動向。僕は、ここに採り上げられた作家すべての良い読者ではないが、それでもなかなかの説得力を感じた。特にひいきの作家(有栖川有栖、北村薫など)について論じた部分は、自分でも漠然と気付いていながらうまく表現できないもやもやが晴れるような議論で、とてもすっきりした。良書。2009/07/11
鳩羽
4
新本格以降の作家論から、その作品がどう時代に読まれてきたのか、その作品からどう時代を読むことができるのかを露わにしようとする評論集。作品は時代を映す鏡でもあるけれど、ズーム自在のカメラでもあることを教えてくれる。2013/07/23
たなと
2
評論を読むたびに、評論家っていろんな知識が必要なんだなぁと感心する。思いもよらないところを結びつけて考えたりとか。それは置いといて、「東京創元社の<ミステリ・フロンティア>が、紙の本に対するこだわりやノスタルジーを漂わせているのも、紙の本を必要とせずに成り立ちそうなラノベ的なものを、視野に入れているためと思われる。」になるほどと思った。ミステリ・フロンティアを何冊か読んだけど気づかなかったな。綾辻行人の十角館の評論も面白かった。エラリィのあのセリフがミスディレクションになってるとか気づかない。2012/08/10
-
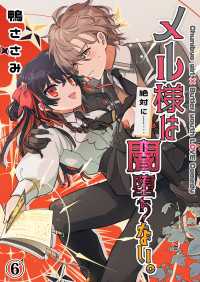
- 電子書籍
- メル様は絶対に闇堕ちない。第6話
-

- 電子書籍
- Z世代に嫌われる上司 嫌われない上司
-
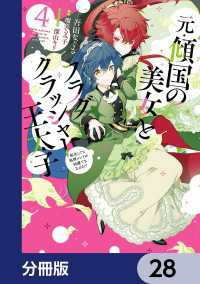
- 電子書籍
- 元・傾国の美女とフラグクラッシャー王太…
-

- 電子書籍
- 嘆きの亡霊は引退したい ~最弱ハンター…
-

- 電子書籍
- アート・ルーマー(4)




