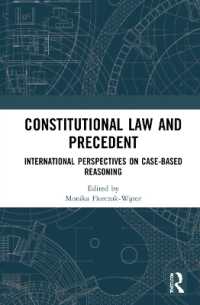内容説明
哲学者のウィトゲンシュタインは「すべての哲学は『言語批判』である」 と語った。本書では、日常で使われる言葉の面白さそして危うさを、多様な観点から辿っていく。サントリー学芸賞受賞の気鋭の哲学者が説く、言葉を誠実につむぐことの意味とは。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
130
本書のタイトルがドンピシャリ。著者の問いかけにハッとする:なぜ「白い」「赤い」と言うのに「緑い」とは言わないか。責任を回避して問題を誤魔化す「○○感」という言葉の氾濫。「濃厚接触」(淫靡な意味?)「都市封鎖」などの奇妙な日本語を使うコロナ対応の怪。ジェンダーバイアス批判から母語、母国、母屋もダメか。まん延、ねつ造、駐とん地などの間の抜けた交ぜ書き。謝罪でないお約束の言葉の数々。…「すべて哲学は言語批判である」というウィトゲンシュタインの言葉を踏まえ、身近な話題を提供する哲学者の読みやすいエッセイである。2022/04/28
はっせー
103
言葉。私達に取って大事な存在。しかし大事な存在だからこそないがしろにされやすい存在でもある。まるで空気のように。その言葉について考えたのがこの本である。コロナ禍で出てきたような言葉や流行の言葉をしっかりと考えてある。例えば抜け感やガチャ。このへんの言葉をなぜ出てきたのかを考察する。また印象に残っているのはニュースピークである。これはジョージ・オーウェルさんが書かれた『1984年』に出てくるものである。要は言葉を減らせば思考力を減らす!いまの世の中よくわからない言葉で溢れていることに警鐘を鳴らす本である!2022/06/18
エピファネイア
102
我々が何気なく口にし、耳にする言葉。数々の言葉、言い回しについて気づきを与えてくれる。第1章が特に興味深い。「みっつ、みっか」、「よっつ、よっか」、「いつつ、いつか」と規則的にみえる呼び方が、「むっつ、むいか」、「ななつ、なのか」のように規則から逸脱する場合がある。「赤い」、「白い」、「青い」、「黒い」は形容詞として定着しているのに「緑い」、「紫い」とは言わない。日本語を母語としない方には非常にわかりづらい日本語。言葉の歴史をたどればこれらの答えが見えてくる。感想、レビューを正しい日本語で書きたいと思う。2023/01/30
アキ
102
2020年9月から朝日新聞に連載していたコラムに加筆したもの。著者の6歳の娘との会話から、普段何気なく使っている日本語という言語を捉え直す。言葉は文化を表し、生活の中で用いられる「生ける文化遺産」であると言う。例えば「やさしい日本語」の普及による言語の簡略化の危険性や、コロナ禍で新たに生み出された多くのカタカナ語の利点と副作用、政治家の「発言を撤回する」という不可解さなど、「鏡の国のアリス」のハンプティ・ダンプティにならないためにも、言葉を雑に扱わず、自分の言葉に責任を持つことの重要性を強調している。2022/01/01
けんとまん1007
83
噛みしめながら頁をめくった。噛めば噛むほど味わい深くなる。一つ一つの言葉を、いかに大切にするかを、平易でありながら深みのある言葉で綴られている。巷に溢れかえる、雑な言葉や、その使い方。相手を無視し、自分勝手に話すだけで、その結果にも関心がない風潮。量ばかり追い求め、質はますます薄くなることへのアンチテーゼ。何度も推敲する癖が、ようやくついてきたので、納得の1冊。2023/01/11