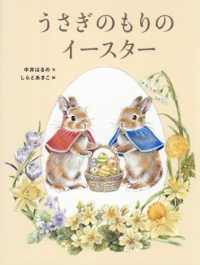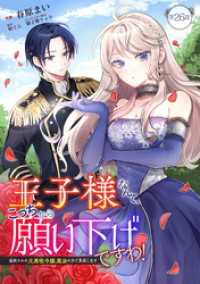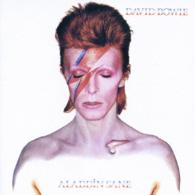- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
なんのために生きるのか? と考える自分とはなんだろう? 哲学の問いは,いつも私たちの日常の中から生まれてきました.「自己」「生と死」「真理」「実在」「言葉」……古代から現代まで,人間が考え挑み続けてきた根源的な問いの数々を,やさしい言葉で一から解きほぐします.予備知識は不要です.ようこそ,哲学へ.
目次
はじめに┴第1章 生きる意味┴1 何のために生きるのか┴2 幸福とは何か┴第2章 「よく生きる」とは┴1 ソクラテスの問い┴2 よいことと悪いこと┴3 なぜ他者を思いやる必要があるのか┴第3章 自己とは何か┴1 自己という不思議┴2 心とは何か┴第4章 生と死┴1 生命とその限界┴2 人間にとっての死┴3 生きる意味を見失ったとき┴第5章 真理を探究する┴1 真理とは┴2 論理的に考える┴第6章 ほんとうにあるもの┴1 ものの仮の姿と背後にある実在┴2 自然科学が想定するほんとうにあるもの┴3 経験のリアリティ┴4 「意味」の世界┴第7章 言葉とは何か┴1 言葉の謎┴2 音と意味が一体になったことば┴3 システムとしての言葉┴4 言葉の限界と可能性┴読書案内┴あとがき