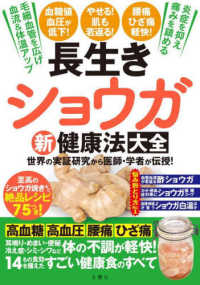- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
神社には、なぜ鳥居があるのか。神社の本殿は、なぜあのような形をしているのか。神社のルーツは何か。どのようにして今の形になったのか──伊勢神宮、出雲大社、あるいは沖ノ島、熊野三山、三輪山の磐座祭祀といった代表的な神社とその信仰のかたちを分析するとともに、日本各地に今も残る古い信仰のかたちの中に神社のルーツを探る。神社についてのすべてがわかる決定版。
目次
はじめに
第一章 神社と宮と社
第二章 沖ノ島と三輪山の磐座祭祀
第三章 伊勢神宮と出雲大社
第四章 磐座祭祀の伝承
第五章 禁足地祭祀の伝承
第六章 神社と本殿建築の変遷
第七章 山の世界と熊野三山
第八章 厳島神社とその歴史
第九章 原初を伝える社の神
第一〇章 神社と鳥居
おわりに 神社とは何か
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Defricheur
16
狭い意味での「神道」を論じているのではなく、神社という建築物から、日本人の精神・社会の構造や歴史を読み解いていく。ひとくちに「神社」といっても多種多様な存在形態がある一方で、様々な角度から分析を加えていくと、古来から日本人が通有する精神構造を反映したものであることが明らかになっていく。2022/03/06
もるーのれ
8
神社の起源や性格について、文献史学・考古学・民俗伝承学などの見地から紐解く一冊。やや強引な所はあるものの、精緻な分析に基づいた論旨は明確で分かり易い。古代祭祀の系譜を引く神社のあり方として磐座祭祀と禁足地祭祀を挙げている。社殿のあり方として起源となる建物形態(豪族居館・祭祀建物)や祭祀時の神職の出入りの有無などの分類軸を設定する。そして鳥居は精霊を迎え入れるための構造物であるとする。神社再開の構造に関する指摘が鋭く、示唆に富む内容であった。神社を観る・調べる上での着眼点として大いに参考になった。2025/08/16
かわかみ
8
「伊勢神宮と出雲大社」に続いて読んだが、なるほどね、と思ったのは神社の始原として磐座祭祀と禁足地祭祀があって、前者の方が古いという指摘と、ニソの杜が新嘗祭(贄の忌み)の始原だという指摘くらいか。この著者はクセが強い。箸墓を当然のように卑弥呼の墓だと述べたり、神仏習合は叡山発祥の本地垂迹思想から始まったと述べたり、北条泰時は同族の平清盛を顕彰するために厳島神社の再建を図ったと述べたり…。証明できない命題に大胆な仮説を構想するのが民俗学の面白い点だが、風呂敷は風呂敷と明示しないと学問の信用が落ちよう。2025/04/22
イツシノコヲリ
6
民俗伝承学を専門とする著者が神社の成り立ちや変遷について明らかにしている。筆者が他の書籍で扱っている沖ノ島・伊勢神宮・出雲大社・ニソ社などの他に、熊野三山と厳島神社が新たに加わっている。最終章には鳥居の起源について書かれていて、鳥が物をついばむことを期待している習俗だという。全体的に読みやすく、神社の成り立ちについての入門書としては最適だと思う。まあ厳島神社五重塔については過大評価しすぎで、足利義満創建については考えられなくはないけど、根拠が乏しいかな。2022/12/15
乱読家 護る会支持!
6
神社とは? ⚫︎自然界の生命力を神として信仰し、迎え、祭る場である。 ⚫︎天つ神(稲の王である天皇を祭っている神)と国つ神(土着の首長を祭っている神)に分かれる。 ⚫︎磐座祭祀と水源祭祀は、現在まで伝承されているの基本的な信仰のかたちのひとつ。 ⚫︎三輪山や沖ノ島など、磐座祭祀から禁足地祭祀へと変化していっあ。禁足地祭祀は伊勢神宮の遷都などで現在まで続いている。 ⚫︎本殿は、伊勢神宮や春日社のような「非住居型・祭員非参入型」と、出雲大社など多くの神社で取り入れられている「住居型・祭員参入型」に分けられる。2022/05/14