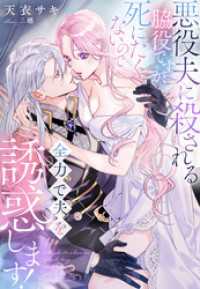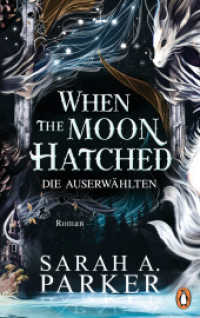内容説明
ひきこもりという存在が社会に認識されるようになって約20年。事態は解決に向かうどころかさらに深刻化している。支援の手が届かなかったひきこもりは40代、50代になり、80代の親が彼らを抱え込むことになった。近年、にわかに社会問題化した「8050問題」。その当事者と家族に焦点を絞った先に見えてくるこの社会の有り様とは? 深き苦悩を見つめた希望と救いのノンフィクション。
目次
はじめに
第1章 迷走する家族
強すぎる父
母に食い尽くされた息子
金と暴力がコミュニケーションの手段
放置された老婆、立ち尽くす娘
第2章 闇を照らす光
安心して引き込もれる社会に
いかに依存し合って生きていけるか
第3章 歩き始めた人たち
親となんか生きていきたくない
何もできないんです。助けてください
かっこつけたかった
第4章 「見えない」存在から「見える」存在へ
「ひ老会」の挑戦
8050問題が意味するもの
おわりに
文庫版あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サンダーバード@怪しいグルメ探検隊・隊鳥
87
80代の親が50代の引きこもりの子供を抱える「8050問題」。実に重い話である。何故一見幸せそうであった家族がそうなってしまったのか?多くの場合はそもそも親子のコミュニケーションが歪であった場合がほとんどだ。暴力、無視、あるいは過干渉…。身近な存在である親子でさえこんな関係であれば他人と良好な関係を築く事など難しいであろう。もちろん良い方向に向かっていくように国や自治体、周囲の人達が支えていかなければならないのだが、そこまで面倒を見ないと人間は生きていけないのかと思うと複雑な気持ちになる。★★★★2022/02/03
hiyu
5
読んでみると「ひきこもり」という言葉に妥当性があるのか悩む。自らの意思でという意味が込められているので。一方でひきこもりの背景には種々の理由や要因が幾重にも重なっていると思われるが、本書の中で示された方法論のうち、べき論については違和感がある。いわゆるひきこもりには伴走者が何よりも必要だろうと感じるから。2025/01/07
くらーく
3
引きこもりの中高年と同じ世代。キーワードは共依存か。どれも、悲惨な事例だし、あとがきを見ると、ほとんど状況は変わらず。親が年を取って、亡くなっている事例がちらほらですかね。それにしても、ここで取り上げられている親に真っ当な親がいないように見えるのはなぜだろうね。特に父親。自分の子供もきちんと育てられない、子供の気持ちも分からない体たらくなのに、会社ではそこそこ出世して高給を稼いでいた。日本の組織体(企業)は、おかしかったのかねえ。。再生物語って言うけど、これで再生?厳しいなあ。時間は取り戻せないものねえ。2023/03/12
sakichi
3
人生、どこで折れるか渦中の人にはわからないものだからね。2021/11/07
jupiter68
2
うーんやっぱ強烈だ。なかなか解決の道がない。見守るしかないのか、ということを思う。ただし、解決すべき当事者。当事者が動けるような体制づくりが必要、ということまでは理解したが、その次のアイデアがない。苦しい。2025/07/06