- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
古代から現代までの戦略思想家のなかから孫子(孫武)、マキャベリ、ジョミニ、クラウゼヴィッツ、マハン、リデルハートという六人を取り上げ、彼らが戦争と直接向き合い培った戦略思想のエッセンスを抽出する。六人それぞれの戦略思想を上位概念から、実際の戦場における戦い方についての考えまで幅を広げて検討。戦略概念を主軸に、政治と軍事の関係を焦点に分析し、最前線での用兵思想などのあり方についても考察する。古典から現代に至るまでの戦略思想の流れがわかる入門書。
目次
はじめに
「戦い」が消えた戦略
歴史を知るための戦略思想
古代から現代までの戦略思想家
本書の構成について
第一章 孫子
1 孫子の戦略思想1──戦わずして勝つ
古代の戦略思想家「兵家」
天下に知られた『孫子』
大戦略から戦術まで網羅する『孫子』
政治と軍事の関係
「戦わずして勝つ」の戦争観
武力による百戦百勝は否
事前のシミュレーションを重視
戦争は経済を疲弊させる
武力戦ならば短期戦
2 孫子の戦略思想2──武力戦の極意
攻勢はどこで戦うべきか
守勢は必ずしも不利ならず
武力戦に共通する原則──相対的な優勢の確保
分散と集中の運用の条件
目標は敵野戦軍
高等戦術を要求
情報活動を前提とする戦略思想
幅広いインテリジェンス論をめぐって
組織マネジメントとリーダーシップ
非情な運用方法による「勢」
武力戦のあり方の要旨
目標は戦争終結へと
3 『孫子』とその時代──群雄割拠と弱肉強食
古代の独特な戦争様相
戦争のルールに変化
孫武の出自とキャリア
孫武の登用への賭け
楚の攻略に功績
『孫子』の評価
孫武の限界
第二章 マキャベリ
1 マキャベリの戦略思想1──性悪説に基づく権力観
中世から近代へ──軍事の変遷
傭兵隊の存在
ベースにある性悪説
権力装置「ステート」という考え方
狐と獅子の性質を求める『君主論』
君主は「運命」を引き寄せねばならない
ギリシャやローマをモデルにした『ディスコルシ』
国防のために宗教も手段として利用
『戦争の技法』で用いた手法
市民軍の創設を主張
マキャベリの戦争観と戦争目的
財力だけでは国防は成立しない
同盟のあり方と依存について
2 マキャベリの戦略思想2──指揮権の統一
戦争は短期戦での主力決戦を
進撃して敵の領土で戦うか、自国で迎え撃つか
兵制を重視する考え
指揮権の統一について
訓練・規律・統率のスタンス
決戦の条件と指揮官への助言
3 マキャベリとその時代──傭兵隊から市民軍へ
マキャベリとその時代
シャルル八世のイタリア侵入
傭兵軍団の実態
ピサ戦役の失敗
市民軍創設へ
マキャベリの失脚とその後
マキャベリの総括
マキャベリの評価
第三章 ジョミニ
1 ジョミニの戦略思想1──戦争をいかに遂行するか
変わりゆく戦争様相
傭兵隊から常備軍へ
兵学理論の構築を重視
ジョミニの著作と影響
戦争の政治目的の類型
それら武力戦に伴う性質
政治と軍事の関係──政治指導者と軍事的指導者
「皇帝」に求められる資質
ジョミニの「戦略」定義
サイエンスかアートか
2 ジョミニの戦略思想2──内線作戦
不変の戦争術の原則とは
内線作戦について
作戦の型式について
拡大する作戦地帯
作戦基地・戦略要点・決勝点・目標とは
欺瞞や奇襲について
情報・インテリジェンスに対する態度
3 ジョミニとその時代──ナポレオンとともに
幼少から軍事に関心
フランス軍の大佐として
ナポレオンのジョミニ評価
制限戦争の時代
王朝国家の軍隊
高コストから戦闘回避
フリードリッヒ大王の軍事改革
その戦争の限界
ナポレオンの戦争
政治と軍事のトップを兼務
目標は敵野戦軍
ナポレオンの限界
ジョミニの評価
第四章 クラウゼヴィッツ
1 クラウゼヴィッツの戦略思想1──絶対戦争とは何か
比較的知られるクラウゼヴィッツ
『戦争論』は未完
観念上の絶対戦争
制限下の現実の戦争
政治と軍事の関係
両者の衝突について
純軍事的視座の問題
戦争の合理的な見積もりは可能なのか
戦争の三位一体
2 クラウゼヴィッツの戦略思想2──摩擦とは何か
摩擦と障害
攻撃と防御の関係
短期戦による勝利
軍事的天才という考え
欺瞞・奇襲・情報について
戦争の形態について
第一種の戦争と第二種の戦争
3 クラウゼヴィッツとその時代──プロイセン、ロシアでの活躍
クラウゼヴィッツの出身
シャルンホルストとの出会い
イエナの敗北
フランスで捕虜として
軍事改革への取り組み
ロシア軍に入る
士官学校長として
クラウゼヴィッツの評価
クラウゼヴィッツの「後継者」モルトケ
モルトケの戦略的包囲
外線作戦の使用
弟子を自称したモルトケ
もう一人の後継者シュリーフェン
第五章 マハン
1 マハンの戦略思想1──海上権力とは何か
海洋の戦いの歩み
近代海戦「黄海海戦」「日本海海戦」
海軍の戦略思想とマハンの登場
歴史における科学的な基本法則
シーパワー・海上権力という概念
『海上権力史論』の構成と緒言
海上権力・シーパワーの構成について
マハンの戦争観
政治と軍事の関係
2 マハンの戦略思想2──艦隊の戦略
マハンの海軍戦略──海軍の存在理由と通商破壊
海軍の集中の原則
艦隊は攻勢的要素か防勢的要素か
戦略地点について
海外遠征について
要塞艦隊主義と現存艦隊主義
3 マハンとその時代──帝国主義と日露戦争
マハンが培った宗教観
アナポリス卒業後
海軍大学校校長へ
退役後のマハン「大佐」
帝国主義へ
中国の存在を意識
日本への警戒心
マハンと秋山真之
日本のマハン
マハンの評価
第六章 リデルハート
1 リデルハートの戦略思想1──間接アプローチ戦略
ドイツ帝国の宿命
第一次世界大戦期の戦略思想家
「間接アプローチ戦略」のリデルハート
「大戦略」(高級戦略・グランドストラテジー)とは何か
国家レベルの「英国流の戦争方法」とは
政治と軍事の区分について
政府の目標変更について
「軍事戦略」(純戦略)の鍵は目的と手段の調整
2 リデルハートの戦略思想2──機甲戦理論
具体的攪乱方法について
牽制と代替目標
交通線の遮断
前進の柔軟なあり方──麻痺への追い込み
「機甲戦理論」研究と心理的攪乱
ゲリラ戦争について
「保守主義的国家」の大戦略とエンドステート
3 リデルハートとその時代──激戦の原体験
リデルハートのあゆみ
戦術より高い次元に
知名度が高まるリデルハート
第二次世界大戦中の言動
クラウゼヴィッツ批判の妥当性について
リデルハートの評価
終章 戦略思想の共通点と相違点
1 核抑止の戦略思想
核兵器の戦略思想
大量報復戦略という考え
相互確証破壊の成立
2 戦争とは何か
戦略思想家六人による「円卓会議」
戦争とは何か
戦争と倫理の関係について──孫武、リデルハート、クラウゼヴィッツの立場
戦争と倫理の関係について──ジョミニ、マハン、マキャベリの立場
3 政軍関係
政治と軍事の関係についての見解
政治と軍事の最高権力は兼務可能──ジョミニ、マキャベリの立場
政軍権力は組織的に区分──孫武、クラウゼヴィッツ、マハン、リデルハートの立場
戦争と経済について
4 いかに戦うか
戦争の手段をどう考えるか
武力戦中心のアプローチと限界
合理性の価値
戦争の期間について
攻勢と防勢(守勢)、攻撃と防御について
大戦略レベルの攻勢と防勢について
敵をどこまで追い込むべきか
殲滅戦に疑義を呈する孫武とリデルハート
核戦力をどう考えるか
戦争の終わらせ方について
あとがき
主要参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
巨峰
ふみあき
masabi
qwer0987
かっさん
-

- 電子書籍
- 嘘つき達の恋愛リアリティー【フルカラー…
-
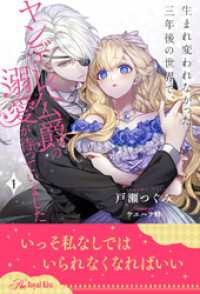
- 電子書籍
- 生まれ変われなかった三年後の世界で、ヤ…
-
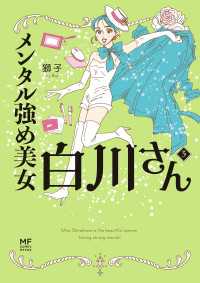
- 電子書籍
- メンタル強め美女白川さん3【電子特典付…
-
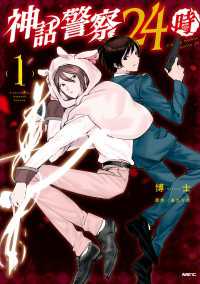
- 電子書籍
- 神話警察24時 1 MFC
-
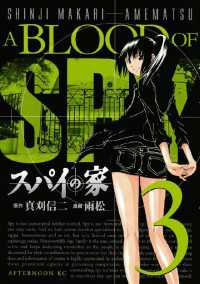
- 電子書籍
- スパイの家(3)




