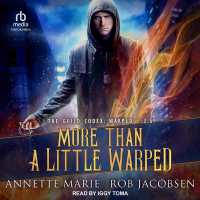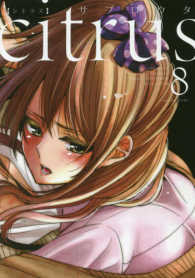内容説明
私はこの本で、現代の倫理学で議論される原理的な問題と応用倫理学で取り扱われる内容を、明確に描き出したい。それには日常生活で出会う倫理問題を考えることが、現代倫理学の中心問題を理解する早道だと思う。難しい術語や学説の違いを知るより、現代の倫理学者達の議論の中身に入ってもらいたいという気持ちで書いた。何よりもまず、読み物として面白く通読できるよう心がけた。(「あとがき」より)
目次
1 人を助けるために嘘をつくことは許されるか
2 10人の命を救うために1人の人を殺すことは許されるか
3 10人のエイズ患者に対して特効薬が1人分しかない時、誰に渡すか
4 エゴイズムに基づく行為はすべて道徳に反するか
5 どうすれば幸福の計算ができるか
6 判断能力の判断は誰がするか
7 〈……である〉から〈……べきである〉を導き出すことはできないか
8 正義の原理は純粋な形式で決まるのか、共同の利益で決まるのか
9 思いやりだけで道徳の原則ができるか
10 正直者が損をすることはどうしたら防げるか
11 他人に迷惑をかけなければ何をしてもよいか
12 貧しい人を助けるのは豊かな人の義務であるか
13 現在の人間には未来の人間に対する義務があるか
14 正義は時代によって変わるか
15 科学の発達に限界を定めることができるか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
田氏
24
言葉を覚え始めた娘が、やがて「ねえねえ、『正しい』ってなにー?」なんて聞いてくる。そんな日が来たときに備えて、正しさとはなんだろうと日々考えているのだが、自分にそんな日が来る見込みはゼロに等しいので杞憂である。うーん、正しさを評価するものにとって、その行為により生じるコストが受け入れ可能であるか否かの差なんじゃないかと僕は思ってる。わかんなーい。そんな受け答えを想定するのも杞憂である。あのさ、あのときお父さんの定義した正しさって、正しかった?成長した娘の問いに答えることができないシーンの想像も杞憂である。2020/12/13
テツ
21
このあやふやな世界の中で揺らぐことがなく破壊されることのない確固とした何かを見出したい。非の打ち所がなく自らの礎となる規範が存在したらどんなに楽になるのだろう。そのために積み重ねる思考。ありとあらゆる問題に対して自分の思考と言語だけで渡り合う訓練。人の身でどれだけ積み重ねたとしても完璧な(狭義の)道徳に至ることもなければ、真理に目覚めることもないのだろう。人に許されるのはそこに到達するための道を見出し、到達しないことを知りながら歩み続けていくことだけ。2020/08/05
neputa
19
日常にあふれる情報の波に押し流されぬよう、倫理学の門を叩くことに。先に読み始めた『入門・倫理学』は網羅的・体系的に倫理学をまとめており良いが、論文集の色合いが濃く用語や訳の難解さに直面。実際の社会問題と倫理を併記して紹介する本書を並行して読み進めることにし、これが正解だった。自己啓発本のように答えを明確に示すものではない。だが掲載されている賢人たちによる思考の蓄積は、日々の生活で直面する善性や正しさに対する迷いを、どう思考整理し捉えるかの大きな助けになると感じた。しばらく倫理学に傾倒してみようと思う。2023/02/20
ヤギ郎
16
倫理の教科書に必ず登場する哲学者の理論を借りながら、現代が抱える道徳的問題を考察してゆく本。ただただある一人の哲学者の著作を読み解き、その人の理論を学んでゆくような構成ではなく、より実践的な哲学考察を行っているので、内容を身近に感じまた面白い。現代倫理(道徳)を考えるベースとなる一冊。2015/09/28
里馬
16
とうとう入門してしまった。『正義』とか『幸福』などと抽象的で曖昧な物を扱う学問なんて胡散臭いと思っていた。ふうーっ。こりゃあいつもあいつもあいつも倫理学に惚れこむ訳だ。カントやミル、加藤尚武に出会えて嬉しい。2009/06/06
-
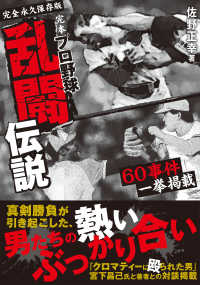
- 電子書籍
- 完本 プロ野球乱闘伝説
-
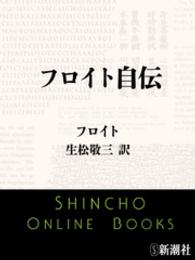
- 電子書籍
- フロイト自伝 新潮文庫