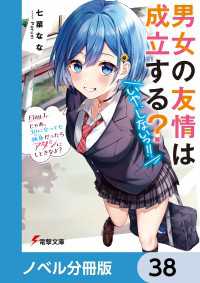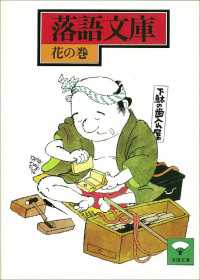- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
チームの主体性と創造性を発揮したい、すべてのマネージャー必携!
ベストセラー『問いのデザイン:創造的対話のファシリテーション』の著者による最新作
仲間と力を合わせ、チームで成果を出すためには、周囲に投げかける「問いかけ」の質を変えることが重要です。
著者の長年の研究と実績をもとにノウハウ化された、チームの眠っているポテンシャルを最大限に発揮させるための「問いかけ」の実践的指南書!
「さあ、この企画に何か意見はありませんか?」
「どんどんアイデアを提案してください! 」
と呼びかけても、プロジェクトメンバーたちは、互いに発言権を譲り合うように、一向に口を開いてくれない
「遠慮なく意見していただいて構いませんよ」
「どなたか、いかがでしょうか?」
といった呼びかけも虚しく、期待していた「画期的な提案」はおろか、誰も「自分の意見」さえ述べてくれない
――こんな状況に遭遇した経験、ないでしょうか?
これは、多くのチームで発生している「孤軍奮闘の悪循環」と呼ばれる状況です。
一度このサイクルに陥ると、チームの主体性と創造性はどんどん下がっていきます。
そして皮肉なことに、優秀でモチベーションの高い人ほど、このサイクルによってチームのポテンシャルを抑制し、そしてチームから孤立していくのです。
しかし、本書に興味を持ったあなたが思い描く理想は、仲間と力を合わせて「チームで成果を出す」世界であるはずです。
では、この悪循環に陥らずに、チームと職場を魅力的な場に変えるためには、どうすればいいのか?
それは、周囲に投げかける「問いかけ」の質を変えることなのです。
これからの時代、仕事は「自力」ではなく、「他力」を引き出せなくては、うまくいきません。
問いかけの技術を駆使することによって、周囲の人々の魅力と才能を引き出し、一人では生み出せないパフォーマンスを生み出す。
これが、現代の最も必要なスキルの一つなのです。
あなたひとりの実績を磨くよりも、「問いかけ」によるチームの力を高めていったほうが、結果として
「あの人と一緒に働くと、気持ちよく仕事ができる」
「あの人のチームだと、良い成果が出せる」
「あの人のもとでは、次々に良い人材が育っている」
といった「あなた自身の評価」へとつながり、活躍の場も広がっていくのです。
そして何より、一人で孤独に努力を重ねるよりも、他者の才能を活かしながら働くほうが、圧倒的に仕事が楽しくなることでしょう。
【停滞した場を打破する! とっさの質問リスト】
■素人質問
「すみません、これどういう意味ですか?」
「初歩的な質問なのですが、これはどういうことですか?」
「理解不足で申し訳ないのですが、このプロジェクトの目的はなんですか?」
■ルーツ発掘
「どこにこだわりがありますか?」
「なぜそこにこだわるのですか?」
「いつ頃からこだわるようになったのですか?」
「○○○とは何が違うのですか?」
■真善美
「『正しい○○○』とはなんでしょうか?」
「本当の意味での『良い○○○』とはなんでしょうか?」
「今こそ考えたい『美しい○○○』とはなんでしょうか?」
■パラフレイズ
「その言葉を、別の言葉に言い換えるとどうなりますか?」
「その言葉を、別のものに喩えるとどうなりますか?」
「その言葉を、このミーティングでは禁止しませんか?」
「その言葉を、数字で表現すると、100点満点で何点ですか?」
「その言葉を、改めて定義するとしたら、どのような言葉になりますか?」
■仮定法
「もし~だとしたら、どうでしょうか?」
「仮に~だとすると、どうなりますか?」
「もしあなたが~の立場だったら、どう考えますか?」
「もし制約がなかったら、どうしたいですか?」
「もし世界が~だったら、どうなっているでしょうか?」
■バイアス破壊
「本当にXは必要ですか?」
「Xを除外してみると、どうなるでしょうか?」
「Xでない~は、考えられないでしょうか?」
「XにあえてYを入れると、どうなるでしょうか?」
- 評価
🧑🏫✨本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
ニッポニア
黒縁メガネ
練りようかん
bookreviews