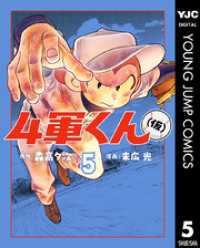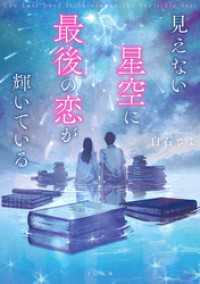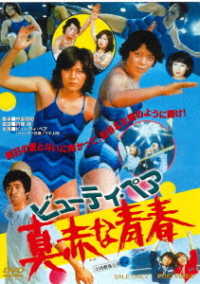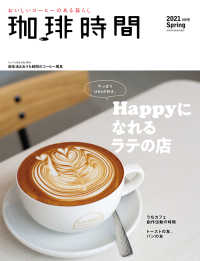内容説明
自由とは新たな挑戦だ
第一部では、2007年にブルガリア最後の「踊る熊」たちがいかにして動物保護団体に引き取られたか、そして生業を奪われた飼い主のロマたちが陥った困難な状況について、さまざまな立場の関係者を取材する。第二部ではソ連崩壊以降のおもに旧共産主義諸国(キューバ、ポーランド、ウクライナ、アルバニア、エストニア、セルビア、コソボ、グルジア、ギリシャ)を訪ね、現地の人々のさまざまな声に耳を傾ける。そこに共通するのは、社会の変化に取り残されたり翻弄されたりしながらも、したたかに生き抜こうとするたくましさである。
第一部と第二部はそれぞれ同じ章立て。共産主義の終焉から資本主義に移行しきれない国、またはEUに組み込まれたことで経済危機に陥った国の人々の混乱と困惑を、隷属状態から逃れても「自由」を享受しきれない「踊る熊」たちの悲哀に見事になぞらえ、重ね合わせている。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナーキー靴下
74
伝統であった熊使いが動物虐待と認定され、解放された熊たちは自由を得たはずだった。その踊る熊たちに重ね合わせるように、共産主義体制崩壊後の人々の苦悩を見せるルポルタージュ。共産圏の人から見たら、西側の人間は皆、エンデの「モモ」の灰色の男のように見えるだろうか。数十年、或いは数世紀を経れば、尊厳など皆無の劣悪な環境は犯罪であったと一元化できるのかもしれない。しかし異なる価値観の中で生きてきた人にとっては一生が過渡期、割りきれぬ思いを抱えたまま、それでも人生は続く。万民のハッピーエンドはない。重い内容だが傑作。2021/06/20
syaori
70
ポーランドの作家によるルポ。1部ではセンターに集められ「自由」を学ぶことになったブルガリアの熊使いの熊たちを、2部では独裁から資本主義への体制転換で熊同様「自由に対処」することになった旧共産圏の人々を追ってゆきます。浮かび上がるのは突然の価値・体制変換のなかでもがく人々で、同時に資本主義下の「自由」は失業や困窮など、苦しく不安でもあるということ。まさに「人の数だけ」あり、単純な肯定や否定では測れないその声の中で、自由の「対価」、「痛」みを「払う覚悟はあるだろうか?」という作者の問いが棘のように残りました。2024/02/14
ヘラジカ
63
ソ連崩壊後に共産主義から資本主義への体制転換を余儀なくされた国々を、ブルガリアの伝統芸「踊る熊」の終焉と重ね合わせ、当時と現在の人々の痛みを活写したルポルタージュ。資本主義からすれば自由の勝利として片付けられ勝ちな一幕が、末端の人々にどのような苦悩と当惑をもたらしたか。動物愛護の観点から保護された熊たちは、そのまま変化にもがく人々の比喩になっている。解き放たれ自由になり、でもそれには限度があって、馴染める者もあれば長らく馴染めない者もいた。第一部を世界の旧共産諸国に拡大、対応させた第二部も素晴らしい。2021/03/04
キク
55
社会主義国家の崩壊により、自由を手にしたはずの「見せ物用の踊る熊」と「社会主義体制の犠牲者としての国民」。でも熊使いから解放された熊は、保護施設内でも踊ることをやめない。社会主義体制で育った国民は、熾烈でスピードの速い資本主義社会の競争に参加できないと戸惑う。染み込んだ価値観は例え鼻輪が外されても、国家体制が変わっても、今更簡単には変えられない。慣れ親しんだ強制された生き方から、解放されることが必ずしも幸せとは限らなかった。読んでて、今の僕たちも多分何かしらの鼻輪を付けられているんだろうなと思った。2022/01/16
つちのこ
40
熊使いのロマたちから引取られた踊る熊たち。歯を抜かれ、鼻鎖をされ、アルコール漬けにされた熊たちは、楽器の伴奏に合わせて後ろ足で立って踊り、小金を稼ぐ。共産主義体制の終焉とともに熊たちは自由の身になるが、人間の匂いや声に敏感に反応し、ほとんどの熊が再び踊り出す。突然与えられた自由に対処できない哀しさがそこにはある。後半ではソ連崩壊後の旧共産主義諸国で、自由を受け入れられず右往左往する経済的弱者の人々を描く。真の自由とは何か?自由の価値観を問いかけ、つかみ取ることの難しさを踊る熊に重ねた渾身のルポである。2021/12/20