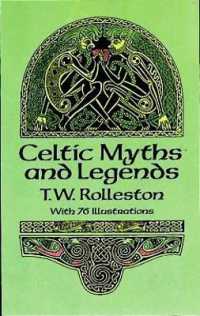- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
新型コロナウイルスの感染拡大を機に、不登校・ひきこもりの子どもたちはますます増えている。しかも、休校に分散登校、オンライン授業に加えて家庭ごとのコロナ対策もあって学校に行かないことが自然となり、行政もその実態を把握しきれていない。不登校・ひきこもりが「見えなくなっている」のだ。こうした状況の中、支援現場ではどのような対応に迫られたのか。オンラインも駆使しながら支援にあたっている様子を報告する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yam6
4
わたくしも、小中学校のオンライン授業は不登校を助長する、ぎりぎり登校できていた子供を不登校にしてしまう、と考えていたので、本著の内容には大方賛同できる。ただし、杉浦氏や高卒支援会が対象としている生徒は高校大学へ進学させることが可能な家庭の子なので、貧困が根底にある不登校児に関わっている自分にはあまり役に立たない内容であった。2022/01/16
TOMTOM
2
不登校のアウトリーチと高卒パスポートをもたせるために活動されている筆者らの、コロナ前から現在の取り組み。コロナによって、オンラインだから出席できる者もいる一方で、すこしずつ生活リズムが戻ってきた者がまた崩れがちになったりと。一人でも多く、社会に出て働く喜びを知ってほしいと根底に感じる。2021/11/28
c.k
1
図書館本。年末年始休みで読めた。男子はひきこもり、不登校。家族関係も悪い。女子は不登校のみで、家族関係は良好な場合が多い。引きこもった年月の分、立ち直りにも時間がかかり、早期対応が大切。いくら学力がついても、いくら友だちができても、朝起きて学校に行かなければ意味がない。規則正しい生活習慣がつくと体力もついてくる。仲間もできて楽しく行けるようになる。自分自身を受け入れるには、まず誰かに受け入れられる経験が大切。規則正しい生活→自律して自信をつける→社会貢献する 2023/01/02
ジョルジオ鈴木
1
★★★★ 学校に復帰するには不登校になった期間と同じくらいの期間が必要であること、共感できるインターン生が有効であることを学んだ。 親との信頼関係の欠落の連続が最終的に不登校を招く。愛情が過剰すぎても良くないし放任すぎても良くない。自律性を維持しながら対話の時間を積み重ねることが重要。 コロナが立ち直る機会を奪っている一方で、オンライン授業が復帰のきっかけにもなっている。感覚値では、3割の児童生徒はオンラインが向いている。 名著 2022/07/26
Go Extreme
1
コロナショックによる不登校・ひきこもりの急増と不透明化: 増加した子どもたちの自殺 コロナ欠席で不登校とカウントされず 言い訳・コロナだから コロナショックで困難になる立ち直りへのステップ ひきこもりからの復帰遅れ 立ち直る過程で起こった、コロナによる挫折 オンラインが救った不登校・ひきこもりの生徒たち: 3割の生徒はオンラインのほうが合っている コロナ禍における教育支援センターの問題点 アウトリーチ支援 将来を見据えた特別授業と支援の広がり ゲームの有効性 生活改善合宿 一人暮らしのすすめと、親の覚悟2022/01/01