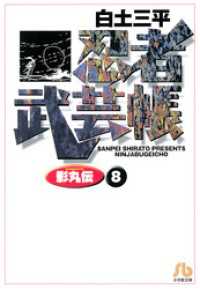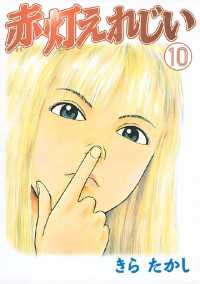内容説明
本書は、言語に関する素朴な疑問から出発し、その疑問に答えるにはどうしたらよいか、という形で議論を進める。言語学や哲学や論理学の予備知識を要求しない、文字通りの入門書である。しかし、哲学一般にいえることだが、哲学は何か完成された知識を暗記することではないので、本書もじっくり考えながら読む必要はある。そうすることによって、知識ではなく、「思考の方法を学ぶ」という哲学の核心を身に付けることができる。テーマは、より専門的な文献を読む基礎になるもの、関連した分野のトピックスに配慮したものを選んだ。
目次
まえがき
第一章 言語哲学とは何か
言語学者は言葉についての問いのすべてに答えるわけではない
言語哲学は「科学」ではない
言語学と言語哲学
第二章 意味と指示
意味のあるなし
「何かを表す」とはどういうことか
同一性を表す文の問題
「意味」と「意義」
文の「意味」と「意義」
「意義」とは何か
意味と情報伝達
第三章 記述の理論
「現在のフランスの国王」の意味は何?
ラッセルの記述の理論
ストローソンの批判
真理値の担い手
確定記述の二つの使用
第四章 固有名の問題
指示対象のない固有名
固有名に関する記述説
「記述の束」説
「徳川家康が関ヶ原の戦いで負けていたら」――記述説に対するさらなる批判
固有名に関する因果説(または指示の因果説)
因果説の問題点
関連する話題――可能世界意味論との関係
第五章 意味についての検証主義
意味に関する検証主義と意味の検証理論
有意味と思えるが検証不可能な文
分析的な文を別扱いにする
分析的な文とは何か
意味の全体論
論理実証主義運動
第六章 意味懐疑論と翻訳の不確定性
客観的対象としての意味について考える
意味の同一性
交換可能性による説明
意味論規則
意味懐疑論
翻訳の不確定性
データから何が決まるか
クワイン―チョムスキー論争
第七章 サピア=ウォーフの仮説
言語と文化の関係
文化とは
サピア=ウォーフの仮説
カントの相対化?
言語を適切に翻訳しているか
概念(の所有)を言語と独立に同定できるか
言語と文化を独立に同定できるか
サピア=ウォーフの仮説のテスト
親族関係と親族に関する言語表現
相関関係≠因果関係
哲学的主張としてのサピア=ウォーフの仮説
第八章 プラグマティックス
文それ自体の意味と話者の言わんとするところ
話者の言わんとするところを推論する
会話の含意
発言は行為でもある
事実確認的発話と行為遂行的発話
言語行為論
文の意味を発話の意味によって定義できるか
「意味とは使用である」という説
グライスによる意味の定義
第九章 私的言語論
「あなたに私の気持がわかる?」
私的言語の可能性
暗号は私的言語ではない
ウィトゲンシュタインによる私的言語の定義
私的言語を擁護する議論の検討
私的対象を指示するということは可能か
「この痛み」という言葉は私的なものを指示しているのか
考察
第一〇章 言語についての知識の本性
知識の起源についての二つの考え方
言語の知識についての経験主義的説明
言語能力と言語運用の区別
文法の知識
子供は文法規則を帰納的推論によって知るのか?
深層構造
生得性仮説
第一一章 言語の体系的研究の可能性
ウィトゲンシュタインの前期の言語観
『探究』における『論考』批判
言語の体系的研究は可能か
反論
参考文献
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
zirou1984
白義
Z
センケイ (線形)
愛楊