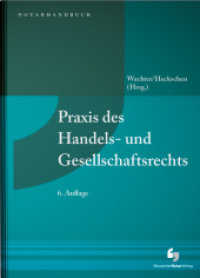内容説明
音楽評論家にして名盤復刻レーベルの主宰者が名盤・奇盤を世界中からかき集め、レビューはもちろん演奏家たちのエピソードや業界の裏事情など、おもしろ/びっくりの話題をたっぷりと語る。
東欧で活躍する指揮者・小林研一郎の『第9』を聴きに訪れたチェコ・プラハで数々の音楽遺産に感動し、ドイツ・ベルリンで訪れた悲運の指揮者レオ・ボルヒャルトの広大な墓地をさまよう。評論家のクリストファ・N・野澤や濱田滋郎、日本コロムビアのプロデューサー川口義晴ら故人とのかけがえのない思い出を語り、同じ戦争を別の場所で経験した黒柳徹子とセルジュ・チェリビダッケに思いを馳せる。
どこまでも本物の音にこだわってデジタル技術の発達による過剰編集を喝破し、自身のレーベルでリリースしたCDの制作秘話や業界裏事情、TPP締結で受けた損害までを赤裸々に語る。
「そうなんだ!」のエピソードと「なるほど!」の造詣から繰り出す演奏評で読者をクラシックの深淵に誘う待望のガイド。
目次
No.1 驚愕! 半音低いシュヴァルツコップの『4つの最後の歌』(リヒャルト・シュトラウス)
No.2 プラハで聴く小林研一郎とチェコ・フィルハーモニー管弦楽団
No.3 クリストファ・N・野澤をしのぶ
No.4 悪用されているデジタル技術
No.5 戦前のベルリンで活躍した指揮者、オスカー・フリート
No.6 テオドール・クルレンツィスを検証する
No.7 プロデューサー、川口義晴のこと
No.8 夭折の女性チェリスト、アニア・タウアー
No.9 美輪明宏とカルロス・クライバー
No.10 世界で最初にメトロノーム演奏をおこなった、アルバート・コーツ
No.11 黒柳徹子とチェリビダッケ
No.12 アーノンクールについて、懐かしさと戸惑いと
No.13 トスカニーニの記念の年に
No.14 フランス・ターラの主宰者ルネ・トレミヌ
No.15 ムラヴィンスキー研究の第一人者・天羽健三のこと
No.16 ジョージ・セル、好きではないけれど、やはりすごい
No.17 ブルメスターと「幻の長時間録音」
No.18 伝説のプロデューサー、ジョン・マックルーアとの関わり
No.19 世界最古のベートーヴェン『「田園」交響曲』を聴く
No.20 ボッセとベルグルンド
No.21 悲運の指揮者、レオ・ボルヒャルト
No.22 カレル・アンチェルの著作から
No.23 ムラヴィンスキーのチャイコフスキー『後期3大交響曲集』を再検証する
No.24 フルトヴェングラー・ドイツ帝国放送局1939-1945
No.25 追悼、スクロヴァチェフスキを中心に
No.26 ジョン・ハントのディスコグラフィー
No.27 映像によるクレンペラーのベートーヴェン『交響曲全集』
No.28 伝統の響き、フランツ・コンヴィチュニー
No.29 ホルストの『組曲「惑星」』、公開初演100年記念
No.30 ベートーヴェンの交響曲の反復記号について
No.31 録音黎明期のオーケストラ録音からみえてくるもの
No.32 お徳用盤は、結局のところお得ではない?
No.33 CD制作手記
No.34 安倍政権とTPP
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
Wataru Hoshii
Teo
Go Extreme
-
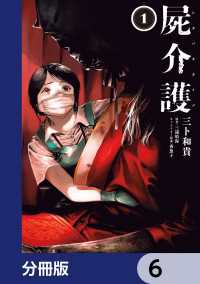
- 電子書籍
- 屍介護【分冊版】 6 青騎士コミックス
-

- 電子書籍
- 既婚者サークル~妻と夫の別の顔~ 第1話