内容説明
終盤戦にはパターンがある、と強者は言います。
しかしそれは数多く指して体で覚えるもの、というのがこれまでの常識でした。
「現代将棋を読み解く7つの理論」のあらきっぺ氏は、終盤戦においても理論とことばを大事にします。
一般的な概念から終盤戦を分析し、難しい局面の核心を切り開いていく解説は必読です。
優勢な局面には、必ず勝利への正しい道があります。
本書を読んで、あなたにとっての王道を見つけてください。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ま
31
将棋の格言っていくつもあるけど断片的なもの。著者はこれらを「露出」「反射」など自分の言葉で紡いで見事に体系化している。前作に続き素晴らしい。既存の次の一手問題集とかをこの本のワードでまとめ直すのも良策かもしれない。他方でコラムに「名前」と題するものがあったので、謎な著者名の由来が分かるかと思いきやそうでもなく、しょうもない内容だった。ワードセンスがあるのかないのかようわからん著者であったw2022/09/24
akihiko810/アカウント移行中
25
元奨励会3段ブロガーによる、将棋の終盤戦のセオリーを言語化した本。印象度A 著者あらきっぺの本は2冊目だが、さすがの詳しい内容。対象棋力は初段程度。 終盤の寄せ(囲い剥がし)と凌ぎ、そして攻防手についてのセオリーが詳しく述べられている。これを読んで、凌ぎが少しだけうまくなった。 「開拓」といって、入玉するために上部の邪魔駒を排除する手は、敵玉に迫らない1手パスにも見えるので目から鱗。あと、「占領」といって、玉周りの空間を味方の駒で支配する玉頭戦はかなり難解だと思った。2022/12/05
akihiko810/アカウント移行中
18
再読。元奨励会3段ブロガーによる、将棋の終盤戦のセオリーを言語化した本。印象度A 対象棋力は初段以上程度。 終盤の寄せ(囲い剥がし)と凌ぎ、そして攻防手についてのセオリーが詳しく述べられている。 春日部将棋教室で終盤戦のコツを習ったので、復習・補強にこの本を再読。 終盤の速度計算、自玉のZ、攻防手など参考になるが、本の終盤は結構難解なので、まだ完全に理解するには時間がかかりそう2025/05/29
Book Lover Mr.Garakuta
18
【図書館本】【速読】:こちらも雑に読み飛ばすにはもったいない本。飛ばし読みではなくじっくりと時間をかけないと良く分らない様に思う。面白いのは面白いが専門性も高く入門者には難しいかも、只全局の流れは俯瞰できるし、考え方の基本を学ぶにはよいかも知れません。ある程度の実力を持った人が基礎固めするにはよいと思われます。2022/02/12
アンパッサン
4
たくさんの参考書があるのにいまひとつ、ピンとこない。こないまま、かかれてあるとおりに学ぶんだけど、わかったようなわからないようなまま。が、予備校で板書された途端、一切が新しくとらえ直され、受験生の脳内に深く刻まれる理解。この本はまさしくそれだ。素晴らしい言語化、イメージ化。また表現がクラウゼビッツかよと思わせる文体。まったくあたらしい棋書ではないか?大変よかった。2022/04/19
-
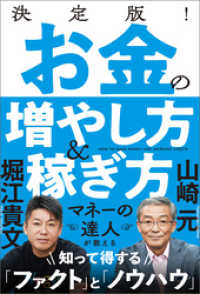
- 電子書籍
- 決定版! お金の増やし方&稼ぎ方








