内容説明
地下深い研究施設スーパーカミオカンデでの観測によってノーベル物理学賞に輝いた梶田隆章さん。その研究を語る肉声とともに、取材を続けてきた朝日新聞記者が、ニュートリノ振動とは、授賞式、生い立ち、研究史、さらに日本科学の危機について解説する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
re;
18
日本科学未来館でカミオカンデの光電子増倍管を見た。直径50cmのドーム型の物体が壁一面に並んでいる。全くの素人に分かりやすく説明してくれたスタッフの方達のお陰で、根っから文系の私は素粒子の虜となった。ニュートリノに質量があることを発見してノーベル賞を受賞した梶田隆章さんの言葉には『やりとげ続ける人』の強さがある。私達を、ひいては宇宙を構成する『物質』とはなんなのか。その一端を紐解く純粋科学の面白さに取りつかれた梶田さんの生き様が素敵。素粒子の世代の話はやっと腑に落ちた!解説書としても分かりやすく優秀!2020/12/24
黒豆
9
梶田さんはニュートリノ研究の立ち上がり時期と研究の中心となる時期が重なっているようだ。カミオカンデ用に開発された技術として 、浜松ポトニクスの光電子増倍管が有名だが、三井金属-大空間の掘削工事、三井造船-5万トンの水槽建造、富士通-膨大なデータ解析、オルガノ-超純水システムなども興味深かった。次のニュースはKAGRAでの重力波検出か?あとがきに池澤夏樹さんの「スティルライフ」で、グラスの中の水をじっと見つめながら、「ひょっとしてチェレンコフ光が見えないかと思って」2016/07/24
toshi
7
表紙には梶田隆章氏の名前がまるで著者のようにレイアウトされているけれど、梶田氏の講演などでの発言を引用しつつ項目別にまとめた本。 先日読んだニュートンはニュートリノについての分かりやすい解説だったけれど、この本は裏話的な内容や周辺の話が中心で、ニュートリノについては少ししかページを割いていないし、書いた人も分かっていないんじゃないかと思われるほど分かりにくい。だから、ニュートリノについて知りたい人は別の本をお勧めします。これは科学的な好奇心を満たすのではなく、その裏の人間ドラマを描いた本です。2016/07/21
ふるしゅん
6
おもしろかった。2015年にノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章さんについてのお話。ニュートリノや関連研究についての解説から、梶田さんの半生、研究施設であるスーパーカミオカンデについて、企業の貢献、日本の科学教育・研究職の現状など。ニュートリノについての難しい話は斜め読み。チャンスに出会うためには、日頃から広く目と心を開いて準備をしておくことが重要。ノーベル博物館に贈呈する品に、日本製の光電子増倍管だけでなく、研究撤退したアメリカグループのものも用意したところに梶田さんの人格の素晴らしさを感じた。2021/10/17
kaorin
6
ニュートリノとは、質量で3種類に分類されたν1、ν2、ν3、という異なる周波数を持つ波のうち、2種類の混合(波の重なりのうなり)によって3種類のフレーバー(電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノ)に分かれるとある。また、神岡にはスーパーカミオカンデ以外にXMASS(ダークマター観測)、KAGRA(重力波観測)、カムランド(反ニュートリノ検出)、阪大のCANDLES(二重ベータ崩壊観測)等の施設もある。16年予定のハイパーカミオカンデではニュートリノのCP対称性の破れの発見を目指している。2016/08/03
-
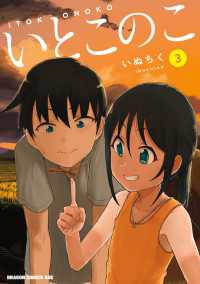
- 電子書籍
- いとこのこ 3【2色カラー特別版】 ド…





