- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
原材料調達から生産・販売に至るまで、モノの流れを効率的に管理するSCM(サプライチェーンマネジメント)は、企業のグローバル化、国内物流の困難さ、ネット販売、アマゾンに代表されるビジネスモデルの変革などに対応するため、より進んだSCM構築が急務となっている。本書は、学会創立20周年に当たって計画された、新たなSCM構築に向けて、SCM戦略のマネジメントと関連手法を体系的に解説した、わが国初のSCM総合ハンドブックである。
目次
第Ⅰ編総括編
1 SCM関連行政と一般的動向
1.1 SCMと行政の関わり
1.1.1 はじめに
1.1.2 行政におけるSCM関連の経緯概要
1.1.3 総合物流施策大綱の概要
1.1.4 わが国の課題
1.2 SCM関連行政と一般的動向
1.2.1 循環型社会における環境規制関連の法規体系の大枠
1.2.2 SCM行政における環境法規
1.2.3 サプライチェーンセキュリティ
1.3 リバースチェーンマネジメントの体系
1.3.1 リバースチェーンマネジメントの領域
1.3.2 フォワードチェーンとリバースチェーンの関係
1.3.3 グリーンサプライチェーン
1.3.4 リバースチェーンマネジメントの体系
1.4 SCMコスト
1.4.1 原価の本質
1.4.2 原価計算の方法
1.4.3 原価計算の目的
1.4.4 原価管理と標準原価
1.4.5 原価管理の範囲
1.4.6 SCMの二面性
1.5 モーダル別輸送とモーダルリンケージの展望
1.5.1 日本の物流動向
1.5.2 モーダルシフトについて
1.5.3 モーダルリンケージ
1.6 グローバルSCMネットワークシステムの基本
1.6.1 はじめに
1.6.2 ハブの定義と一般類型
1.6.3 ハブ関連輸送方法論の考察
1.6.4 モーダルリンケージとモーダルシフト
1.6.5 グローバルハブネットワークモデルの基本
1.6.6 モーダルリンケージ型グローバルハブネットワーク類型
1.6.7 基本グローバルハブネットワークモデル
1.6.8 おわりに
第2 章SCMの歴史的発展
2.1 はじめに
2.2 合理化の推移
2.2.1 製造合理化の時代
2.2.2 マーケティング合理化の時代
2.2.3 事務・情報合理化の時代
2.2.4 研究・開発合理化の時代
2.2.5 物流・ロジスティクス・SCM・3PL合理化時代
2.3 物流,ロジスティクス,SCMの発展過程
2.3.1 日本における物流の起源
2.3.2 物流からロジスティクス
2.3.3 米国の変遷
2.4 おわりに
第3 章SCM(供給連鎖管理)の定義
3.1 はじめに
3.2 物流の定義
3.3 ロジスティクスの定義
3.4 3PLの定義
3.5 SCMの定義
3.5.1 定義の調査
3.5.2 SCMの定義の混乱要因と結果
3.5.3 定義の基本
3.6 おわりに
第4 章SCMの目的と使命・範囲・発展段階
4.1 はじめに
4.2 SCMの目的
4.2.1 目的の定義と発展形態
4.2.2 目的に関する考え方
4.3 SCMのビジョン
4.4 SCMの管理
4.4.1 SCMの範囲
4.4.2 SCMの発展
4.4.3 SCMの管理
4.5 おわりに
第5 章経営戦略の基本
5.1 はじめに
5.2 戦略の定義
5.3 代表的な経営戦略関連理論の引用
5.4 代表的な意思決定理論の引用
5.5 代表的な多角化戦略論の引用
5.6 おわりに
第6 章経営戦略の基本展開
6.1 はじめに
6.2 経営計画と経営戦略の基本
6.2.1 経営計画の種類と特徴
6.2.2 戦略計画の基本類型
6.2.3 戦略計画の展開
6.2.4 階層構造型戦略の構造と展開
6.3 おわりに
第7 章SCMチャネルの基本
7.1 はじめに
7.2 流通チャネルの基本モデル
7.2.1 既存流通チャネル
7.2.2 新(現代)流通チャネル
7.3 生産形態別流通チャネルの基本
7.3.1 日本の産業別流通チャネルの基本
7.3.2 日本の生産形態別流通チャネルの基本
7.3.3 生産形態別総流通チャネルの基本
7.3.4 供給連鎖概要の提案
7.4 おわりに
第8 章SCMと機会損失
8.1 SCMネットワークにおける機会損失の展望
8.1.1 機会損失とは
8.1.2 サプライチェーンとは
8.1.3 SCMの機会損失の展望
8.1.4 SCM戦略の要素
8.2 流通業における機会損失
8.3 製造業における機会損失
8.4 機会損失の分析とゼロ化の方法
8.4.1 SCMと情報共有化
8.4.2 機会損失のゼロ化の方法
第9 章経営におけるSCMの役割
9.1 経営における2つの側面の統合
9.2 協調指向型SCMの必要性
9.2.1 協調指向型SCMとは
9.2.2 SCM以前の協調取組み
9.2.3 協調指向型SCMの必要性
9.3 共同指向型SCMの展望
9.3.1 SCM共同化の基本
9.3.2 共同化推進主体
9.3.3 共同化基本要素
9.3.4 共同指向型SCMの展望
9.4 SCMの新しいミッション
9.4.1 SCMの新しいミッション
9.4.2 オムニチャネルとは
9.4.3 オムニチャネルとSCM
第10章SCMの基本業務機能
10.1 荷役機能
10.1.1 荷役とは
10.1.2 荷役の機械化・自動化
10.1.3 荷役合理化の考え方
10.2 包装機能
10.2.1 包装とは
10.2.2 包装の機能
10.3 保管機能
10.3.1 保管とは
10.3.2 保管の意義
10.3.3 倉庫の種類
10.3.4 倉庫の体系
10.3.5 名称による区分
10.4 輸・配送機能
10.4.1 輸送とは
10.4.2 輸送の形態・機能
10.5 流通加工機能
10.5.1 流通加工とは
10.5.2 流通加工の目的
10.5.3 流通加工の必要性
10.6 情報機能
10.6.1 SCMの基本業務機能における情報機能とは
10.6.2 物流情報の種類
第11章原理・原則論
11.1 はじめに
11.2 IE の基本原則
11.2.1 5W1Hの原則
11.2.2 5Sの原則
11.2.3 QCの7つ道具
11.3 システム設計の基本思考
11.4 ロジスティクス基本機能の諸原則
11.4.1 荷役の原則
11.4.2 包装の原則
11.4.3 保管の基本原則
11.4.4 配送システムの原則と原型
11.4.5 3S1Lの原則と7R の原則
11.4.6 庫内ロケーションの基本
11.4.7 庫内補充の原則
11.4.8 配送センターチェックの基本
11.5 基本管理指標
11.6 改善推進の基本
11.7 提案書の作成・提案の原則
11.8 SCM戦略展開の基本
11.9 おわりに
第Ⅱ編SCMマネジメント編
第1 章最適立地ベースのグローバルSCMネットワークシステム
1.1 はじめに
1.2 北米における最適ハブネットワークの提案
1.2.1 提案プロセス概要
1.2.2 シミュレーションの諸条件とシミュレーション結果の総括
1.2.3 北米における階層構造ハブネットワークの分析と考察
1.2.4 北米圏のハブネットワークの階層構造分析
1.2.5 階層別最適ハブネットワークの提案
1.2.6 おわりに
1.3 東アジアにおける最適ハブネットワークの提案
1.3.1 シミュレーションの条件と結果
1.3.2 東アジアにおける階層構造ハブネットワークの分析と考察
1.3.3 階層別最適ハブネットワークの提案
1.4 EUにおける最適ハブネットワークの提案
1.4.1 はじめに
1.4.2 シミュレーションの条件と結果
1.4.3 EUにおける階層構造ハブネットワークの分析と考察
1.4.4 階層別最適ハブネットワークの提案
1.4.5 小括
1.5 三極経済圏最適ハブネットワークの提案
1.5.1 はじめに
1.5.2 シミュレーションの条件と結果
1.5.3 三極経済圏階層構造ハブネットワークの分析と考察
1.5.4 三極経済圏階層別最適ハブネットワークの提案
1.6 おわりに
第2 章SCM(供給連鎖管理)戦略の基本
2.1 はじめに
2.2 SCM戦略の文献調査
2.3 SCM戦略展開の基礎理論
2.4 経営戦略におけるSCM戦略の位置
2.5 SCM戦略の基本フレームワーク
2.5.1 SCM環境分析
2.5.2 SCM目標設定
2.5.3 SCM戦略の策定
2.6 おわりに
第3 章SCM戦略の展開
3.1 はじめに
3.2 SCM戦略展開の方法
3.2.1 戦略展開の基本と構造
3.2.2 戦略の基礎理論
3.3 SCM戦略の基本展開
3.3.1 SCM戦略展開の類型
3.3.2 チャネル戦略展開の基本モデル
3.3.3 チャネル拡大戦略の基本展開
3.4 おわりに
第4 章人事・組織管理
4.1 SCM 人事管理
4.2 SCM組織の基本
4.2.1 サプライチェーンマネジメントの目的とタスク
4.2.2 SCMの組織構造
4.2.3 SCMの組織構造の事例
4.3 SCM 教育の基本
4.3.1 サプライチェーンマネジメントで求められる知識・スキル,能力
4.3.2 SCM タスクを遂行する業務知識・スキル,能力
4.3.3 サプライチェーンマネジメントの教育方法と教育体系
4.4 人事・組織管理
第5 章コスト管理
5.1 SCM管理会計
5.2 政府ガイドライン『物流コスト算定活用マニュアル』
5.2.1 形態別分類
5.2.2 領域別分類
5.2.3 機能別分類
5.2.4 主体別分類
5.2.5 変固別分類
5.3 環境管理会計ガイドライン
5.3.1 環境配慮型設備投資
5.3.2 環境配慮型原価管理
5.3.3 環境配慮型業績評価
5.4 実践的管理会計
5.5 物流ABC準拠による物流コスト算定・効率化マニュアル
5.6 日日原価管理
第6 章業績評価測定と評価基準(KPI)
6.1 はじめに
6.2 評価方法について
6.2.1 財務分析ツール
6.2.2 評価方法の種類
6.3 チェックリスト方式
6.4 管理指標方式
6.4.1 生産性の発展段階
6.4.2 基本指標
6.4.3 基本構造
6.4.4 輸送管理指標
6.4.5 指標の限界
6.5 経営科学指標方式:多変量指標
6.5.1 全体プロセスのフロー
6.5.2 調査結果の要約
6.5.3 重回帰分析の結果
6.5.4 経営科学指標方式の留意点
第7 章アウトソーシング管理の空洞化
7.1 はじめに
7.2 管理の空洞化について
7.3 管理の空洞化の総合対策
7.3.1 連帯組織の強化
7.3.2 コア組織の確立
7.3.3 契約の見直し
7.3.4 改善教育制度の確立
7.3.5 現場作業の対策
7.3.6 コラボ体制の確立
7.4 おわりに
第8 章共同化推進・管理
8.1 はじめに
8.2 共同化の定義
8.3 共同化の発展経緯
8.3.1 日本における共同化の起源
8.3.2 日本における共同化の変遷
8.4 共同化の類型
8.4.1 日本における共同化の発展
8.5 共同化の推進と管理
8.6 おわりに
第9 章SCM作業管理
9.1 管理の基本
9.1.1 5S 活動
9.1.2 小集団活動
9.1.3 マニュアル整備と教育
9.2 現場監督者管理
9.2.1 スタッフマネジメント
9.2.2 KPI による現場管理
9.2.3 日々収支管理
9.3 非正規作業員管理
9.3.1 非正規作業員の確保
9.3.2 評価制度
9.3.3 キャリアパス制度
9.4 SCM 作業の管理
9.4.1 保管
9.4.2 荷役
9.4.3 輸送
9.4.4 包装
9.4.5 流通加工
9.5 今後の方向
第10章設備・機器管理
10.1 設備・機器管理の基本
10.1.1 スムースな業務の流れ
10.1.2 物と情報の密接な関係作り
10.1.3 物と情報を運ぶツール機能の確保
10.1.4 より効率の良い方策の模索
10.2 設備機器の維持・保全
10.2.1 機器の寿命
10.2.2 機器の維持・保全の体制と運用
10.3 設備機器の更新
10.3.1 更新計画
10.4 設備・機器の管理
10.4.1 設備・機器設置
10.4.2 機器使用での安全管理
10.4.3 作業員教育
第11章標準管理
11.1 標準の基本─目的
11.2 標準化の対象
11.2.1 機器の統一化─使用する機器の統一,情報交換ツール
11.2.2 作業の標準化─取扱品の分類・整理,処理の流れと手順
11.2.3 情報の標準化─運用・帳票,ツール統一,在庫・発注,異常措置
11.2.4 標準規格の採用─物流器具,搬送物,搬送機器
11.2.5 管理の標準化─人事,諸基準,保守
11.3 標準化の推進─作業員の教育,意思疎通と周知,必要機器の設置
11.3.1 標準化の推進と作業員への周知
11.3.2 必要ツールの設置─管理コンピュータ,指示表示機,管理体制
11.4 標準化の管理─諸基準(運用,保守),定期的見直,安全管理
11.4.1 運用の周知
11.4.2 定期的な見直しと修正
11.4.3 安全管理
第12章情報管理
12.1 情報管理の対象
12.1.1 情報共有の必要性
12.1.2 管理すべき情報
12.2 情報セキュリティ管理
12.2.1 情報資産とリスク
12.2.2 情報セキュリティ管理の基本
12.2.3 情報セキュリティ管理の標準化・国際化
12.3 情報のメンテナンス
12.3.1 情報の統合と標準化
12.3.2 マスター情報のメンテナンス
12.3.3 情報のバックアップと復旧
12.4 情報の管理
12.4.1 情報資源の管理
12.4.2 責任と利益の一致
第13章リバースチェーン管理
13.1 リバースチェーンマネジメントの領域
13.2 フォワードチェーンとリバースチェーンの関係
13.3 グリーンサプライチェーン
13.4 リバースチェーンマネジメントの体系
第14章セキュリティ管理
14.1 セキュリティの基本
14.1.1 情報セキュリティの定義とその3要素
14.1.2 情報セキュリティのその他の特性
14.2 情報セキュリティ関連法規(順守規定の基本)
14.2.1 サイバー犯罪を取り締まるための法律
14.2.2 情報の真正性と完全性を向上する法律
14.2.3 個人情報を保護する法律
14.2.4 迷惑メールを規制する法律
14.2.5 著作権などの知的財産を保護するための法律
14.3 セキュリティの対策
14.3.1 技術的セキュリティ対策
14.3.2 物理的セキュリティ対策
14.3.3 人的セキュリティ対策
14.3.4 組織的セキュリティ対策
14.4 セキュリティの管理
14.4.1 情報セキュリティガバナンス
14.4.2 情報セキュリティマネジメント
第15章SCMサステイナビリティ
15.1 持続可能性
15.2 代替燃料
15.3 3R
15.4 低環境負荷を志向した運行計画
第16章SCMと人間工学
16.1 人間工学の基本
16.1.1 人間工学とは
16.1.2 人間工学の分類法
16.2 人間工学の原理・原則
16.2.1 人間工学の基本的な考え方
16.2.2 人間工学の方法論
16.2.3 SCMにおける人間工学の活用
16.3 現状と展望
第17章システム分析と改善手法
17.1 はじめに
17.2 システム分析の基本
17.2.1 システム分析の基本
17.2.2 帰納法と演繹法
17.3 改善・改革のエンジニアリングの基本
17.3.1 基本フレームワークと推進ツール
17.3.2 基本分析プロセスと階層構造型ネットワーク分析の基本
17.3.3 分析の基本要因と10道具
17.4 SCMのシステムの基本
17.4.1 目的と対象範囲の明確化
17.4.2 あるべき姿の設計と確認
17.5 おわりに
第18章SCMとロボット
18.1 SCMとロボットの変遷
18.2 ロボットの現状
18.3 ロボットの展開
18.4 おわりに
第19章基本戦略展開の数値例
19.1 本章の目的
19.2 予測
19.2.1 予測の種類とその適用範囲
19.2.2 予測のケース;回帰モデルの計算の仕方,見方
19.3 地図情報の応用
19.3.1 ヒュベニ公式
19.3.2 ヒュベニ公式の応用例
19.4 立地選定
19.4.1 前提条件の整理
19.4.2 立地選定手法
19.4.3 立地選定シミュレーションの基本およびケーススタディ
19.5 在庫管理手法と応用
19.5.1 発注方式の決定
19.5.2 在庫管理手法
19.5.3 ハンドシミュレーションの例
19.6 輸送配送の手法と応用
19.6.1 発着地間の輸送量配分
19.6.2 輸送網における輸送量配分
19.6.3 VSP(Vehicle Scheduling Program)による目次xxii配送シミュレーションの問題
第20章SCM展開のチェックリスト
20.1 はじめに
20.2 戦略関係総合チェックリスト
20.2.1 経営戦略概括(フレームワーク)チェックリスト
20.2.2 SCM戦略チェックリスト
20.2.3 SCM戦略チェックリスト
20.3 配送センター総合チェックリスト
20.3.1 契約チェックリスト
20.3.2 センター用チェックリスト
20.3.3 3PL用自己評価リスト─ Randhal
20.4 提案書チェックリスト
20.5 海外ロジスティクス特性リスト
第Ⅲ編基本科学編
第1 章IE の基本
1.1 科学的管理法の基本
1.1.1 IE(Industrial Engineering)
1.1.2 IE の手法体系
1.2 工程分析の基本
1.2.1 工程分析とは
1.3 経路分析の基本
1.3.1 経路分析の意義
1.3.2 経路分析の目的
1.3.3 経路分析の方法
1.3.4 機械配置の特徴
1.4 流れ分析の基本
1.4.1 流れ分析とは
1.4.2 流れ線図の作成方法の要点
1.4.3 流れ線図による改善の着眼点
1.4.4 レイアウト
1.5 標準時間の基本
1.5.1 必要な時間と無駄な時間
1.5.2 時間分析手法
1.5.3 標準時間の設定
1.6 稼働分析の基本
1.6.1 稼働分析の目的
1.6.2 段取り改善
1.7 IE による改善
1.7.1 問題発見
1.7.2 現状分析
1.7.3 改善立案
1.7.4 改善案の実施
1.7.5 評価
第2 章VE/VAの基本
2.1 VEとは
2.1.1 VEの狙い
2.1.2 VEで扱う価値概念
2.1.3 VEの範囲
2.1.4 VEを必要とする背景
2.2 VEの見方と考え方
2.2.1 VEによる改善手法の特色
2.2.2 機能とは何か
2.2.3 機能的な物の見方
2.2.4 機能の定義
2.3 VEによる改善
2.3.1 VEの7つのJOB PLAN
2.3.2 VEの組織的な進め方
2.3.3 VEの進め方
第3 章TQCの基本
3.1 TQCとは
3.1.1 品質管理(TQC:Total Quality Control)の生まれるまで(歴史)
3.1.2 わが国の品質管理
3.1.3 日本的TQC
3.1.4 品質保証
3.2 TQC の基本的な考え方
3.2.1 消費者指向:生産者指向でなく,相手の立場を考える
3.2.2 次工程はお客様:セクショナリズムを打ち破る
3.2.3 すべての仕事に品質がある:仕事の質の管理
3.2.4 「狙いの品質」と「できばえの品質」
3.2.5 QC的な仕事の進め方
3.3 問題解決の基本
3.3.1 問題とは何か
3.3.2 問題のタイプ
3.3.3 問題解決とは
3.3.4 問題解決の効果的な進め方
3.4 QC 7 つ道具
3.4.1 QC 7 つ道具とは
3.4.2 QC 手法の進め方
3.4.3 QC 7 つ道具
3.5 新QC 7 つ道具
3.5.1 親和図法
3.5.2 連関図法
3.5.3 系統図法
3.5.4 マトリックス図法
3.5.5 アローダイアグラム法
3.5.6 マトリックスデータ解析法
3.5.7 PDPC 法
3.6 QC サークル
3.6.1 QC サークルとは
3.6.2 方針管理とQC サークル活動
3.6.3 QC サークル活動の推進体制
3.6.4 サークル活動の進め方
第4 章TPM の基本
4.1 TPMとは
4.1.1 設備管理とは
4.1.2 TPMの狙い
4.2 TPMの定義と基本理念
4.2.1 TPMの定義
4.2.2 TPMの基本理念
4.3 TPMの展開
4.3.1 全社的体質改善活動とTPMの関係
4.3.2 設備生産効率の測定と故障ゼロ対策
4.3.3 TPM展開プログラムの概要
4.4 21世紀の工場とTPM展開
4.5 TPM活動の成果測定・評価
4.5.1 TPM成果達成活動の意味
4.5.2 TPM活動の成果測定・評価
第5 章管理図の基本
5.1 管理図とは
5.2 管理図の分類
5.2.1 管理図の分類
5.3 管理図の表し方と使い方
5.3.1 管理図の表し方
5.3.2 管理図の使い方
5.4 管理図の種類
5.4.1 管理図の決め方
5.4.2 X-R管理図
5.4.3 Me-R管理図
5.4.4 X-R・管理図
5.4.5 np管理図
5.4.6 p管理図
5.4.7 c管理図
5.4.8 u管理図
5.5 損益分岐点分析
5.5.1 損益分岐点分析とは
5.5.2 個別費用法
5.5.3 総費用法
5.5.4 スキャターグラフによる方法
5.5.5 最小二乗法による方法
第6 章信頼性管理
6.1 信頼性
6.2 信頼性の評価尺度
6.3 修理系と非修理系の問題
6.3.1 修理系の問題
6.3.2 非修理系アイテムの問題
6.3.3 修理系と非修理系の問題のまとめ
6.4 故障率関数の理論式からの導入
6.4.1 故障率の定義
6.5 寿命分布関数
6.6 信頼度予測
6.6.1 システムの信頼度
6.7 保全,保守業務
6.8 FMEAとFTA
6.8.1 FMEA(FailureMode and Effects Analysis)
6.8.2 FTA
第7 章プロジェクト管理
7.1 プロジェクト管理の基本
7.1.1 プロジェクトとプロジェクトマネジメント
7.1.2 フェーズとプロセス
7.1.3 プロジェクトマネジメントの知識エリア
7.2 PERT
7.2.1 アローダイアグラム
7.2.2 最早時刻と最遅時刻の計算
7.2.3 余裕時間とクリティカルパス
7.2.4 PERT手法の応用と三点見積法
7.3 プロジェクトの評価方法
7.3.1 事前評価,中間評価と事後評価
7.3.2 プロジェクト評価方法
第8 章SCMと多変量解析
8.1 回帰分析
8.1.1 回帰分析の概要
8.1.2 回帰分析の有効性と信頼性
8.1.3 回帰分析の活用方法
8.2 主成分分析
8.2.1 主成分分析手法
8.2.2 主成分分析結果の読み方
8.2.3 主成分分析の活用方法と留意点
8.3 クラスター分析
8.3.1 クラスター分析と類似度
8.3.2 階層的クラスター手法
8.3.3 非階層的クラスター分析とk-means 法
8.3.4 クラスター分析の活用方法
8.4 因子分析
8.4.1 因子分析の考え方と手順
8.4.2 因子の解釈と寄与率
8.4.3 因子得点と因子分析結果の活用
8.5 判別分析
8.5.1 判別分析手法の概要
8.5.2 判別関数の導出方法
8.5.3 判別モデルの評価
8.6 数量化理論Ⅰ類,Ⅱ類,Ⅲ類,Ⅳ類
8.6.1 数量化理論とダミー変換
8.6.2 数量化理論I 類
8.6.3 数量化理論活用の注意点
第9 章予測方法
9.1 指数平滑
9.1.1 予測方法
9.1.2 指数平滑法の基本
9.1.3 指数平滑法の活用方法
9.2 Box-Jenkins法
9.2.1 時系列とその特性
9.2.2 時系列の基本モデル
9.2.3 Box-Jenkinsの方法
9.3 その他時系列モデル
9.3.1 多変量時系列モデル
9.3.2 分散不均一モデル
9.3.3 時系列の状態空間モデルとカルマンフィルタ
第10章地図のデータ利用
10.1 はじめに
10.2 地球楕円体における2点間直線距離の導出
10.3 2 地点間直線距離の導出方法による誤差
10.4 おわりに
第11章最適立地手法
11.1 最適立地問題とは
11.2 最適立地問題の分類
11.3 代表的な最適立地モデル
11.3.1 p-median 問題
11.3.2 p-center問題
11.3.3 単純施設配置問題
11.3.4 二次割当問題(quadratic assignment problem)
11.3.5 容量制約付き施設配置問題
11.3.6 ハブ施設配置問題(hub location problem)
11.4 施設配置問題に対する最適解法
第12章在庫管理手法
12.1 在庫管理の基本
12.1.1 在庫の機能と役割
12.1.2 在庫の把握と管理
12.1.3 現品管理とABC分析
12.2 在庫の基本理論
12.2.1 サービス率の理論
12.2.2 その他の指標と理論
12.3 発注システム
12.3.1 定期発注方式
12.3.2 定量発注方式
12.3.3 ダブルビン方式
12.3.4 その他の方式と事例
12.4 多段階在庫管理
12.5 在庫補充方式
第13章配送センター設計手法
13.1 配送センターシステム
13.1.1 配送センター(distribution center)
13.1.2 配送センター特性
13.1.3 配送センター特性のキーファクター
13.1.4 生産システムと配送センターシステムの使命の違い
13.1.5 生産システムと配送センターシステムの特性の違い
13.1.6 入出荷システム
13.1.7 オーダピッキング・システム
13.1.8 配送センターの基本モジュール
13.1.9 通過型の配送センターシステム
13.2 EIQ配送センターシステム設計法
13.2.1 配送センターシステム設計法
13.2.2 EIQ 配送センターシステム設計法
13.2.3 EIQ 法よる配送センターシステム設計の考え方
13.2.4 EIQ 分析
13.2.5 EIQ 法の活用
13.2.6 配送センターシステム設計の進め方
13.2.7 システム設計の理念・考え方
13.2.8 システム設計の使命の確認
13.2.9 カストマーサービス・レベル
13.2.10 配送センターを設計するために必要な条件は大変多い
13.2.11 物流システムを認識する
13.2.12 配送センター企業の業務内容を把握する
13.2.13 配送センターシステムの構成
13.2.14 ソフトとハード
12.2.15 WMS(WarehousingManage System)
13.2.16 運用ソフト(EIQ-WMS)
13.2.17 受注データ(EIQ データ)
13.3 基本物流機器
13.3.1 配送センターの基本物流機器
13.3.2 物流機器選定の基本
13.3.3 数量で脱皮する保管機器
13.3.4 物流機器選定基準
13.3.5 その他の保管機器
13.3.6 荷役運搬機器
13.3.7 配送センターの自動化
13.3.8 機械的自動化
13.3.9 情報的自動化
13.3.10 ABC(Activity Based Costing)
13.4 配送センターシステム事例
第14章最適輸・配送手法
14.1 最適輸送
14.1.1 輸送・配送
14.1.2 線形輸送問題
14.1.3 線形計画法
14.1.4 非線形輸送問題
14.1.5 分枝限定法のソフトウェア
14.1.6 コンピュータによる数値計算
14.2 最適配送
14.2.1 配送
14.2.2 配送巡回路作成のための技法
14.3 巡回セールスマン問題
第15章実験計画法
15.1 実験計画法の基礎理論
15.1.1 実験計画法とは
15.1.2 1 因子実験(1元配置)
15.1.3 2 因子実験(2元配置)
15.1.4 分割実験
15.1.5 直交配列実験
15.2 SCM への応用
15.3 期待効果
第16章関連手法
16.1 はじめに
16.2 遺伝的アルゴリズムの基本
16.2.1 GAの原理
16.2.2 GAの仕組み
16.2.3 GAの応用例
16.3 ファジィの基本
16.3.1 ファジィの原理と基礎
16.3.2 ファジィ推論
16.3.3 ファジィ制御
16.4 階層化意思決定法の基本
16.4.1 AHPの手順
16.4.2 AHP における計算
16.4.3 AHPの応用例
16.5 ISMの基本
16.5.1 ISM法の手順
16.5.2 ISM法の応用例
16.6 焼きなまし法の基本
16.6.1 SAのアルゴリズム
16.6.2 SAの長所および短所
16.7 タブサーチの基本
16.7.1 タブサーチのアルゴリズム
第17章アプリケーション・ソフトウェア一覧表
17.1 WMS製品一覧
17.2 BOM製品一覧
17.3 TMSの製品一覧
17.4 ERP
17.5 多変量解析
第Ⅳ編ケース研究編
第1章JIT方式
1.1 システムの現状
1.2 システムの特徴
1.3 システムの今後
第2章 VMI 方式
2.1 システムの現状
2.2 システムの特徴
2.3 システムの今後
第3章 家電業界
3.1 システムの現状
3.2 システムの特徴
3.3 システムの今後
第4章 ネット通販業
4.1 システムの現状
4.2 システムの特徴
4.3 システムの今後
第5章 部品業界
5.1 システムの現状
5.2 システムの特徴
5.3 システムの今後
第6章 食品加工業界
6.1 システムの現状
6.2 システムの課題
6.3 システムの今後
第7章 医薬品業界
7.1 システムの現状
7.2 システムの特徴
7.3 システムの今後
第8章 小売業のSCM
8.1 システムの現状
8.2 システムの特徴
8.3 システムの今後
第9章 卸売業のSCM
9.1 システムの現状
9.2 システムの特徴
9.3 システムの課題
第10章 百貨店アパレル業界
10.1 システムの現状:百貨店アパレル商品納品経路
10.2 システムの特徴:百貨店におけるIT 化の取組み
10.3 システムの課題
第11章 物流不動産業界
11.1 システムの現状
11.2 システムの特徴
11.3 システムの課題
第12章 半導体業界
12.1 システムの現状
12.2 システムの特徴
12.3 システムの課題
第13章 農業流通関係穀物業界
13.1 システムの現状:流通経路
13.2 システムの特徴:穀物メジャー
13.3 システムの課題


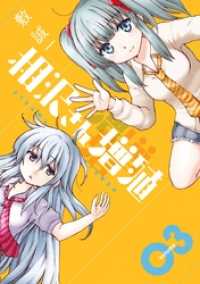
![0嬢の物語 ヘアー無修正完全版[5巻セットDVD]](../images/goods/ar/web/vimgdata/4560292/4560292372644.jpg)




