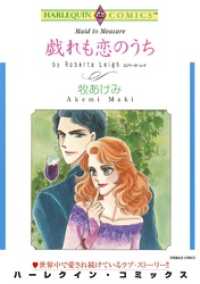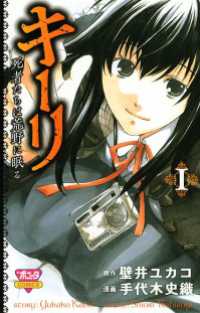内容説明
パンデミックで窮状が白日の下に晒された日本の大学.襲いかかるオンライン化の奔流,不可避の人口減,疲弊する教員,逼迫する資金,低下する国際評価――.存続の危機の根本原因はどこにあるのか.本来の大学を追究し続けてきた著者が,「時間」をキー概念に提案する再生のための戦略とは.ロングセラー『大学とは何か』待望の姉妹編.
目次
序 章 大学の第二の死とは何か コロナ・パンデミックのなかで┴第一章 大学はもう疲れ果てている――疲弊の根源を遡る┴第二章 どれほどボタンの掛け違いを重ねてきたのか――歴史のなかに埋め込まれていた現在┴第三章 キャンパスは本当に必要なのか――オンライン化の先へ オンライン化の津波が大学を襲う/大教室授業のオンライン化は本当に可能か/オープン・エデュケーションにおける日本の遅滞/オープン・エデュケーションとしてのOCW/大規模オンデマンド配信型授業としてのMOOC/ミネルバ大学の挑戦――キャンパスなき全寮制大学/オンラインが生む時間と空間の再編/オンラインとともに町へ出よう┴第四章 九月入学は危機打開の切り札か――グローバル化の先へ┴第五章 日本の大学はなぜこれほど均質なのか――少子高齢化の先へ┴オンライン化,グローバル化,そして少子高齢化/マルチステージ化する長寿化社会の人生/それでも大学は期待されていない――通過儀礼でしかない日本の大学/人生で三回大学に入学する――トランスミッションとしての大学/「通信制大学」という回路/「高専」という回路/金沢工業大学・国際高専の挑戦/ダイバーシティとコミュニティの両立に向けて――大学の本分┴第六章 大学という主体は存在するのか――自由な時間という稀少資源┴大学とは誰か――カレッジ,ファカルティ,ユニバーシティ/若手研究者たちの絶望と疲弊/「学長のリーダーシップ」が孕む逆説/ホモ・アカデミクスたちの大学人生/大学における教授の四類型/学長のリーダーシップと構造改革派/時間という稀少資源と大学構造改革/時間の劣化を反転させる大学の横断的構造化┴終 章 ポストコロナ時代の大学とは何か――封鎖と接触の世界史のなかで┴反復するパンデミックとグローバル化/大学の場所はどこにあったのか/「自粛」の日本政治を支える「世間」/メディア環境化する「世間」/日本の「大学」はそもそも官吏養成機関?/オンラインは新たな銀河系?――何が大学を殺すのか┴あとがき┴主な引用・参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gonta19
trazom
ステビア
崩紫サロメ
Francis