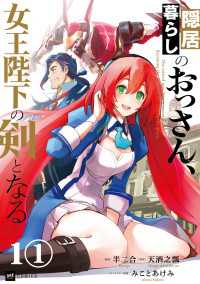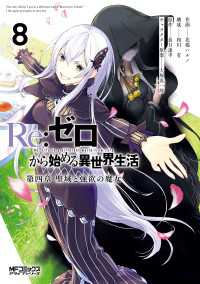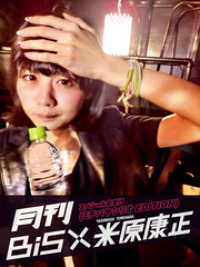内容説明
《世界が変わる哲学》がここにある!
現代フランスを代表する作家ウエルベックが、19世紀ドイツを代表する哲学者ショーペンハウアーの「元気が出る悲観主義」の精髄をみずから詳解。その思想の最奥に迫る!
***
本書『ショーペンハウアーとともに』は単なる注釈書ではない。一つの出会いの物語でもある。二十五から二十七歳のころ――つまり、一九八〇年代半ば――ミシェル・ウエルベックは、パリの市立図書館でほとんど偶然に『幸福について』を借りた。「当時、私はすでにボードレール、ドストエフスキー、ロートレアモン、ヴェルレーヌ、ほとんどすべてのロマン主義作家を読み終わっていたし、多くのSFも知っていた。聖書、パスカルの『パンセ』、クリフォード・D・シマックの『都市』、トーマス・マンの『魔の山』などは、もっと前に読んでいた。私は詩作に励んでもいた。すでに一度目の読書ではなく、再読の時期にいる気がしていた。少なくとも、文学発見の第一サイクルは終えたつもりでいたのだ。ところが、一瞬にしてすべてが崩れ去った」。衝撃は決定的だった。若者は、熱に浮かされたようにパリ中を駆け巡り、『意志と表象としての世界』を見つけ出す。それは、彼にとって「世界で最も重要な書物」となった。そして、この新たな読書はさらにすべてを「変えた」。
私の知る限りでは、いかなる哲学者もアルトゥール・ショーペンハウアーほどすぐさま心地よく元気づけてくれる読書を提供してくれる者はいない。「書く技術」の問題ではないし、この手のジャンルに見られる饒舌でもない。それは公衆に向って発言しようというほどの勇気をもつ者ならばあらかじめ同意書にサインすべき前提条件のようなものだ。『反時代的考察』第三篇は、ショーペンハウアーを否定する少し前に書かれたものだが、そこでニーチェは、この哲学者の深い誠実さ、廉直さ、正直さを賞賛している。ショーペンハウアーの声の調子、その一種の粗野な善良さについて名調子で語り、それを読めば読者は名文家や文体に凝る連中に対して嫌悪感を覚えるだろうと述べる。これこそ、広い意味での本書の目的である。
(本文より)
***
Arthur Schopenhauer
アルトゥール・ショーペンハウアー
(1788-1860)
19世紀を代表するドイツの哲学者。
ドイツ観念論に東洋哲学を取り入れ、実存主義・ニヒリズムの先駆者としても知られる。
主著は『意志と表象としての世界』(1819年)。彼の唯一で独自な思想は、若き日のニーチェを熱狂させたほか、ヴィトゲンシュタイン、フロイト、アインシュタイン、トルストイ、プルースト、ボルヘス、ワーグナーなど、後世の哲学者・作家・芸術家などに多大なる影響を与えた。
今日においては『余禄と補遺』(1851年)からの抜粋である『幸福について』『読書について』などのエッセイが広く一般に親しまれている。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
どんぐり
やいっち
Y2K☮
kazi