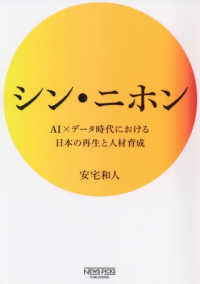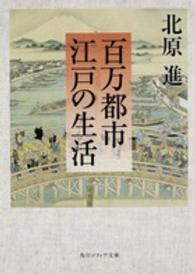内容説明
江戸時代に各地を治めていた藩主は、明治四年の廃藩置県によって国元から切り離されて強制的に東京住まいとなった。戊辰戦争で勝った大名も負けた大名も一緒くたに、領地は没収され、家臣は解散させられた。
最後の将軍、徳川慶喜は狩猟や写真に生きることで自分の政治力を封印した。
慶喜の兄、鳥取藩の池田慶徳は、誠実さと勤勉さで藩をまとめ、維新後も領民を気にかけ、国家に尽くし、飄然と世を去った。
そのほか地方行政に腕をふるった上総の一宮藩一万石の加納久宜、商社を経営しクリスチャンとなった三田藩九鬼義隆、箱館戦争まで参戦後二十年隠棲した最後の老中安藤政信など、十二名の元殿様の知られざる波乱に富んだ生き様を、人気歴史研究家の河合敦先生が紹介する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ウッチー
14
前作も面白かったが、本作もなかなか楽しめた。やはり、歴史上の大役の後は注目されにくいところなので、非常に面白く感じた。また、巻末の大名屋敷ガイドも面白かった。2022/04/27
バーバラ
13
前作同様読み応え十分。今回は登場人物が少し減ったので、その分1人分のボリュームがあり短編のドキュメンタリーを読んでいるような気分になった。本編も面白かったが今回も巻末のおまけが楽しい。登場する大名の江戸屋敷は現在何になっているかを示す一覧表で行き慣れた場所がかつてどこの藩の屋敷であったかわかる。同時に大都会でありながら東京の都心には緑が多いのも大名屋敷の跡地が多いからだと改めて頷ける。コロナですっかりご無沙汰だけど今度赤坂サカスでランチする時はかつてここの主だった広島藩主やご家来衆に思いを馳せてみよう。2022/02/18
bapaksejahtera
13
先般読んだ本の続編。そこで漏れていた徳川慶喜が冒頭採り上げられる。一時は東照神君家康公の再来と期待された彼は、結局趣味人として生きる外はなかったと本書は述べる。同時代、立場の異なる人物の人生を追うことでその時代への認識を深めることとなるのは前書と同じ。本書に述べる通り、人格者で名君の下では革命期の傑物は生じないことは事実に違いない。その中で小大名当主の立場を利して活躍した加納久宣の事績は読んでも心地よい。極めて軽いタッチで読み易い入門書的な良書とは思うが、他方膨大な人物の登場は混乱の元ともなるだろう。2021/08/24
とり
9
新たな殿様の話が出てくるたびに幕末まで時間を遡るので、何かタイムリープものの小説でも読んでいるような気分になってくる。それでいて、時間を遡るたびに違う視点で歴史を眺めることになるので、少しずつ話に厚みが出てくる。まさに歴史を紡いでいる。前所とあわせて、何となくこの時代の空気がわかったような気分になった。2023/02/27
路地裏のオヤジ
9
江戸から明治の激動の時代を生きたお殿様の生き様。各々だが旧領地の民を忘れずに尽くすお殿様たちは流石でした。2022/02/06
-

- 電子書籍
- やり直せるみたいなので、今度こそ憧れの…
-
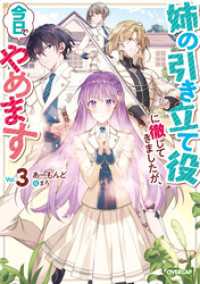
- 電子書籍
- 姉の引き立て役に徹してきましたが、今日…