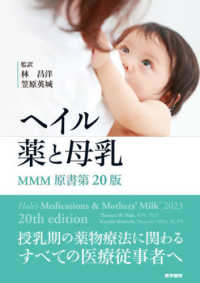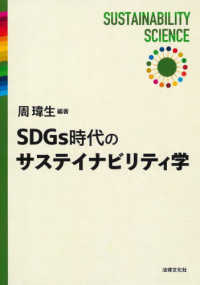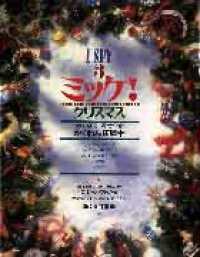内容説明
世界は「種」にあふれている。様々な種類の生物について、生物学者はこの種を基本に議論をする。種は非常に重要な生物学の単位なのだ。だが統一的な定義はない。なぜ定義がないのに生物学者たちは研究を進められるのか?その問いの射程は生物学の哲学にとどまらない。新しい自然主義的な科学哲学の姿を映し出す、エポックとなる1冊。
目次
はじめに
第一章 種問題とは何か
1・1 イントロダクション──種問題とは何か
1・2 形態学的(分類学的)種概念
1・3 生物学的種概念
1・4 系統学的種概念
1・5 多元主義
1・6 種の存在論的地位──種は個物か
1・7 本書の中心的な問いとその重要性
第二章 合意なきコミュニケーション
2・1 イントロダクション──なぜ種について合意がなくてもコミュニケーションができるのか
2・2 三つのケーススタディ
2・3 二論争物語──プライオリティの問題と同所的種分化の問題
2・4 通約不可能性問題とコミュニケーション不全
2・5 結論──定義がないのになぜコミュニケーションが成り立つのか
第三章 「よい種」とは何か
3・1 イントロダクション──種を語るときの二つのモード
3・2 二重過程説とは何か
3・3 生物学者は種についてどう語るのか
3・4 「よい種」とは何か
3・5 生物学者は「よい種」を用いてどのように考えるのか
3・6 種にかかわる推論には二つのプロセスが関与する
第四章 「投げ捨てられることもあるはしご」としての種
4・1 イントロダクション──個々の定義を超えた「種」の理解
4・2 一般種概念の構成要素を明らかにする
4・3 一般種概念と個々の種の定義の関係──精緻化
4・4 一般種概念はどういう認識論的役割を果たしているか
4・5 「投げ捨てられることもあるはしご」としての種
4・6 「一般種概念」から何が言えるのか
4・7 おわりに───一般種概念とは何か、どういう役割を果たしているのか
おわりに
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
志村真幸
-
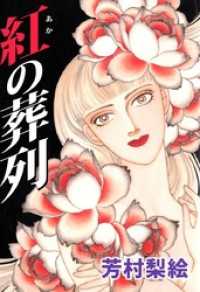
- 電子書籍
- 紅の葬列 まんがフリーク
-
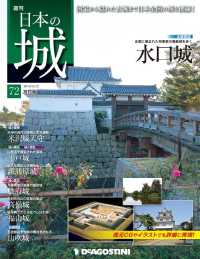
- 電子書籍
- 日本の城 改訂版 - 第72号