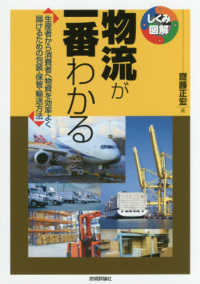内容説明
「禁止」ではなく「使えるようになるための」ルール~ICTモラルとスキルを同時に伸ばす
2018年から一人1台環境を実現しているさとえ学園小学校が、保護者とも連携して作り上げたすごいルール。それを教育ICTの導入から教材開発、研修プログラムの構築等で数多くの学校現場を知る著者が、専門的な視点に基づきつつ平易に解説。ルール導入前はiPadの遊びの機能に惹かれがちだった子ども達。GIGAスクール化を進めるとどの学校も直面する課題ですが、本書で取り上げたルールは自制心を育てるための好例です。
全国から訪れる見学者から寄せられた質問に答えるQ&Aは、きっとあなたの学校の「?」にも答えます。
【著者】
為田裕行
フューチャーインスティテュート株式会社 代表取締役
教育ICTリサーチ 主宰
■経歴
慶應義塾大学総合政策学部卒業後,大手学習塾企業へ就職。一斉指導、個別指導,合宿教育等の現場で鍛えられ,1999年フューチャーインスティテュートの設立に参画。東京都における教師への教材開発支援に関わり,現場への教育ICT導入の可能性を模索。幼稚園~大学まで全ての教壇に立つと共に,学校の先生向けの研修プログラム設計,授業計画コンサルテーション,教育テレビ番組や幼児向け教材,サービスなどの教育監修を行っている。
目次
第1 章 学校生活が一気に変わった一人1 台iPad
1 朝の会
2 授業
3 休み時間
4 帰りの会
第2 章 さとえ式レベルアップ型ルール
1 レベルごとにできることが決められている
2 レベルアップに必要な「スキル」と「モラル」
3 レベルアップの判断
4 レベルダウンの判断
5 レベルアップ型ルールが生み出された理由
第3 章 レベルアップ型ルールの運用のために
1 チェックシート
2 スキルチェックテスト
3 よい活用Book
4 デジタルツール
5 担当者の役割
第4 章 保護者との連携で環境をつくる
1 デジタルで共有する
2 リアルに集える会
第5 章 これからの学校のスタイル
1 リモート授業
2 宿題
3 児童会活動
4 保健室から見たiPad と子どもたち
第6 章 レベルアップ型ルールを支える考え方
1 レベルアップ型ルールの基本理念
2 先生方の思い
Q&A こんな時どうしてますか?
終章 その先へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
U-Tchallenge
taku
kanameyui
-

- 電子書籍
- アラフォー・クライシス―「不遇の世代」…
-

- 和書
- たべもの芳名録 文春文庫