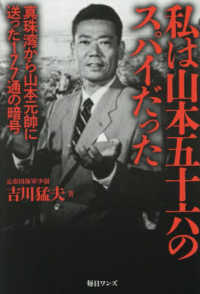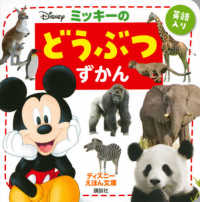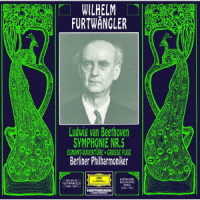- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
環境社会学とはどのような学問なのか。近年、「持続可能な未来」が国際社会の最重要課題となるなかで、この学問はいったいどんな道筋を私たちに示してくれるのか。本書では、日本における環境社会学の立ち上げに大きく寄与し、その研究を長年牽引してきた第一人者が、みずからの研究史を振り返りつつ、この学問がもつ魅力とその可能性を浮き彫りにしていく。他人事でなく自分事として環境問題を受け止め、よりよい未来を模索しようとするすべての人のための導きの書。
目次
はじめに
第一章 社会学との出会い
湯川秀樹の伝記
祖父の近代──名前の由来
一九五四年
「大きな楕円に」──父と母
県境の雪深い町で
『知的生産の技術』を読む
駒場での出会い
社会学こそ学問の王様だ
恩師吉田民人との出会い
高橋徹と富永健一・小室直樹
転機──「五月祭」のお芝居
多士済々
舩橋晴俊・梶田孝道との出会い
〈コンフリクトと社会変動〉──生涯のモティーフ
「社会学それ自体の内包的希薄化」──富永健一の憂い
第二章 新幹線公害問題の衝撃
高速鉄道の世界的再評価
「日本列島の主軸」──交通・通信ネットワーク
新幹線の光と影
「生みの親」に責任はないのか──新幹線設計思想の致命的な欠落
「社会問題研究会」
原子力船むつ
東北・上越新幹線建設反対運動
革新自治体ブーム──首都圏内の地域間格差と生活防衛
条件闘争への転換
名古屋新幹線公害
高速文明 対「静かさ」の価値
環境問題研究の原点
自ら原告団長に──人生の点と点
新幹線公害問題のその後
リニア中央新幹線の環境問題
国内的評価に自足
第三章 社会運動をどう説明するのか
一九八四年──東北大学へ
文学部へ
資源動員論との出会い
公民権運動はなぜ成功したのか
バスボイコット運動の画期的勝利
共通の利益の自覚は人々を行動に駆り立てるのか
選択的誘因
気候ストライキはなぜ成功したのか──社会運動分析の三角形
フレーミング
未来のための金曜行動
資源動員
政治的機会構造
社会変革分析の三角形へ
NPO法の制定過程──社会変革過程を説明する
第四章 原発閉鎖とアメリカ市民社会
内向きの日本の社会学
在外研究──カリフォルニア大学バークレー校へ
井の中の蛙
脱原発の「金鉱発見!」
英語力不足を補うには
アポ取りの苦労
原発閉鎖と市民の力
一九八九年の分水嶺
何を守るのか
政治的対立の解消・社会的合意の基礎
サクラメント電力公社の再生──二一世紀の電気事業者のモデル
「省電力は発電」
世界最初のグリーン電力制度
サクラメント電力公社の現在
北海道グリーンファンドと市民風車の誕生
第五章 コンセントの向こう側──青森県六ヶ所村
コンセントのもう一つの向こう側
トイレに失礼な「トイレなきマンション」
六ヶ所村と放射性廃棄物
六ヶ所村との出会い
「巨大開発」から放射性廃棄物半島へ
構造的緊張の連鎖的転移
周回遅れのランナー
新青森駅の失敗
大間町・むつ市関根浜・東通村
再処理をめぐるジレンマ
核燃料サイクルはなぜ止まらないのか
青森県当局との信頼維持のための再処理
核武装の潜在能力を担保する──再処理の隠れた動機
仮に止めたとしたら
何が真の国益なのか
太平洋戦争末期の旧日本軍のようだ
六ヶ所村の地域づくり──「普通」の東北の農村に
第六章 環境社会学者の自覚
環境社会学会の発足
環境研究の「第一の波」と「第二の波」
「環境社会学の母」飯島伸子
宇井純と飯島伸子
被害構造論の先駆性
日本の環境社会学の独自性
相次ぐ出版企画
社会と環境──システムとその外側
ローカル・コモンズ
人新世──新しい地質学的時代
環境社会学第一世代と第二世代
環境社会学と社会学
アイデンティティ・クライシスの危険
アイデンティティのありか──対象・方法・価値関心
〈ダウンストリームの社会学〉としての環境社会学
廃棄物問題が提起するもの
ダウンストリームとアップストリームの循環・統合を求めて
第七章 持続可能な未来をつくる
二〇二〇年──持続可能な未来への分岐点
「裸の王様」からの転換
「持続可能性」という価値
レジリエンスという第四の次元
SDGsの意義
研究目標・課題としての持続可能性
研究と運動のはざまで
日本の市民社会の限界
コラボレーション
市民社会と対話する〈公共社会学〉
社会学の特質
二〇二〇年生まれの子どもたち
気候危機とコロナ禍の類似性
若者たちへ
一〇〇〇年後の滝桜
あとがき
参考文献
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
寝落ち6段
ネムル
まあい
Mealla0v0
-
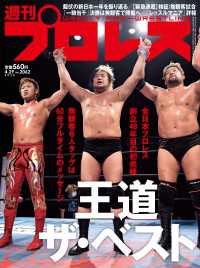
- 電子書籍
- 週刊プロレス 2020年 4/29号 …