- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
高層ビルは新宿に密集する、北海道と本州は生息する動物が異なる、高尾山の植物種数はフィンランドより多い……身近に潜むこれらの謎を解くキーワード、それは「氷河」! 50カ国以上を調査で飛び回ってきた著者が、山を滑り落ち、砂漠を歩き抜き、森をさまよったからこそ見えてきた地球の不思議の数々。身の回りの疑問を出発点に自然のダイナミズムに触れる、あなたも街に、山に、川に、世界に出たくなる、地理学からの招待状。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
79
植生が専門の大学の先生が一般教養をベースに書き下ろしたもの。したがって高校の(現)地理探究レベルの内容で、まさに入門編。問をたてて解説するスタイルなので、興味を持ったところから読むこともできる。登山経験や海外での体験が随所にちりばめられており、写真も豊富(原著はもっと豊富だったそうだ)。p.203の写真には思わず吹き出してしまった。エピソードも結構下世話な話も含まれており楽しく、すいすいと読める。地理好きの高校生にはお勧めだ。原著が10年前なので、アフリカの氷河はもはや風前の灯火かな。人文編も読みたい。2025/01/20
ひろし
53
真鍋さんのノーベル賞受賞で気候変動が話題になっている。ちょうど関連分野のこの本を読んでいてタイムリーだと思った。気象、地形、植生など生活に関わってくる話が端的にまとめられていてわかりやすい。個人的体験があちこち出てくるのがこういう本では珍しい。山手線の話はちょっと物悲しいけど。ナミブ砂漠も気になる。2021/10/06
Book & Travel
41
昔から割りと好きだった地理関連の本を少し読みたくなり手に取った一冊。東京の各駅(名古屋、大阪も)の高低差を沖積平野、洪積台地との関係で説明される冒頭から引き込まれる。地形、気候、植生と土壌という切り口で説明される地理学の基本は、教科書的な所も多いが、研究で世界中を廻ってきた著者の体験談や蘊蓄話が随所に挟まれ、これが読みやすく面白かった。欧州と日本の植生の違いと江戸期のシーボルトの来日を繋げる所など、地理と歴史を知ることで世界の様々なことが面白くなることを改めて実感。刺激を受ける楽しい読書になった。2023/01/31
もえたく
23
新宿に高層ビルが集まるのも、盗撮事件がよく発生する渋谷や中目黒駅の階段が長いのも「氷河」のせい、など自然が日本や世界の歴史と密接に絡んできたことが楽しみながら学べます。理論だけではなく、実際に世界50カ国以上調査した著者の体験談も語られていて興味深かった。続編の『人間の営みがわかる地理学入門』も読んでみたくなりました。2022/06/05
チャーリブ
23
2022年度からは高校社会科で地理も必修(地理総合)となった。いいことである。地震や水害など自然災害の多い国土に暮らす日本人にとって地理学リテラシーは必要不可欠だ。本書は「自然地理学」の一般向けの解説書であるが、様々な疑問に答える形で基本的知識が学べるようになっている。たとえば、「なぜ新宿に高層ビルが集まっているのか?」(沖積平野と洪積台地)「シーボルトがオランダ人になりすまして日本で見たかった木は?」(多様な植物種の日本と単調な植物種のヨーロッパ)など。植村直己氏のうんちの話には私もうなってしまった。○2021/10/19
-
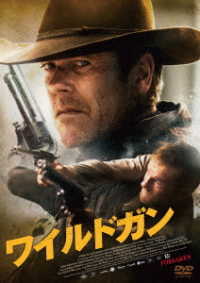
- DVD
- ワイルドガン




