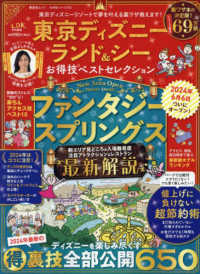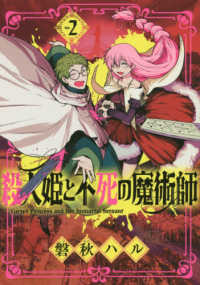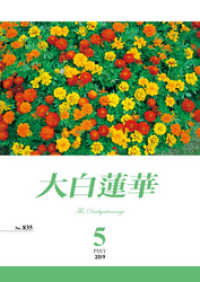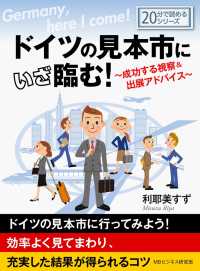内容説明
ギリシア神話や聖書などには古代世界を襲った様々な災厄が記されている。一方、「古史古伝」「超古代史」などと呼ばれる日本の史書には、古代の日本列島およびその周辺の国々が天災や疫病に見舞われたことが記されている。それらの物語に災禍のイメージが刻印されている意味とは何か? そこから何が学べるか?──パンデミックに襲われた2020年を総括しながら、考察する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
59
聖書や古史古伝を疫病災害といった観点から読み解いた一冊。古史古伝は兎も角聖書や神話まで含めると範囲が広すぎて、ちょっと散らかっているようにも思える。古史古伝も内容紹介部分が多かったかな、こういうのは何度紹介されても楽しめるけど。竹内文章とかは内容が荒唐無稽すぎるせいか、あまり災禍と結びつけられていないが、本書の真の見どころは『富士宮下文書』と『東日流外三郡誌』を最新の地質学等の観点からその真偽を見破っている点か。ただ著者の古史古伝に関する本を愛読する身としては、今までと重なる部分も多かったように感じた。2023/05/04
へくとぱすかる
50
「古史古伝」等、超古代史に登場する災害・病気の蔓延の記録が、なぜ書かれたのか、何から影響を受けたのかを掘り下げると意外な側面が見えてくる。偽書がわざわざ書かれるには、大人の理由があり、オカルト本で超古代へのロマンを膨らませた、かつての少年たちの思いとは、まるで遠いところにあったと言うべきだろう。後世の科学的検証によって、史実性が否定され、むしろ近代の思想的事情の資料と化すとは、偽書の作者には思いもよらなかったはず。偽書同士の影響関係や「竹内文書」と富山県の水害など、新しい情報を興味深く読んだ。2020/12/12
イワハシ
4
ちょっとテーマが広すぎて、この分量では収まらずにとっ散らかってしまった印象。2022/09/02
てっき
2
ツイで流れてきたので買った本。内容はムーなどに出てきそうな超古代に関する各種伝承(?)を片っ端からぶった切るもので、筆者が反「江戸しぐさ」の急先鋒と知って非常に小気味良い気持ちになれた。 これだけ多くの言説を見ると正直、よくもまぁこんなに人間の想像力というやつは偉大なものだと思うものだが、あとがきの「予言とは、未来をすでに確定したものとして語る行為であり、つまりは、予言の対象とした未来の事柄を、予言された時点という過去に繰り込む行為である」という一文には、未来を信じる筆者の思いを感じて少々目頭が熱くなった2020/12/30
まるめろ
1
一つ一つの章は読みやすくわかりやすいので面白く読めたが、一冊の本としては纏まりがなく、結局何が目的なのかわからないまま読み終わってしまった。2024/05/09