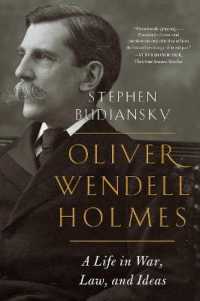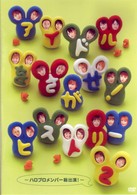- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「水戸黄門」徳川光圀が天皇に理想国家の具現を見た中国人儒者・朱舜水を師と仰ぎ、尊皇思想が生まれる。幕末、挙国一致の攘夷を説く水戸の過激派・会沢正志斎の禁書『新論』が志士たちを感化し、倒幕への熱病が始まった。そして、三島由紀夫の自決も「天狗党の乱」に端を発していた。日本のナショナリズムの源流をすべて解き明かす!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぐうぐう
36
尊皇攘夷という思想の起点である水戸学の四百年を検証する。徳川光圀の、兄を差し置き藩主になった負い目が尊皇という感情とマッチしたことで始まった水戸学は、そもそもが屈折していた学問とも言える。例えば南北朝時代という屈折をどう捉えるか、どこに道理を求め、筋を通すか、義にこだわる光圀が考えに考え込むにつれ、屈折はやはりエスカレートするのだ。しかし屈折した感情は、それを正当化しようとするあまり、思い込みを助長させる。正しさ(という思い込み)が何にも勝るのだ。(つづく)2021/11/11
いーたん
25
天狗党について、恥ずかしながら大河ドラマで知る。たまたまその頃、北陸に出かけた時、天狗党の足跡についても知る。そして、この本を図書館で見つけて読んでみた。水戸学の成立ちと水戸藩の位置付けもさることながら、反射炉や三島由紀夫のご先祖などが絡まりながら幕末の混沌とした様子、水戸藩のやるせなさを著者の熱い語り口でぐいぐい読めていきました。武田耕雲斎についての言及ももちろんあるものの、福井で散った天狗党の終焉についてはかなりあっさりふれられただけでした。そこ、興味あったのですが笑。2021/07/18
鯖
20
水戸支藩の藩主松平頼徳は天狗党の乱を鎮めるため水戸に派遣されたが、攘夷の志を果たせず、幕府朝廷水戸藩全てに裏切られ、責を取る形で討伐軍、諸政党に散々に野次られる衆人環視の中、介錯なしで切腹させられた。彼は三島由紀夫の曾祖叔父にあたる。そして三島由紀夫も市谷駐屯地で同じような最期を遂げる。もうこれだけで物語として完璧だし、読み物としてとても面白いんだけど、選書や新書ではないんだよねこの本。文末大量に記された参考文献のような水戸学についての本が読みたかったので、求めてたものとは違う。ただ物語として完璧。2021/08/15
風に吹かれて
18
滅亡した明王朝再興に尽力して果たせなかった儒学者朱舜水を招いて(1665年)水戸学の基礎を築いた徳川光圀。「尊王」の思想。 カツオ漁をしていた水戸の漁師は遠くの沖に異国船を見かけるようになった(1817年)。1823年ころから沖合の遠くまで行かないとカツオが獲れなくなり、遠沖へ。そしてクジラ漁をしているイギリス人と物々交換などして交流するようになる。藩や幕府はこれを問題視。「攘夷」思想が高まっていく。黒船来航(1853年)以前の話。そして、徳川慶喜による大政奉還は1862年。 →2024/10/28
軍縮地球市民shinshin
17
468頁もの大著なので読むのに相当時間がかかった。「尊皇攘夷」を信奉する水戸学の思想を扱った本であるが、いわゆる通史ではない。水戸学の創始者である徳川光圀の思想から幕末の天狗党の乱までを扱う。話がテレビドラマの「水戸黄門」から三島由紀夫まで扱っている。三島は天狗党蜂起に参加した武士の血を受け継いでいるらしい。自民党の政治家だった梶山静六はまさに天狗党の子孫であることは有名だが、落選中に先祖の石碑を建てていたとは知らなかった。戦前まではやたらと持ち上げられていたが、戦後は排除されてきた人たちだと思った。2025/06/14
-

- 洋書
- 大鱼 (B…