内容説明
選挙権年齢が18歳に引き下げられ,中高生に向けた主権者教育が求められています.本書は,若い世代が自らを選挙の当事者として考えるきっかけとなるように「有権者」を切り口に,選挙のしくみや意義をわかりやすく解説します.有権者には何が求められているのか,社会に参加するとはどのようなことなのかを学ぶための一冊です.
目次
はじめに┴第1章 有権者には4つのタイプがある┴1 市民には4つのタイプがある┴2 有権者にも4つのタイプがある┴3 それぞれのタイプを評価してみる┴4 あなたはどのタイプ?┴第2章 浮動票という言葉が使われた時代があった┴1 時代を振り返ってみる┴2 政党や政治は利益誘導を基本とする┴3 有権者の支持政党はあまり変化しなかった┴4 浮動票に変化が現れた┴第3章 無党派層が現代日本の政治を支配している┴1 有権者の支持政党は固定化しなくなった┴2 政党も多党化してきた┴3 受け皿が欲しい┴4 あなたも無党派ですか┴第4章 有権者をとりまく社会は流動化している┴1 教育は流動化している┴2 居住地の流動化が始まった┴3 社会は急激に個人化している┴4 「コンビニ文化」で地域は同質化している┴第5章 選挙の前に足元の社会を知る┴1 無知に気づく┴2 地域を学ぶ┴3 地域の課題に出会う┴4 投票のすすめ┴あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
コニコ@共楽
19
2015年に選挙権年齢が18歳に引き下げられて5年が経とうとしている。高校生で投票に行くこともできるようになったわけだ。選挙権は、歴史的に経済的に豊かでなくても、男性でなくても、白人でなくても、人々が勝ち得てきた権利。それが、なんで選挙に行かなければいけないと?という他人事に思う人もいる。今、政治の力が求められている中、誰が有権者であり、どんな有権者がいるのかを知る案内書。特に、第4章「有権者をとりまく社会は流動化している」は若い人にも知ってもらいたい。まずは認識から始めることが大切だと思う。2020/05/11
スイ
9
投票の重要性を述べてとにかく選挙に行くように、という本かと思ったら、良い意味で裏切られた。 投票者になる以前に、「市民としての市民」になることを意識すること。 投票は市民性の一つの表し方に過ぎない。 都知事選は市民運動の一つだ、という宇都宮健児さんの言葉も思い出す。 戦後の政治の流れもわかりやすく述べられていて良かった。2020/08/24
糸くず
3
タイトルは「有権者って誰?」であるが、内容は有権者の法律上の定義の変遷ではなく、浮動票から無党派層への変化と無党派層の拡大の原因を探ることで、望ましい有権者の在り方を考察したもの。よくも悪くも教科書的な「投票と政治参加のすすめ」で、政治に関心を持ち始めた人が初めて読む本としてのバランスはちょうどいいが、新鮮さや刺激には欠ける。とはいえ、無党派層拡大の原因を有権者の側から論じた第4章は興味深く読んだ。教育と居住地の流動化、社会の「個人化」、「コンビニ文化」による同質化など考えるきっかけとなる指摘は多い。2020/08/12
さらさら
0
まずは自分の「無知」を自覚すること。経験と学びを通じて市民としての自覚を持つことが、なによりも投票行動に繋がるのだと思った。これからも勉強を続けていきたいです。2025/11/01
-

- 電子書籍
- あなたのハニーは転生から帰ってきた【タ…
-
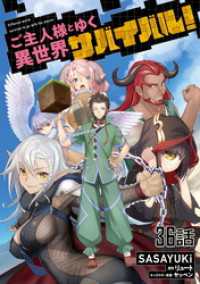
- 電子書籍
- ご主人様とゆく異世界サバイバル! 第3…
-
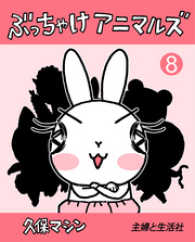
- 電子書籍
- ぶっちゃけアニマルズ8 週刊女性コミッ…
-

- 電子書籍
- REV SPEED 2017年1月号





