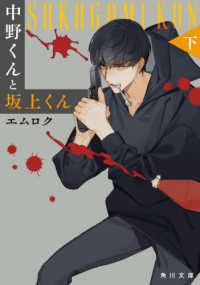内容説明
本書は,小学校以来の学びが水理学を学ぶ上でどのように役に立つかを実感できるよう配慮した教科書である。講義で教員が語る解説を話し言葉に近い形で記述し,問題解答のためのプログラムや水理現象の動画などをWEB上に用意した。
目次
1. 水理学を用いてなにができるのか
2. 力の釣合いと三つの保存則
2.1 水理学の観察方法
2.2 力の釣合い
2.3 三つの保存則とその関係性
2.3.1 質量の保存則
2.3.2 運動量の保存則(微視的に観察した場合)
2.3.3 運動量の保存則(巨視的に観察した場合)
2.3.4 力学的エネルギーの保存則(ベルヌイの定理)
演習問題
3. 動いていない水の力学:静水力学
3.1 静水圧の導出
3.2 平面に作用する水の圧力
3.2.1 平面に作用する圧力の導出
3.2.2 長方形斜面にかかる水の圧力(単純化した事例)
3.3 浮力
3.4 浮体の安定
3.4.1 浮体の種類
3.4.2 安定条件の評価
演習問題
引用・参考文献
4. 粘性のない水の運動:完全流体
4.1 ベクトル解析の基礎
4.2 流線・流跡線
4.3 非回転(渦なし)流れの基礎
4.4 流れ関数
4.5 複素速度ポテンシャル
4.5.1 水平方向に進む流れの場
4.5.2 湧出し,吸込み(1点から流出・流入する流れ)
4.5.3 渦糸
演習問題
引用・参考文献
5. パイプの中の水の流れ:管水路の水理
5.1 粘性流体
5.2 ナビエ・ストークスの方程式
5.3 層流
5.3.1 層流の流速分布①(クウェット流とポアズイユ流)
5.3.2 層流の流速分布②(ハーゲン・ポアズイユ流)
5.4 乱流
5.4.1 レイノルズの実験
5.4.2 レイノルズ数
5.5 レイノルズの方程式
5.6 レイノルズ応力
5.6.1 レイノルズ応力の物理的イメージ
5.6.2 レイノルズ応力の評価
5.7 乱流の流速分布
5.8 管路流れの基礎方程式
5.9 摩擦損失
5.9.1 層流の摩擦損失係数
5.9.2 乱流の摩擦損失係数
5.10 形状損失
5.10.1 断面変化による形状損失
5.10.2 流出・流入による損失
5.10.3 曲がりおよび屈折による損失
5.10.4 そのほかの形状損失
5.11 エネルギー線と動水勾配線
5.12 サイフォンの流れ
5.13 分岐・合流管路の流れ
演習問題
引用・参考文献
6. 川の中の水の運動:開水路の水理
6.1 開水路の流れ
6.1.1 管水路の流れと開水路の流れ
6.1.2 開水路の流れを表す物理量
6.1.3 開水路の流れの種類
6.2 等流
6.2.1 等流とは
6.2.2 平均流速公式
6.2.3 マニングの式を用いた計算
6.3 常流と射流
6.3.1 比エネルギー図における常流と射流
6.3.2 段差を越える流れ
6.3.3 流れの遷移
6.4 跳水と段波
6.4.1 跳水
6.4.2 段波
6.5 不等流の水面形
6.5.1 不等流を表す基礎方程式
6.5.2 限界勾配と緩勾配水路・急勾配水路
6.5.3 緩勾配水路・急勾配水路の水面形
6.5.4 水面形の具体例と描き方
6.6 不等流計算
6.6.1 不等流計算の基本的な考え方
6.6.2 常流・射流と不等流計算
6.7 非定常流
演習問題
引用・参考文献
7. 海の中の水の運動:波の水理
7.1 水面の波の運動
7.1.1 波の諸元
7.1.2 波の性質
7.1.3 波の分類
7.2 波の理論と変形
7.2.1 微小振幅波理論
7.2.2 波の波長と波速
7.2.3 水粒子の運動速度とその軌跡
7.2.4 波のエネルギーとその輸送
7.2.5 波の変形
7.3 ラディエーション応力
演習問題
引用・参考文献
8. 模型実験と相似則
8.1 水理模型実験
8.2 相似則
8.3 フルード相似則
8.4 レイノルズ相似則
8.5 次元解析
演習問題
9. 水理学の応用
9.1 災害への対応
9.1.1 河川洪水
9.1.2 津波
9.1.3 高潮
9.2 環境問題への対応
9.2.1 海面上昇
9.2.2 密度流,塩水遡上
9.2.3 地下水
9.2.4 水質
演習問題
引用・参考文献
付録
A.1 覚えておくべき二つのパラメータと五つの数式
A.2 主要な水理学関連用語の日英対訳表
A.3 水理学の歴史年表
演習問題解答
索引
コラム
コラム1:水理学という学問分野と実社会
コラム2:浮体の水理学,土木工学と船舶工学の境界領域
コラム3:管路の設計と水理学
コラム4:河川の計画と水理学(開水路の水理)
コラム5:河川施設の設計と水理学
コラム6:高度な氾濫解析と水理学
コラム7:海岸防災・地域の防災と水理学
コラム8:高潮の常識を変えた台風ハイヤン
コラム9:感潮域の水理
-
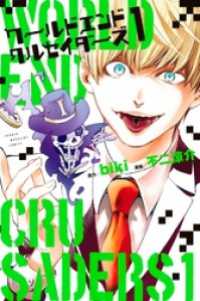
- 電子書籍
- ワールドエンドクルセイダーズ(1)
-
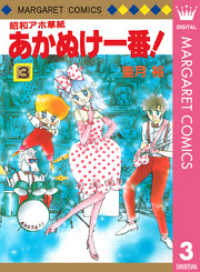
- 電子書籍
- 昭和アホ草紙 あかぬけ一番! 3 マー…